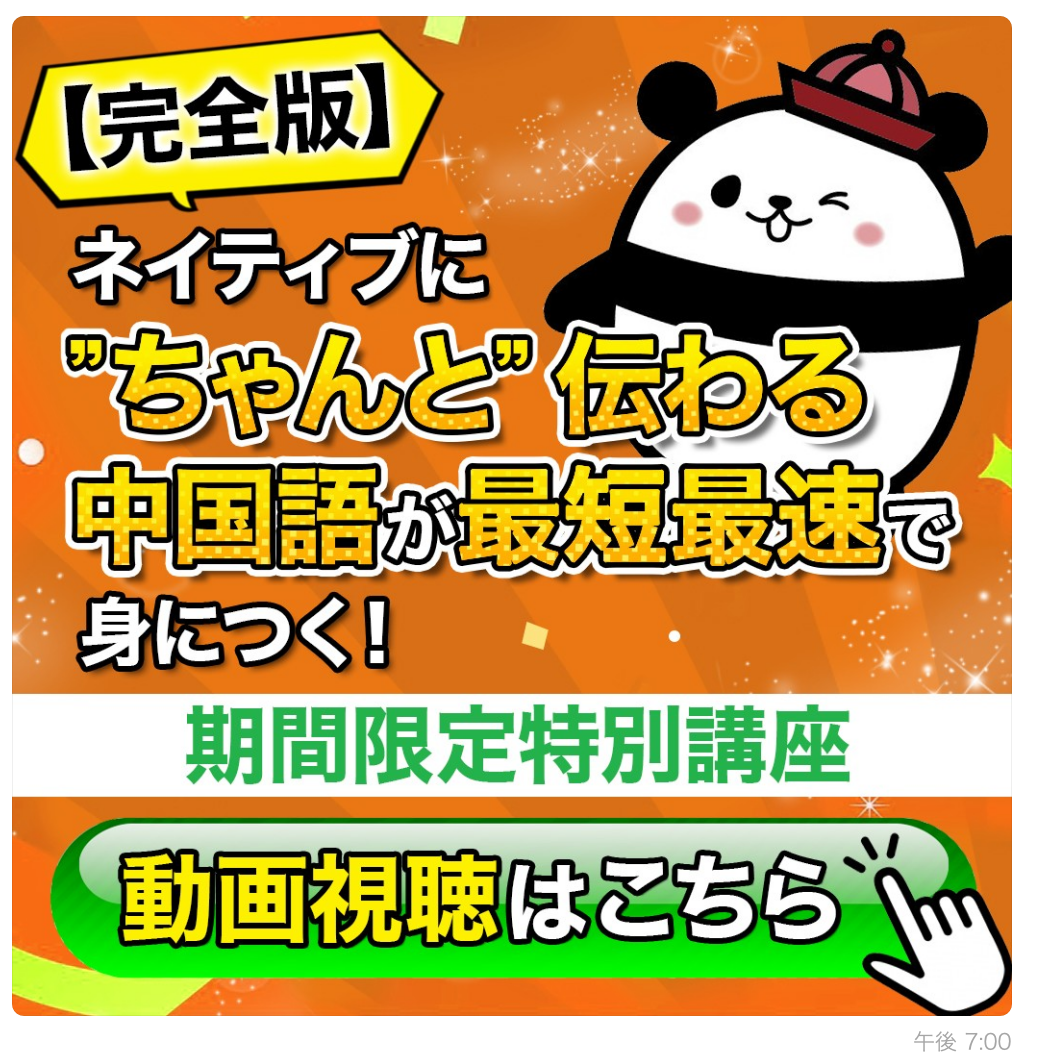
\ 期間限定動画無料配布中 /
中国語検定はどのように勉強したら良いのでしょうか?
中国語学習中の方は、中国語検定の取得を目標とすることも多いですよね。
中国語検定は下から準4級・4級・3級・2級・準1級・1級と6段階のレベルに分かれており、合格できればモチベーションアップにもなります。
試験には出題傾向があり、各級にあった勉強方法で学習をすることが重要です。
この記事では、中国語検定に合格できる勉強方法、各級対策の勉強方法、各級対策のおすすめの参考書を紹介します。
ぜひこの記事で紹介する勉強方法やおすすめの参考書を参考に、中国語検定の合格を目指しましょう!

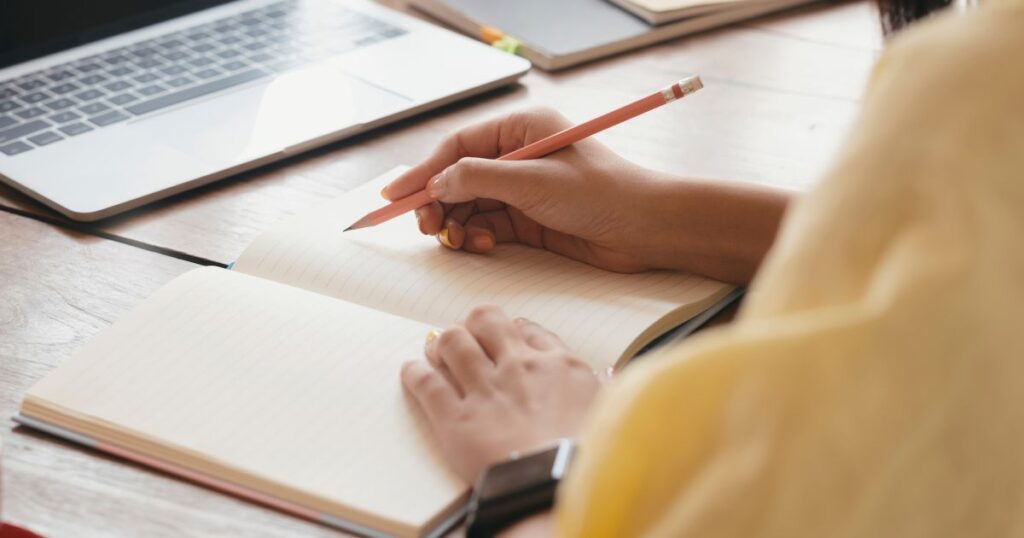
中国語検定に合格できる勉強法を紹介します。
各級によって出題内容は変わってきますが、基本的な学習方法はどの級も共通しています。
以下の3点を意識して学習を進めましょう。
【関連記事】HSKとは?初心者におすすめの勉強方法や人気の参考書を紹介
中国語検定に合格するためには、単語の暗記が最重要です。
どの級も語句に関する出題が必ずあります。
リスニングや読解問題においても、知らない単語ばかりの文は理解することができません。
各級に必要な単語は以下のとおりです。
単語帳やテキストの単語一覧などを利用して、出題範囲の単語は確実に覚えるようにしましょう。
過去問題集で出題された文法は要チェックです。
直近2〜3回の過去問を解くと、毎回似たような文法が問われていることに気づきます。
中国語検定は出題傾向の変動が少なく、過去に出題されている文法は、次の試験でも出題される可能性が高いです。
問題集を利用して重点的に練習しましょう。
中国語検定のリスニング問題では、聞き取れる部分をしっかり理解することが重要です。
聞き取れないところに気を取られていると、音声がどんどん進んでしまい、本来聞き取れるはずの部分まで聞き逃してしまいます。
短文の場合は聞き取れない問題は諦めて、聞き取れる問題に集中するのが得策です。
長文の場合は前後関係から推測できることも多くあります。
聞き取れない単語があっても焦らずに、聞き取れる部分をしっかりと理解して設問に答えていきましょう。
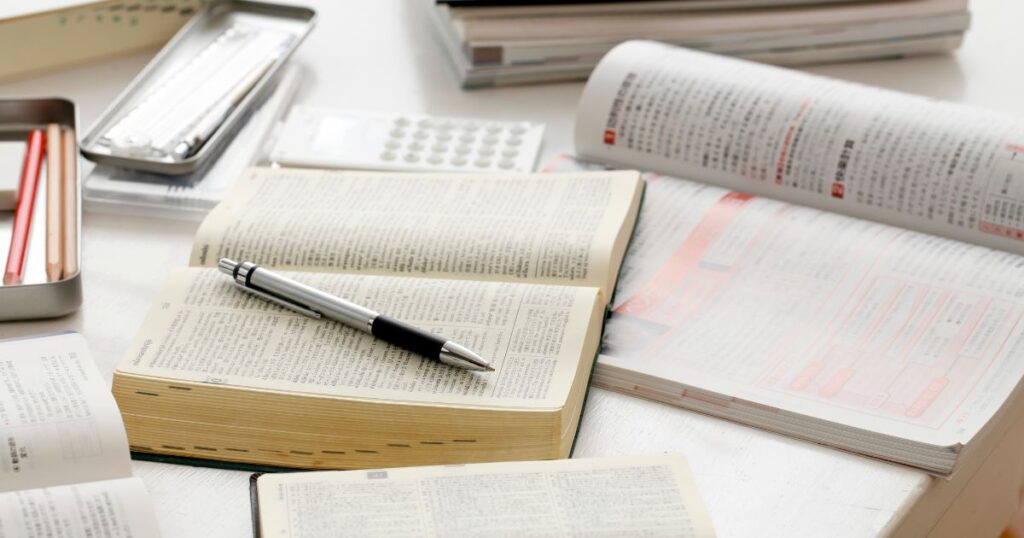
中国語検定の各級対策の勉強法を紹介します。
どの級でも共通して必要な対策は、過去問を解くことです。
過去問を解くことで、出題傾向や形式を把握でき、自分の苦手分野がわかるからです。
過去問を解くこと以外の、各級対策の勉強法を紹介します。
各級に合った対策の勉強法で合格を目指しましょう。
【関連記事】ゲーム感覚で楽しみながら中国語学習ができるおすすめの11個のアプリやツール
中国語検定準4級の認定基準は、以下の通りです。(各級の認定基準は中国語検定公式ホームページより抜粋)
大学の第二外国語で半年以上の学習程度であり、難しいレベルではありません。
中国語検定準4級レベルの単語(漢字、ピンイン、意味)を覚えて、文法の基礎を勉強しましょう。
単語は、漢字とピンインと意味、全てを覚える必要があります。
文法問題は難しい問題はあまりないので、基礎を覚えれば大丈夫でしょう。
リスニングでは正しいピンインを選ぶ問題もあるので、正しい発音を覚えることも重要です。
中国語検定4級の認定基準は、以下の通りです。
中国語学習者の最初の目標となることも多いのが、中国語検定4級です。
準4級と比べて難易度は若干高めですが、単語と文法の基礎をしっかり勉強すれば合格することはできます。
リスニングと筆記ともに、準4級と比べて文章が長くなるので、過去問を解いて慣れておきましょう。
中国語検定3級の認定基準は、以下の通りです。
中国語検定を初めて受験する際、準4級や4級の内容が簡単だと感じる場合は、いきなり3級を受ける人もいるでしょう。
中国語学習初心者にとって中国語検定3級は簡単ではありませんが、きちんと勉強をして対策をしていれば、一発で受かる可能性もありますよ。
中国語検定3級レベルの単語や文法を覚えたうえで、過去問で7割以上取れたら、中国語検定3級に受かる実力があると言えます。
3級は4級と比べてだいぶ難しいので、日常的に中国語を聞いて、耳を慣らすことも重要です。
中国語検定2級の認定基準は、以下の通りです。
中国語検定2級は中国語の基礎をマスターした中級レベルであり、ビジネスでも中国語を使えるレベルであると言えます。
それだけレベルが高く、合格率は20%後半~30%ほど。
基本的な文法は理解し、シャドーイングやディクテーションを行ってリスニング力をあげることも必要です。
中国語検定準1級の認定基準は、以下の通りです。
中国語検定準1級は、HSK6級よりも難しく、非常に高いレベルです。
文法の理解や語彙力を伸ばすだけではなく、成語や文学、また文化的知識や中国事情に関しても幅広い知識が必要になり、翻訳のパートでは日本語力も試されます。
過去問を何度も解いて、足りないと思われる内容を工夫して勉強することが必要ですよ。
中国語検定1級の認定基準は、以下の通りです。
中国語検定1級のレベルは非常に高く、ネイティブでも合格することが難しいと言われています。
準1級までの内容よりも、更に深い知識が求められます。
二次試験の面接では通訳の試験があり、二次試験合格者は年間10数名しかいません。
過去問を何度も解いて苦手な内容を重点的に勉強し、別途面接の対策も必要になります。
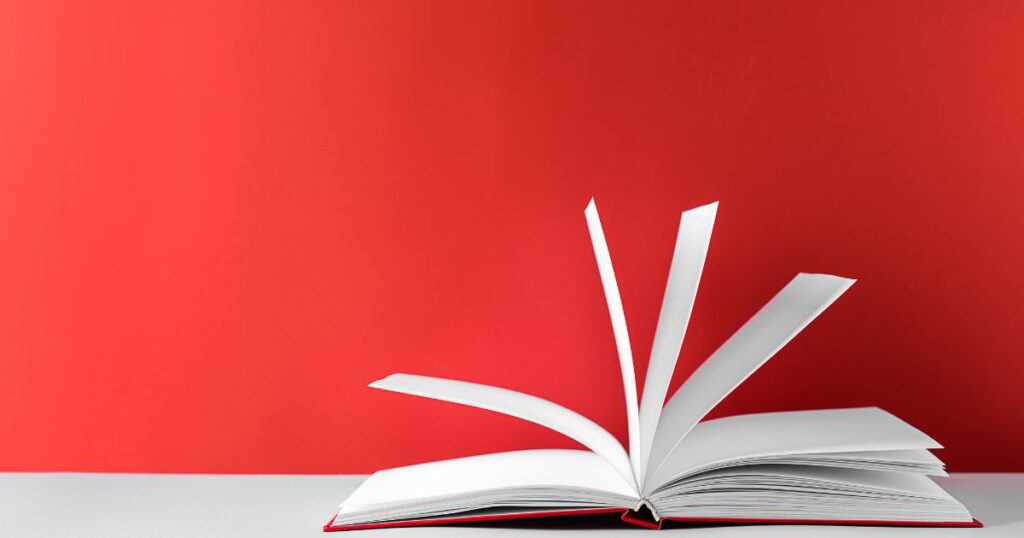
中国語検定の各級対策の参考書を紹介します。
過去問は中国語検定協会出版からCD付きで販売されています。
検定対策に役立つ参考書や問題集、単語帳は以下のとおりです。
【関連記事】全レベルまとめ!HSK対策におすすめ参考書と学習の進め方
「Whyにこたえるはじめての中国語の文法書」は、中検準4級受験者だけではなく、中国語学習初心者全員におすすめですよ。
「中検(R)公式ガイドブック 準4級・4級 模擬テスト各級1回付き」は準4級と4級が一緒になっているため、同じ参考書です。
「本気で学ぶ中国語」シリーズは、中国語検定の対策だけではなく、中国語全体のレベルアップに役立つ参考書です。
準4級~3級は、公式ガイドブック、トレーニングブックシリーズ、完全攻略シリーズ、キクタンなど、おなじみのシリーズが並んでいますね。
3級から、トレーニングブックは2冊に分かれます。
中検2級以上は、公式ガイドブックがありません。
おなじみのトレーニングブックシリーズも良いのですが、筆記問題の対策には「中国語検定2級徹底攻略 筆記問題完全マスター」が特におすすめですよ。
中検準1級以上になると、参考書の種類が非常に少なくなってきます。
上記で紹介しているのは数少ない中検準1級の参考書で、どれもおすすめです。
中検1級の参考書は、過去問以外にはありません。
中検準1級の参考書を使う以外には、中国語のニュースを読んだり聞いたりと自分で工夫をして勉強することが必要です。
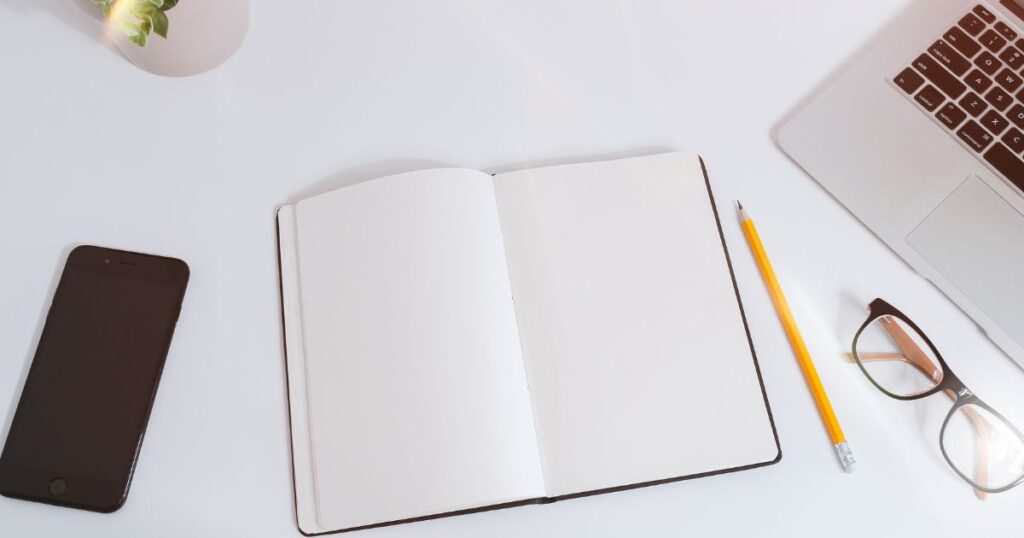
この記事では、中国語検定に合格できる勉強方法、各級対策の勉強方法、各級対策のおすすめの参考書を紹介しました。
中国語学習初心者さんは準4級の内容から学習を始め、3級合格が1つの目標となります。
2級は難易度がぐんと高くなり、中国語ができると認められるレベルです。
準1級以上は通訳など中国語を使った専門的なお仕事をする人向けです。
中国語検定は出題形式や傾向が比較的はっきりしており、必要な単語を覚えること、過去問を中心とした対策をすることで効率的に合格を目指すことができます。
中国語学習が思うように進まない、試験は合格したけど話せないというときは、毎日中国語公式LINEまでご相談くださいね!
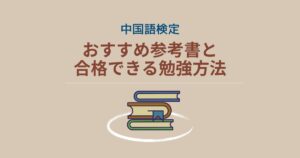
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
