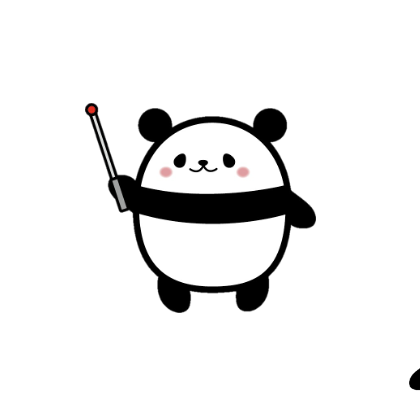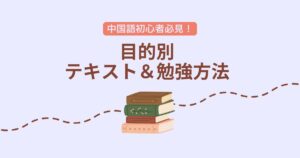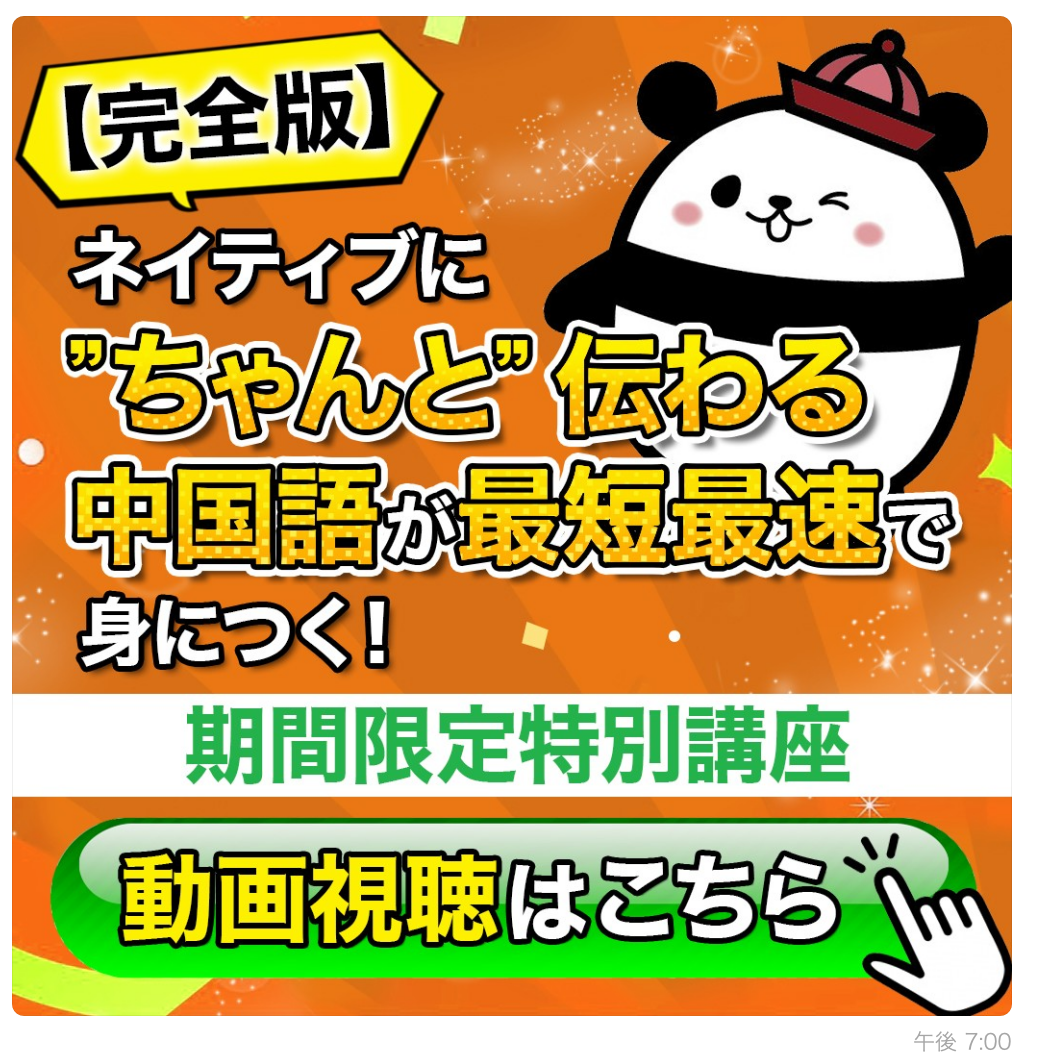
【中国語初心者必見】もう迷わない!目的別おすすめテキスト&勉強法
この記事でわかること
- 中国語の教材は、目標・学習スタイル・予算に応じて、発音重視の物を選ぼう。
- 発音・文法・旅行・会話・試験・単語、中国語の初心者におすすめの目的別テキスト一覧。
- 中国語の発音練習や会話フレーズの学習にはYouTubeやアプリも便利。
中国語の勉強を始めるには、どんなテキストが良いでしょうか?
書店に並ぶ参考書はもちろん、学習アプリ、インターネット動画、HNK講座までいろいろな種類があって迷ってしまいますよね。
さらに、自分に合わないテキストでの独学は、挫折してしまう可能性もあります。
本記事では、中国語の基礎を学べる初心者向けテキストの選び方と、目的別おすすめテキスト&勉強法、YouTube・アプリ・ポッドキャストなどの無料ツール活用法を紹介します。
中国語学習の第一歩を踏み出しましょう。
目次
中国語初心者向けテキストの選び方:あなたの目的とレベルに合った1冊を!
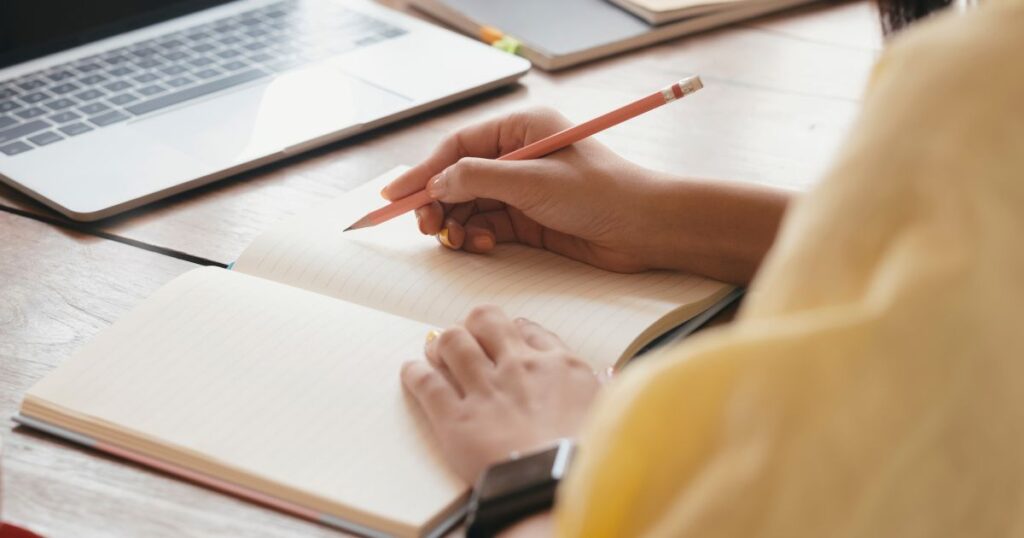
最初に、中国語初心者向けテキストの選び方を紹介します。
目的やレベルに合った教材は効率的にレベルアップでき、モチベーションも維持しやすくなりますよ。
- 中国語勉強初心者テキスト選びの3つのステップ:目標設定・学習スタイル・予算
- 【要注意】中国語初心者テキスト選びでよくある失敗と対策
中国語勉強初心者テキスト選びの3つのステップ:目標設定・学習スタイル・予算
これから中国語の勉強を始める、もしくは、すでに勉強しているけれどなかなか上達しないという場合は、まず「学習目標」を明確にし、続けやすい学習スタイルを探しましょう。
旅行で使いたいのか、ビジネスで活用したいのか、資格取得を目指すのかなどによって、それぞれに適した教材があります。
また、勉強と言うと机に向かって教科書とノートで勉強するイメージがありますが、これではなかなかやる気にならない場合、動画を見たりアプリで勉強する方法もあります。
そして、教材選びには「予算」も外せない要素です。
インターネット上には便利な無料学習ツールがたくさんあります。
有料の教材とうまく組み合わせて使えば、教材費を抑えることも可能です。
テキスト選びに悩んだら、「何のために学ぶか」「どう学ぶのが自分に合うか」「予算はいくらか」の3点を基準に選びましょう。
【要注意】中国語初心者テキスト選びでよくある失敗と対策
中国語初心者がテキスト選びでよくする失敗は、主に3つあります。
1つ目は発音学習を軽視した教材選びです。
中国語は声調が意味を左右する言語であり、日本語にない発音も多いため、カタカナ表記に頼った発音では聞き取ってもらえません。
教材はピンインと呼ばれる発音表記があり、音声が聞けるものを選びましょう。
2つ目は自分のレベルに合わない難易度の教材を選んでしまうことです。
仮に目標がHSK4級だとしても、いきなりHSK4級の教材から始めてしまうと、何もかもチンプンカンプンでくじけてしまいます。
HSK1級教材や他の入門書から始め、徐々にレベルアップするのが効果的です。
3つ目は学習プランなしの場当たり的な教材購入です。
様々な教材を少しずつ購入するものの、どれも途中で放棄して結局何も身につかないのでは、「教材難民」になってしまいます。
教材は自分の目的とレベルに合っていて、かつやる気になるものがおすすめです。

可能であれば、書店で手に取ってパラパラとめくってみてください。
発音→基礎文法・語彙→会話練習→専門分野と段階的に進めることで、効率よく確実に上達できますよ。
【目的別】中国語初心者におすすめの勉強法と教材
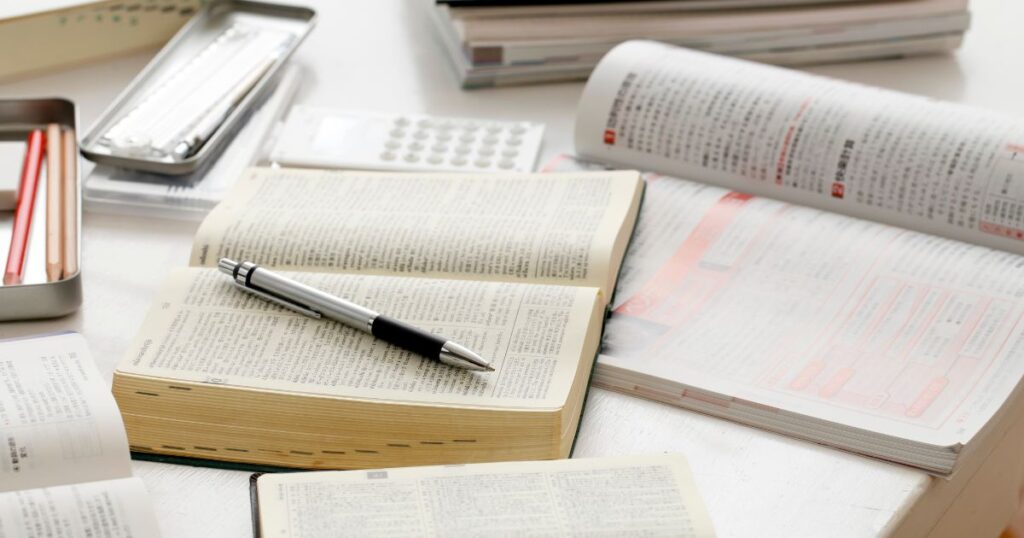
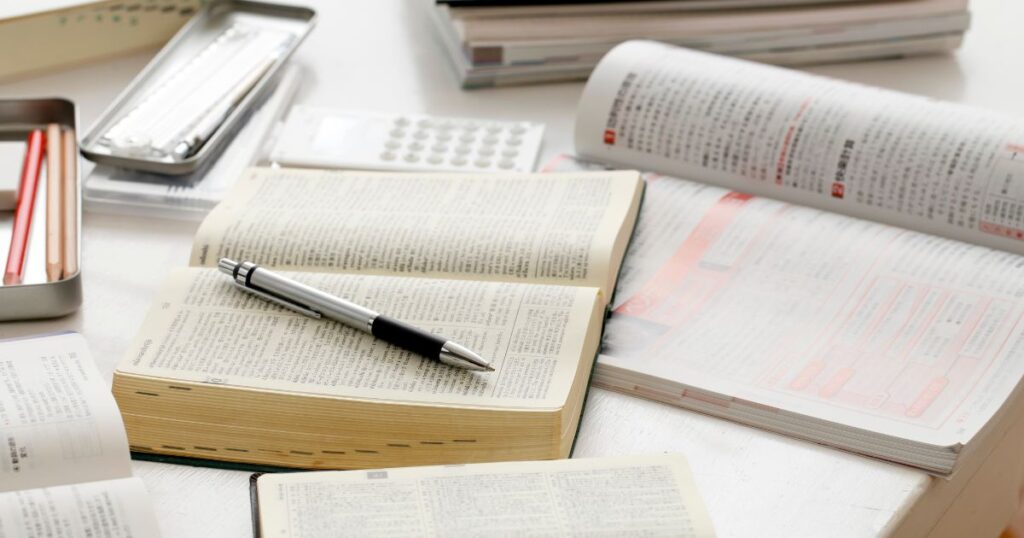
この章では、中国語を独学で学ぶ初心者のための効果的な学習方法とおすすめテキストを紹介します。※本記事記載のテキストは2025年3月現在の価格です。
中国語は発音が重要な言語です。
発音からスタートし、その後は目的に合わせて選んでみてくださいね。
- 【発音】ピンインと声調を徹底攻略!
- 【文法】基礎からしっかり!挫折しない文法テキスト&勉強法
- 【旅行】現地で役立つ実践フレーズを覚えよう!
- 【会話】オンライン学習も活用!スピーキング力UPの秘訣
- 【資格】中国語検定・HSK対策におすすめの問題集&過去問
- 【単語】日常会話~HSK対策まで!効率的な単語学習
【発音】ピンインと声調を徹底攻略!
中国語学習は、まず発音(ピンイン・声調)から始めます。
中国語は声調によって意味が変わる言語のため、発音が不正確だと単語や文法を覚えても相手に意図が伝わりません。
日本語にない発音も多く、カタカナ読みに頼ると後々修正が難しくなります。
発音学習におすすめのテキストは以下の3冊です。
- 『紹文周の中国語発音完全マスター』アスク出版、1,980円(税込)
- 『音が見える!中国語発音がしっかり身につく本』コスモピア、1,980円(税込)
- 『<CD付><Web動画付>日本人のための中国語発音完全教本』アスク出版、2,420円(税込)
発音学習のポイントは、ネイティブの音声を繰り返し聞く、自分の発音を録音して比較する、口の形や舌の位置に注意することです。
特に四声(四つの声調)は手で形を描きながら練習すると効果的です。
毎日15分程度の発音練習を習慣化していきましょう。
【文法】基礎からしっかり!挫折しない文法テキスト&学習法
中国語文法は英語と同様にSVO(主語+動詞+目的語)の語順ですが、時制変化や冠詞がなく一見簡単に感じられます。
しかし、助詞「了」や「的」の使い方、疑問文の作り方、量詞(助数詞)の使用など独特の概念もあるため、これらを体系的に学ばないと中級以上へのステップアップが難しくなります。



基礎からしっかり学んでいきましょう。
初心者におすすめの文法テキストは以下の2冊です。
- 『新ゼロからスタート中国語 文法編』王丹 著、Jリサーチ出版、1,320円(税込)
- 『why? にこたえるはじめての中国語の文法書』同学社、2,750円(税込)
『新ゼロからスタート中国語 文法編』は45の「文法公式」でわかりやすく解説されており、HSK1〜3級の対策にも役立ちます。
『why?にこたえる…』は20年ものロングセラーです。
文法学習は、例文を声に出して読み、暗記することで文法パターンが自然と身につきます。
学んだ文法を使って自分で例文を作る練習も効果的な学習方法です。
毎日中国語ブログでも基本文法を解説しています。
【関連記事】中国語の基本をマスター|基本文法5選と日常会話フレーズ15個
【旅行】現地で役立つ実践フレーズを覚えよう!
せっかく中国に行く機会があるのなら、現地でも中国語を話してみたいですよね。
中国は英語が通じないこともあるので、飲食や買い物などのフレーズは覚えておくと便利です。
中国旅行におすすめの中国語教材は以下の2冊です。
どちらもイラストや色分けで見やすい構成になっています。
- 『旅の指さし会話帳④ 中国語』麻生晴一朗 著、情報センター出版局、1,540円(税込)
- 『はじめての中国語旅行会話』曲 婉琴 著、アスク出版、1,980円(税込)
【会話】オンライン学習も活用!スピーキング力UPの秘訣
会話力向上には、早い段階から積極的に話しましょう。
中国語学習では「言えれば聞けて、聞ければ言える」という相乗効果があります。
会話学習におすすめのテキストは次の3冊です。
- 『ゼロからスタート中国語 会話編』王丹 著、Jサーチ出版、1,540円(税込)
- 『すぐに使える中国語会話 ミニフレーズ2000』Jリサーチ出版、1,760円(税込)
- 『CD BOOK 超短文で話せる!ラク覚え中国語』NHK出版、1,980円(税込)
会話練習の際は、音読とシャドーイング(ネイティブの発話をすぐ後に続けて真似る練習法)が効果的です。
より実践的な会話練習は、HelloTalkやTandemなどの言語交換アプリでネイティブと交流することができます。
最初は挨拶や自己紹介から始め、徐々に日常会話、趣味の話題へと広げていきましょう。
日本語で考えてから中国語に訳すと長くなってしまうので、簡単な短い文で言うのがコツです。
さらに、ChatGPTなどのAIツールを活用した会話練習や、自分の発話を録音して振り返ることも効果的な方法です。
【試験対策】中国語検定・HSK対策におすすめの問題集&過去問
中国語の資格試験対策には、試験形式に特化した問題集と過去問を使用しましょう。
HSKと中国語検定(中検)は出題形式や評価基準が異なるため、それぞれに合った対策が必要です。
おすすめのテキストは以下の通りです。
【HSK(汉语水平考试)】
- 『HSK公認テキスト1級』SPRIX、2,618円(税込)
- 『HSK公認テキスト2級』SPRIX、2,838円(税込)
- 『HSK公式過去問集 2021年度版 1級』SPRIX、2,750円(税込)
- 『HSK公式過去問集 2021年度版 2級』SPRIX、2,970円(税込)
【中国語検定】
- 『<音声DL>出るとこだけ!中国語検定準4級 合格一直線』アスク出版、1,980円(税込)
- 『<音声DL>出るとこだけ!中国語検定4級 合格一直線』アスク出版、2,200円(税込)
これらの教材はさらに上の級もあります。
HSKは1級が最も基礎、中国語検定は準4級が最も基礎です。
試験対策では、まず目標級の出題範囲と形式を理解し、過去問で現状を確認した上で、弱点強化と総合対策のバランスを取りながら学習を進めましょう。
特にリスニングは毎日練習することが効果的です。
各試験の特徴については、こちらの記事もご覧ください。
【関連記事】中国語検定とHSKはどっちがおすすめ?違いや受けるべき級を解説!
【単語】日常会話~HSK対策まで!効率的な単語学習法
中国語の単語は漢字で表記されるため、日本人には有利に感じられますよね。
しかし、同じ漢字でも意味や使い方が異なるものも多数あり、注意が必要です。
そして、何より、声調を含めた正確な発音を覚えないと実践では使えません。
単語学習は、発音、漢字、意味の3つを覚えましょう。
おすすめの単語帳は以下の通りです。
- 『キクタン中国語【入門編】中検準4級レベル』アルク出版、1,980円(税込)
- 『キクタン中国語【初級編】中検4級レベル』アルク出版、1,980円(税込)
- 『<音声DL>合格奪取!新HSK1~4級 単語トレーニングブック』アスク出版、1,980円(税込)
- 『新ゼロからスタート中国語単語BASIC1000』Jリサーチ出版、1,320円(税込)
- 『音声DL版 パッと見てわかる!中国語単語イラスト図鑑』アスク出版、1,980円(税込)
『キクタン中国語』は中国語検定のレベル別に対応しており、チャンツという音楽に乗せて単語を覚える学習法を採用しています。
HSK対策なら『合格奪取!新HSK単語トレーニングブック』が意味別に分類されていて効率的です。
効果的な単語暗記のコツは、音声を聞きながら自分でも発音し、頻繁に復習することです。
忘れる前に復習すると、覚えたことが定着しやすくなります。
中国語学習を加速させる!無料ツール&リソース徹底活用術
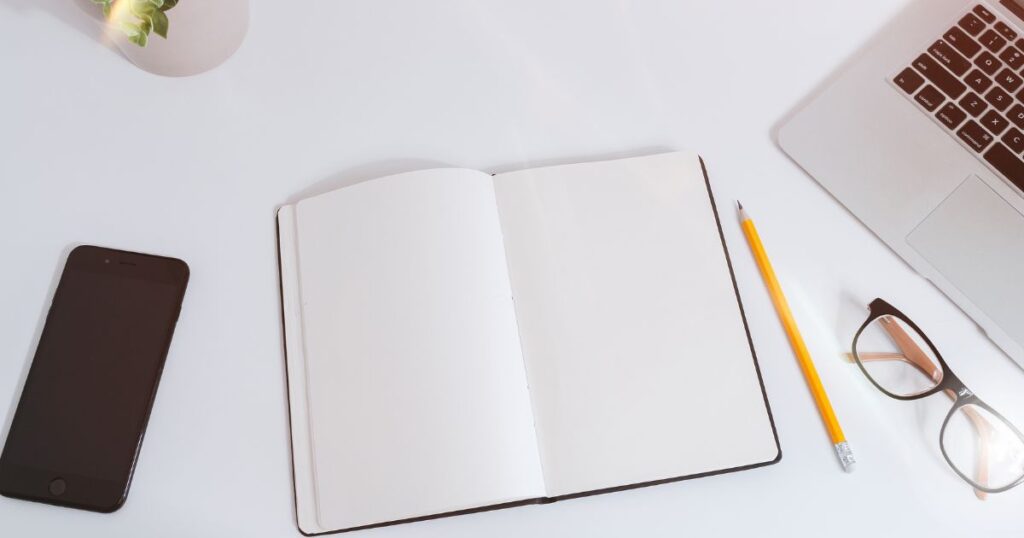
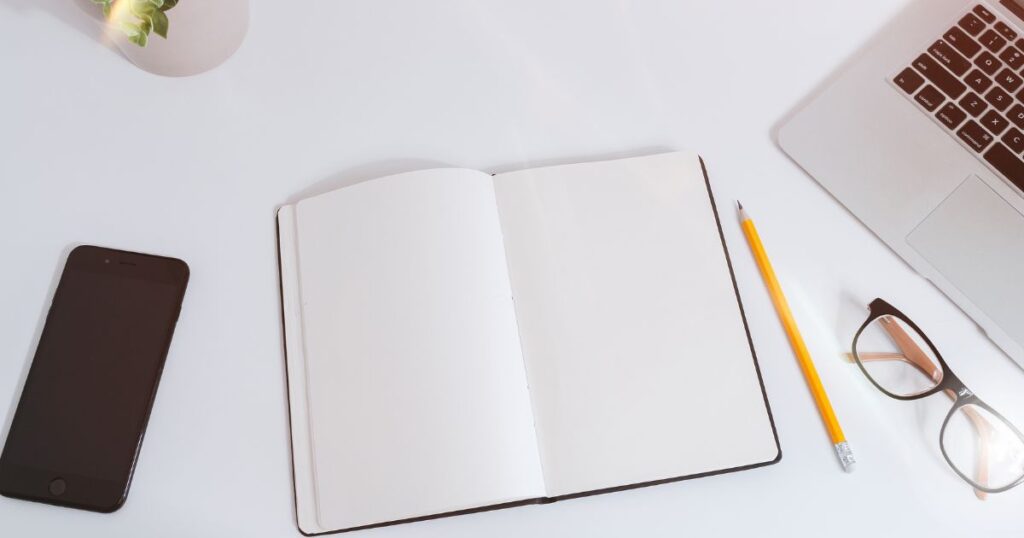
この章では、中国語学習を効率的に進めるための無料ツールやリソースを紹介します。
これらの多くは、音声を聞くことができるのが最大の利点です。
大いに活用していきましょう。
- 【YouTube】初心者向け動画、発音練習、おすすめチャンネル
- 【アプリ】ゲーム感覚で楽しく学習!単語、文法、会話練習に
- 【ポッドキャスト】移動時間も有効活用!リスニング力UP
- 【NHK】中国語講座、体系的に学ぶ
【YouTube】初心者向け動画、発音練習、おすすめチャンネル
YouTubeは中国語学習、特に発音練習や会話表現の習得に非常に便利な無料ツールです。
ネイティブの口の形や舌の位置が確認でき、音声を聞きながら学習できるのが大きなメリットです。
おすすめチャンネルは以下の通りです。
【発音】
- 李姉妹ch.
- ヤンチャンCH/楊小溪
- 毎日中国語 【50万回再生!】この動画1本で全中国語発音400種類を完全網羅【全ての母音&子音を徹底解説】
日本人向けに発音のコツを丁寧に解説しています。
【初心者向け基礎】
- カエルライフ
- Nihaoabc
基礎が分かりやすくまとめられています。
【聞き流し】
ネイティブが使う短くて簡単なフレーズ動画を紹介しています。
発音学習では、ネイティブの口の動きをよく観察し、一時停止や繰り返し機能を活用しながら真似てみることが効果的です。
さらに、視聴後に学んだフレーズを声に出して復唱したり、シャドーイングを行ったりすることで、受動的な視聴から能動的な学習へと転換できます。
【アプリ】ゲーム感覚で楽しく学習!単語、文法、会話練習に
中国語学習アプリは、スキマ時間を有効活用できます。
即時フィードバックや進捗管理機能により、モチベーション維持がしやすいという特徴もあります。
おすすめは以下の3つです。
- Hello Chinese
- ChineseSkill
- Duolingo
Hello Chineseは、HSK3級レベルまでの500以上の語彙、120以上の文法ポイントを無料で学べ、ネイティブスピーカーの動画や音声認識機能が充実しています。
ChineseSkillはHSK2級程度までで、詳細な文法解説とスピーキング練習が特徴です。
Duolingoはゲーム感覚でバランスよく学べます。
アプリを最大限に活用するには、自分に合ったものを1〜2つ選び、毎日10〜15分程度の「小さな学習ノルマ」を設定しましょう。
テキスト学習や実際の会話練習とバランスよく組み合わせることも大切です。
【ポッドキャスト】移動時間も有効活用!リスニング力UP
中国語ポッドキャストは視覚に頼らず学習できるため、通勤・通学や家事の時間を有効活用できます。
また、ネイティブの自然な会話スピードやリズムに触れることで「生きた中国語」のニュアンスが身につきます。
初心者向けのおすすめポッドキャストは以下の2つです。
- ChineseClass101
- Slow Chinese Podcast
「ChineseClass101」は基礎からしっかり学べるコンテンツで、各エピソードには英語の解説もあります。
「Slow Chinese」はゆっくりとした中国語で話されるので、リスニング力を徐々に高めたい方に最適です。
効果的に活用するには、自分のレベルに合ったシリーズを選び、毎日聴く習慣をつけましょう。
初めは全体の雰囲気や繰り返し出てくるフレーズに注目し、慣れてきたら同じエピソードを複数回聴くことで理解度を深めていきます。
さらに重要なフレーズを声に出して復唱したり、ノートに書き留めたりするのも良い方法です。
【NHK】中国語講座で体系的に学ぶ
NHKの中国語講座は、言語教育の専門家や経験豊富な講師陣による質の高いカリキュラムが特徴で、独学の弱点である「体系的な学習」を補完できます。
NHK「まいにち中国語」はラジオ第2放送で毎日放送されており、ウェブサイトやアプリ、ポッドキャストでも過去の放送を一定期間無料で聴くことができます。
「テレビで中国語」は映像で中国の文化や風景も楽しみながら学習できる番組です。
NHKの中国語講座は、定期的に視聴・聴取する習慣をつけましょう。
公式テキストがあると学習効果がさらに高まります。
【Q&A】中国語学習の疑問を解決!よくある質問集


この章では、中国語学習者からよく寄せられる疑問にお答えします。
- 台湾華語を独学で勉強できる初心者向け教材は?
- 「キクタン中国語入門編」はダウンロードできる?
台湾華語を独学で勉強できる初心者向け教材は?
『<音声DL>単語と文法から学ぶ PAPAGO式 台湾華語』(アスク出版)がおすすめです。
台湾華語を学べる教材はあまり多くないのですが、こちらのシリーズは日本語の解説が付いた本格的なテキストです。
台湾華語を独学で学ぶ際は、まず基本的な発音(ピンイン/注音符号)と繁体字の基礎から始めます。
必ず音声教材が付属しているものを選び、発音練習を重視しましょう。



台湾のドラマや映画、音楽も楽しみながら学習するのに効果的です。
「キクタン中国語入門編」はダウンロードできる?
アルクの公式サイトで書籍購入者向けに音声ダウンロードサービスが提供されています。
また「キクタン」専用アプリがApp StoreやGoogle Play Storeから無料でダウンロードでき、一部のサンプル音声が利用できます。
アルクのYouTubeチャンネルでもサンプル音声やチャンツの一部が視聴できる場合があります。
まとめ
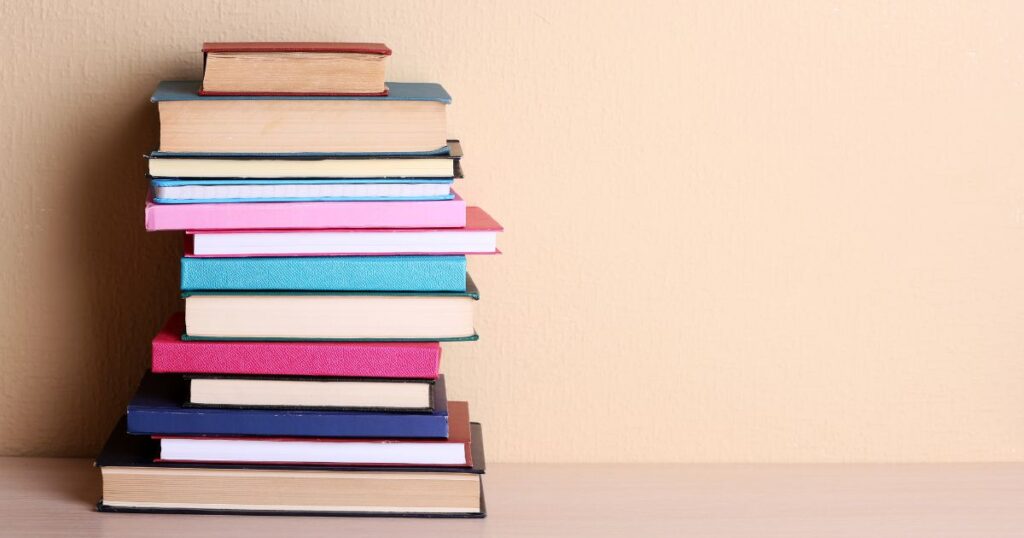
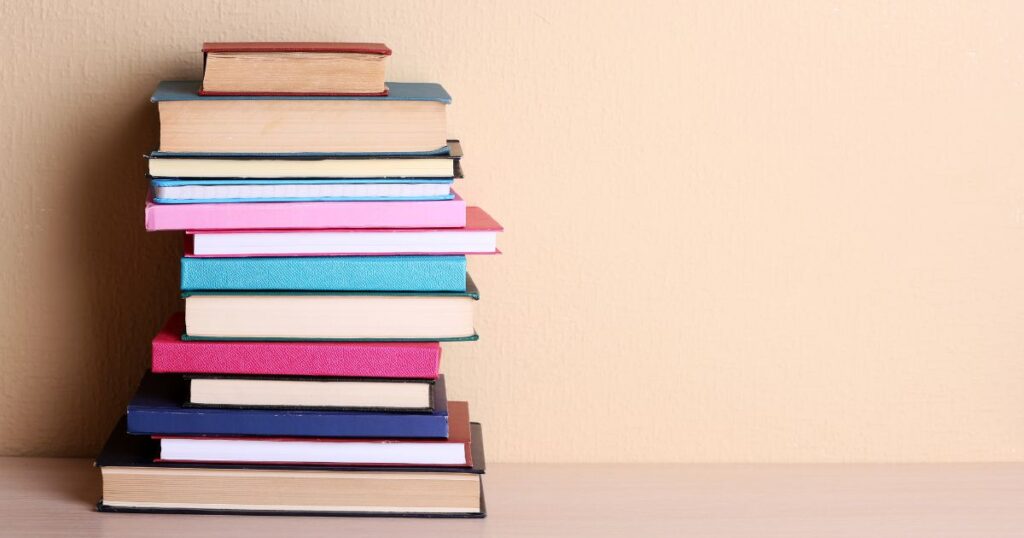
本記事では、中国語初心者向けテキストの選び方と目的別おすすめのテキスト、各分野の勉強法を紹介しました。
教材は目標・学習スタイル・予算に合わせて、続けやすいものを選びましょう。
その際、音声を聞くことができて、ピンイン表記のあるものがベストです。
カタカナ読みでは発音が通じず、コミュニケーションができなくなってしまいます。
また、高い目標を掲げている場合でも、初級から着実にステップアップしていくのがおすすめです。
紙の参考書以外にも、YouTubeや学習アプリ、ポッドキャストなどを併用すると、費用も抑えられて効果的に学習できます。



音読やシャドーイングを通して、練習しながら基礎を身につけていきましょう。
毎日中国語公式LINEでも、お得な中国語情報を配信しています。
ぜひ登録してご覧くださいね。