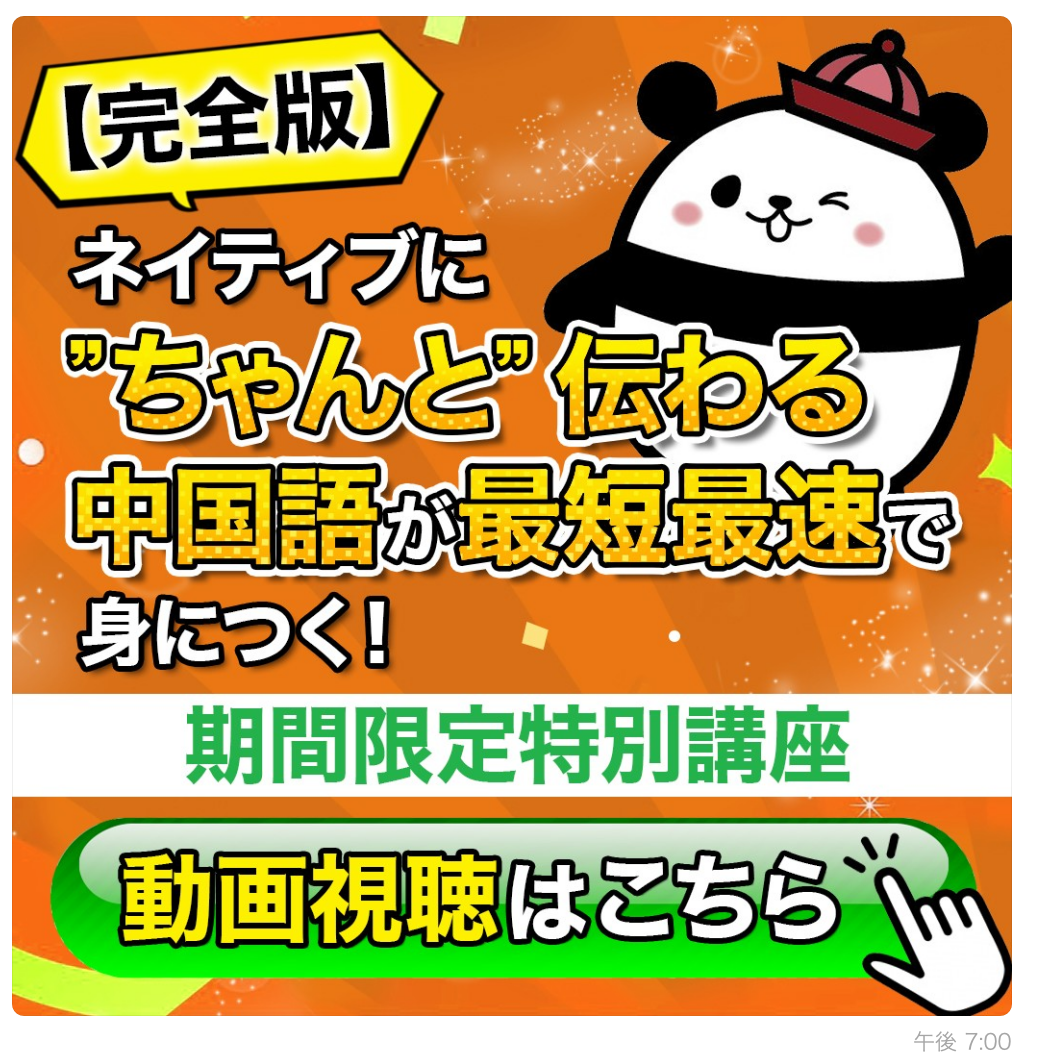
\ 期間限定動画無料配布中 /
台湾語と中国語に発音の違いはありますか?
台湾で話されている公用語は実は「台湾語」ではなく、私たちが一般的に「台湾華語」と呼んでいる言葉です。
台湾華語は中国大陸の普通話(標準中国語)と相互理解が可能ですが、発音面や語彙にやや違いがあります。
また、「台湾華語」とは別に「台湾語」も存在し、こちらは普通話とは意思疎通が困難です。
この記事では台湾華語と標準中国語の発音の違いを比較し、どちらの発音を学ぶべきか、台湾華語を学ぶならどのような方法があるかを解説します。
「生きた中国語」を身につける第一歩を踏み出しましょう。


台湾でコミニュケーションをはかるためには、まず現地の言語事情を知ることから始めましょう。
この章では、台湾で話されている主要な言葉の違いとそれぞれの特徴を解説します。
台湾旅行や留学を考えるとき、多くの人が「台湾語と台湾華語(國語)って何が違うの?」という疑問にぶつかります。
結論から言うと、この2つは相互に会話が成り立たないほど異なる、実質的に「別の言語」です。
台湾華語が公用語として教育やメディアで使われる標準語であるのに対し、台湾語は特定の地域や家庭で話される生活に根ざした言葉です。
言語学的には、どちらも大きな「シナ語派」というグループの親戚ですが、非常に早い段階で枝分かれしたため、発音や文法が大きく異なります。
特に、音の高さで意味を区別する「声調」は、台湾華語の4種類に対し、台湾語には実質7種類(理論上は8種類)も存在します 。
さらに、台湾華語にはない「ッ」で終わるような短い音(入声)や、単語の並び方で声調が変化する「連続変調」という複雑なルールがあり、音の響きが全く異なります 。
例えば「こんにちは」は、台湾華語ではおなじみの「你好(nǐ hǎo)」ですが、台湾語では「汝好(Lí-hó、リーホーに近い音)」となります。
台湾の公共施設やレストランでは基本的に台湾華語が通じますが、特に南部や年配の方との会話では台湾語が使われることもあります。
台湾旅行や短期留学が目的なら、まずは公用語である台湾華語の習得に集中するのが効率的です。
台湾華語と中国本土の普通話(標準中国語)は、例えるなら「イギリス英語とアメリカ英語」のような関係です。
ルーツは同じ北京官話なので基本的に意思疎通可能ですが、発音の響きや日常で使う単語にやや違いがあり、漢字の字体も異なります。
| 違い | 台湾華語 | 普通話 |
| 漢字 | 繁体字 | 簡体字 |
| 発音表記 | ボポモフォ | ピンイン |
| 発音の雰囲気 | 柔らかい | 普通(地域による) |
| 抑揚 | 小さい | 大きい |
| そり舌音 | あまり使わない | よく使う(特に北の地域) |
| -nとngの区別 | あまり区別しない | 区別する |
| 軽声 | 使わない | 使う |
台湾華語は、歴史的な背景から発音が全体的に柔らかく、日常会話には「おじさん」「おばさん」といった日本語由来の単語もあります。
また、そり舌音がほとんどないので、日本人にとっては普通話より発音しやすいことが多いです。
大陸の人が台湾の人の発音を聞くと、一発で「台湾人だ」と分かるそうです。
そのくらい、発音の雰囲気に違いがあります。
台湾では地域や世代によって言語使用状況に差があり、特に北部と南部、若年層と高齢者層で使用言語の傾向が異なります。
台北を中心とする北部や都市部では台湾華語が主流である一方、台南や高雄などの南部や農村部では台湾語の使用頻度が高くなります。
また、若い世代は主に台湾華語を使用しますが、高齢者層は台湾語を日常的に使うことが多いです。
例えば、台北の近代的なオフィスビルでは台湾華語が当たり前に使われる一方、台南の活気あふれる伝統市場を歩けば、そこかしこから台湾語が聞こえてきます。
若者同士の会話は基本的に台湾華語ですが、祖父母との会話では台湾語に切り替える人もいます。
さらに、客家語や原住民言語など、その他の少数言語も地域によって使用されています。
台湾旅行や短期留学の際は、台湾華語を中心に学習すれば基本的なコミュニケーションに問題はありません。
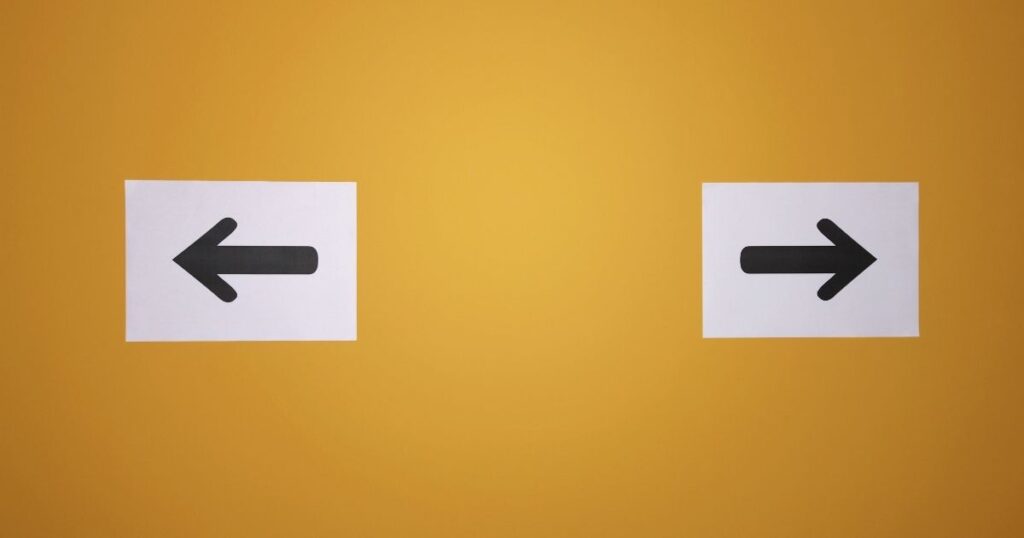
台湾の人と話したときに感じる「なんだか優しい響きだな」という印象、その正体は中国本土の普通話との発音の違いにあります。
この章では、日本人学習者が特に知っておきたい4つの大きな発音の違いを、具体例とともに解説します。
多くの日本人学習者が中国語学習でつまずくポイントの1つが、舌をそらして発音する「そり舌音」です。
しかし、台湾華語ではこのそり舌音が非常に弱い、あるいはほとんど使われないため、日本人にとって圧倒的に発音しやすいという大きなメリットがあります。
普通話ではピンインでzh, ch, shと表記されるそり舌音は、台湾華語ではそり舌ではない歯茎音のz, c, sに近い音で発音される傾向があります。
これは台湾華語特有の「柔らかい」印象を生み出す要因の一つです。
| 例 | 台湾華語 | 普通話 |
| 知道 | zī dào / ヅーダオに近い | zhī dào |
| 好吃 | hǎo cī / ハオツーに近い | hǎo chī |
普通話の「zh, ch, sh」の発音で挫折しかけた方も、台湾華語なら大丈夫。
舌をリラックスさせたまま、自然な発音で通じる喜びを味わえるはずです。
台湾華語がメロディーのように優しく聞こえるもう1つの秘密は、声調の抑揚にあります。
普通話に比べて音の高低差がなだらかで、特に「第3声」の発音が大きく違います。
台湾華語と普通話は共に4つの声調(四声)を持ちますが、台湾華語では音の高低差が普通話ほど極端ではありません。
普通話の第3声は、日本語の「あ〜あ(がっかり)」のように、一度ぐっと音を下げてから上げる「V字型」の音です。
一方、台湾華語ではこの後半の上昇部分がなく、船の汽笛のように「ボーッ」と低く平坦に発音されることがほとんどです。
例えば「我(wǒ)」という単語は第3声ですが、台湾華語では単に低い音で平らに発音する傾向があります。
この全体的にフラットな発音が、台湾華語特有の「優しさ」を生み出しています。
また、台湾華語では会話の最後に「喔 (o)」「啊 (a)」「啦 (la)」といった柔らかい響きの語気助詞を頻繁に付け加えることも、親しみやすい印象を強めています。
台湾華語では、末尾の鼻音「n」と「ng」の区別が普通話ほど明確ではなく、多くの話者が両者を混同して発音する傾向があります。
普通話では、舌先で作る前鼻音の-nと、舌の根元で作る後鼻音の-ngを明確に区別しますが、台湾華語話者は両者を明確に区別せず、どちらも-nに近い音で発音する傾向があります。
これは単なる「訛り」や「間違い」ではなく、台湾語(閩南語)の影響も受けた、台湾華語の発音ルールとして認識されています。
例えば「分(fēn))」と「豐(fēng)」の発音が非常に似て聞こえることがあります。
同様に、「前(qián)」と「強(qiáng)」の発音も区別が曖昧になることがあります。
この鼻音の区別は、多くの日本人学習者が苦手とするところですが、台湾華語ではその違いが曖昧なため、学習の負担が軽くなる嬉しいポイントと言えるでしょう。
普通話では、単語の2音節目を軽く添えるように発音する「軽声」が多用されますが、台湾華語ではこの軽声がめったに使われません。
その代わり、一音一音を、それぞれの声調通りにしっかりと発音するのが特徴です。
例えば「もの」を意味する「東西」は、普通話では「dōng xi」(1声+軽声)と発音しますが、台湾華語では「dōng xī」(1声+1声)と発音されることが多いです。
台湾華語を学ぶ際は、軽声に関する普通話の規則にとらわれず、各音節の本来の声調を維持して発音する練習をするとよいでしょう。

中国語学習を始めようとするとき、最初に「文字」と「発音記号」という2つの壁に直面します。
台湾で使われる文字や記号は、中国本土のものとは異なります。
この章でそれぞれの特徴を理解しましょう。
台湾で使われているのは、日本の旧字体にも似た、伝統的で画数の多い「繁体字(はんたいじ)」です。
香港やマカオでも繁体字が使用されています。
一方、中国本土では、画数を大幅に減らした「簡体字(かんたいじ)」が使われています。
| 日本の漢字 | 繁体字 | 簡体字 |
| 発 | 發 | 发 |
| 国 | 國 | 国 |
| 会 | 會 | 会 |
| 台湾 | 台灣 | 台湾 |
| 認識 | 認識 | 认识 |
| 読書 | 讀書 | 读书 |
簡体字でも日本の字と同じものがありますが、簡略化されていると何の漢字か想像しにくいですよね。
繁体字は日本の旧字体に近いので、日本人にとっては直感的に意味を理解しやすいというメリットがあります。
台湾の街の看板やメニューも、日本語の漢字力で意味を推測できる場面が多くあります。
台湾をメインに考えている場合は、繁体字で学習を進めると学習のスタートダッシュが格段に楽になります。

大陸中心の場合は簡体字を選びましょう。
台湾では主にボポモフォ(注音符号)、中国本土ではピンイン(拼音)が発音記号として使用されています。
ボポモフォは、台湾独自の発音記号で、漢字の一部を元に作られた37個の記号で音を表します。
| 漢字 | ボポモフォ | ピンイン |
| 你好 | ㄋㄧˇ ㄏㄠˇ | nǐ hǎo |
| 謝謝 | ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˋ | xiè xie |
| 喝咖啡 | ㄏㄜ ㄎㄚ ㄈㄟ | hē kā fēi |
ボポモフォは子音と母音の記号を組み合わせて1つの音を作る仕組みで、どことなく日本語のひらがなに似ている形のものもありますね。
台湾の子どもたちはこのボポモフォで漢字の読み方を覚え、大人も日常的にスマートフォンやPCの入力で使用します。
一方、ピンインは中国大陸で公式に採用されているアルファベットを使った発音表記システムです。
欧米の学習者や、ローマ字に慣れている日本人にとって、とっつきやすいという利点があります。
繁体字でもピンインで読んだり文字入力をしたりすることはできるので、もし「まずは手軽に始めてみたい」という場合は、ピンインからスタートすることもできます。
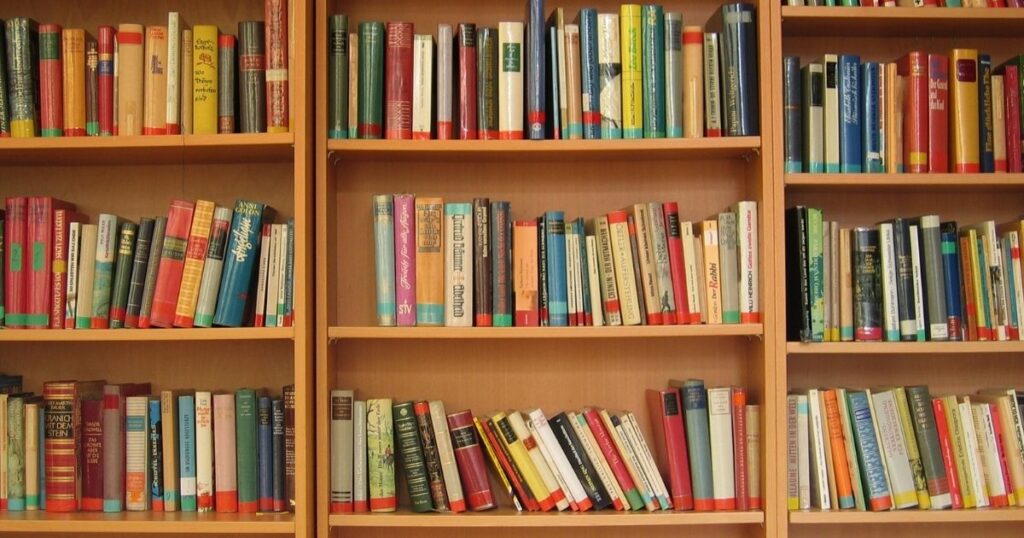
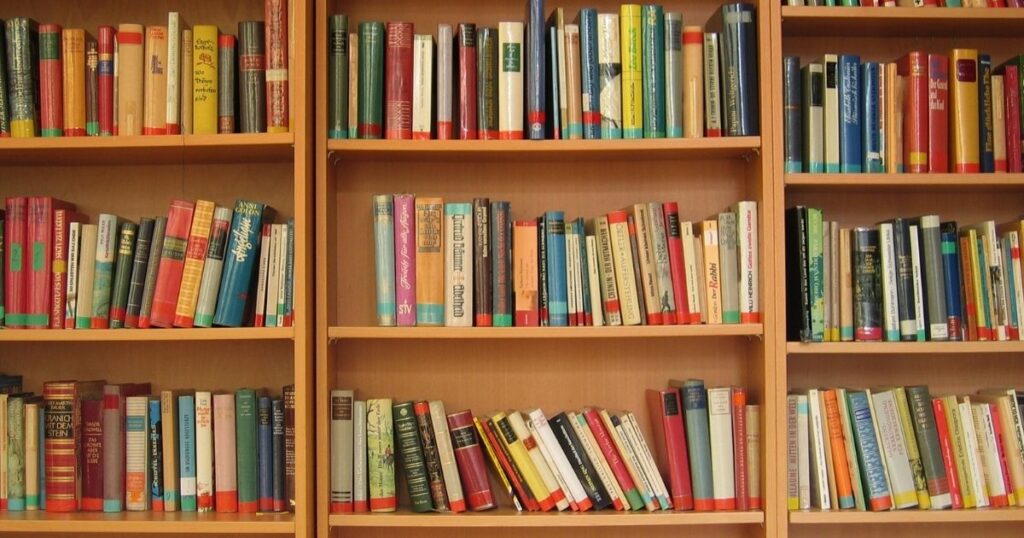
台湾華語と普通話は基本的に相互理解が可能ですが、単語や表現にいくつか違いがあります。
この章では、代表的な違いを紹介します。
台湾でタクシーに乗ろうとして「出租车!」と言っても運転手さんにキョトンとされた…なんて経験があるかもしれません。
実は、台湾華語と普通話では、日常生活で使う単語が少し違うのです。
この違いを知っておくだけで、現地でのコミュニケーションが格段にスムーズになります。
台湾華語は日本統治時代の影響や欧米文化との接触により、日本語や英語からの借用語が多く含まれています。
| 単語 | 台湾華語 | 普通话 |
| タクシー | 計程車 jì chéng chē | 出租車 chū zū chē |
| 自転車 | 腳踏車 jiǎo tà chē | 自行车 zì xíng chē |
| 弁当 | 便當 biàn dāng | 盒饭 hé fàn ※便当も使う |
また、台湾で「土豆(tú dòu)」を注文すると香ばしい「ピーナッツ」が出てきますが、中国大陸で頼むとホクホクの「じゃがいも」が出てきます。
知らずにいると、思わぬ表現の違いにびっくりしてしまいますよね。
台湾華語と普通話では、挨拶や社交場面での表現にも違いがあります。
挨拶は言語学習の基本であり、地域特有の表現を使うことで、現地の人々との親近感が生まれます。
台湾華語の挨拶表現には、台湾語(閩南語)由来の言葉が混ざることがあります。
例えば、人に軽くぶつかってしまった時や、店員さんに声をかける時。「すみません」の代わりに、台湾語由来の「歹勢(pháinn-sè、パイセーに近い発音)」がごく自然に使われます 。
これを使えたら、一気に現地に溶け込めますよ。
また、「ありがとう(謝謝)」への返事も特徴的です。
教科書では「不客气(bú kè qi)」と習いますが、台湾の日常会話では圧倒的に「不會(bú huì)」が使われます。
こちらの曲では冒頭部分の会話に「不會」が出てきますよ。
>>>周杰倫 Jay Chou【半島鐵盒 Peninsula Ironbox】Official MV





あなたのゴールはどこにありますか?
近い将来、台湾で生活や仕事をするのか、それとも中国大陸でビジネスを展開したいのか、限られた時間で最大の効果を出すには、まず自分の目的地を明確にすることが学習成功の鍵です。
目的地が台湾であるならば台湾華語(國語)、大陸ならば普通話の学習に全力を注ぎましょう。
台湾華語は台湾における共通語であり、特に台北のような都市部の教育機関やビジネスシーンでは必須の言語です。
台湾南部や伝統的な地域との深いつながりを求める場合は、台湾華語を習得した上で、台湾語(閩南語)を学ぶと良いでしょう。
大陸メインでときどき台湾に行くかもしれないのならば、普通話の方が教材も豊富だという利点があります。
発音や単語にやや違いはあっても、話す言葉は意思疎通可能なので、大きな心配はいりません。
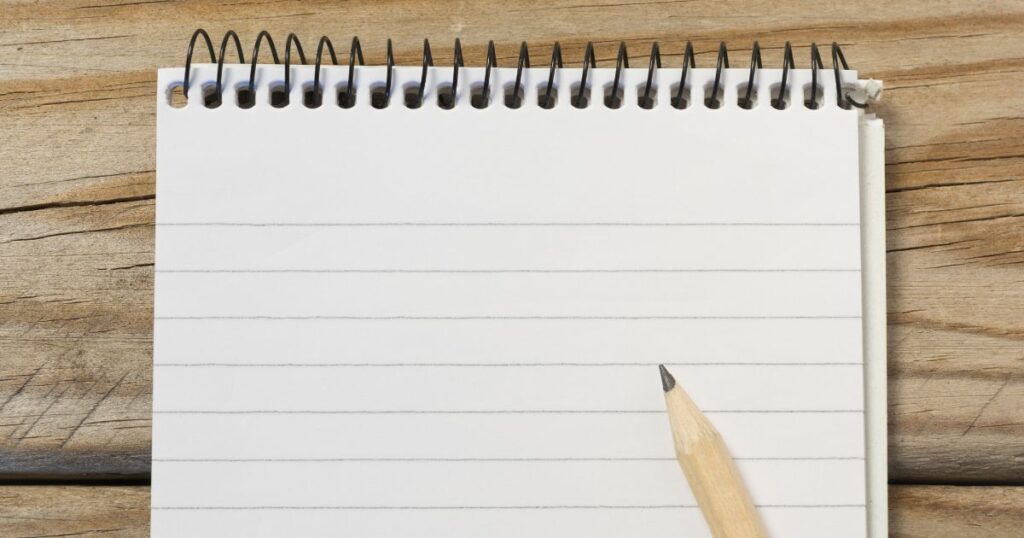
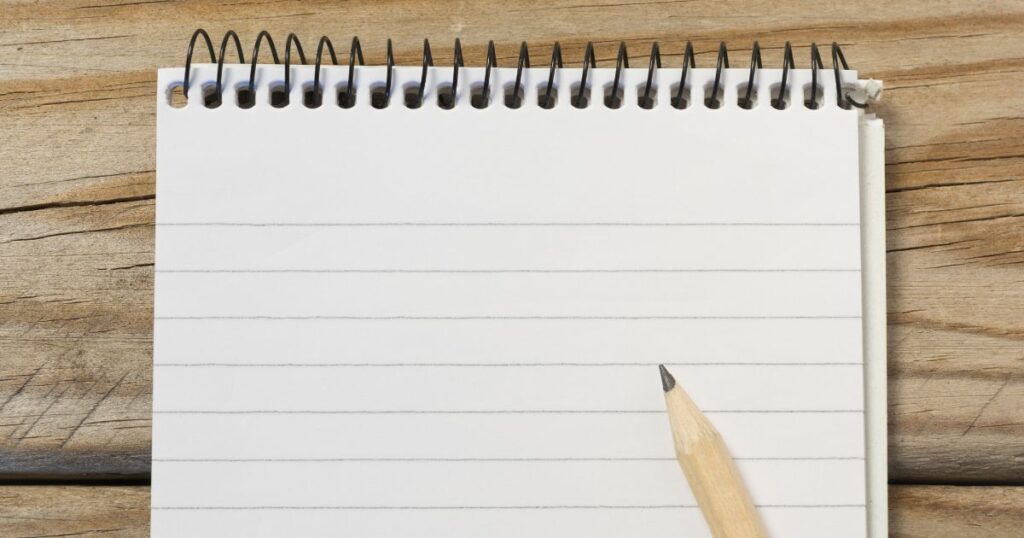
台湾華語と大陸の中国語は互いに意思疎通できますが、台湾華語は発音が柔らかく優しい雰囲気があります。
それは、大陸の中国語と比べて「そり舌音」や声調の高低差が少なく、軽声や鼻音の区別もほとんどなくなるからです。
また、台湾では繁体字とボポモフォが、大陸では簡体字とピンインが使われ、語彙や表現にもやや違いがあります。
どちらを選ぶかは、どの地域を目的とするかが重要です。
台湾旅行や文化理解が目的なら台湾華語、中国大陸でのキャリアアップを目指すなら普通話が適しています。
通じる中国語習得に向けて、今日から学習をスタートしましょう。
毎日中国語公式LINEでも話せるようになる中国語学習情報をお届けしています!
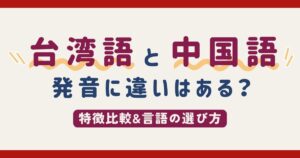
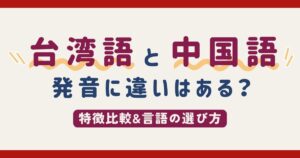
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
