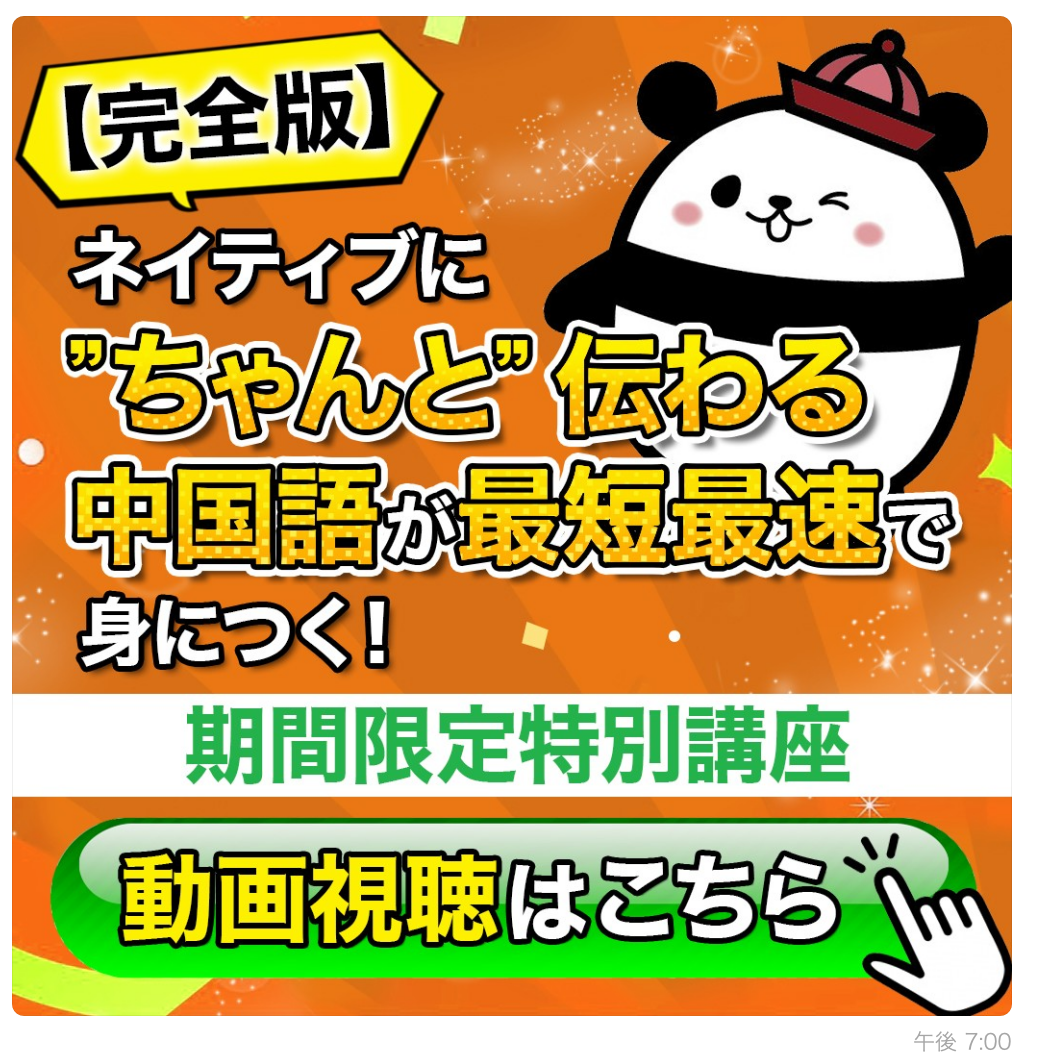
\ 期間限定動画無料配布中 /

半年でHSK6級に合格したいです!何をしたらいいですか?
HSK6級は難易度の高い試験で、5000語の単語、ニュースや専門的なインタビューを聞き取れるリスニング力、大量の文章を短時間で正確に読み取る読解力、そして読んだ文を要約する作文力が必要です。
しかし、今現在、ある程度の中国語力があり、良質な教材を活用した効率的な勉強法なら、半年合格も夢ではありません。



この記事では半年でのHSK6級合格に向けた学習戦略と成功の秘訣を余すことなくお伝えします。
半年後、HSK6級合格者としての自信に満ちた未来をつかみとりましょう!




まず、HSK上級である6級に半年で合格することは現実的に可能なのかを見ていきましょう。
HSK6級に合格するためには、中国語を母国語とする人々に近い、非常に高いレベルの中国語運用能力が求められます。
中国の新聞や雑誌に書かれている複雑な内容を理解し、専門的なトピックや文化的な背景についても深く把握できるレベルです。
現在、HSKの試験は1級から9級までありますが、もともとは6級が最上級で、今も6級は高い中国語力として広く認められています。
合格するためには5000語以上の膨大な単語力、長文を速く正確に読む力、複雑な話題や背景知識も理解できるリスニング力、そして与えられた文章について筋道を立てて要約する作文能力など、総合的な中国語能力が必要です。
日常生活で中国語を使って情報を得たり意見を交換したりすることに全く支障がないのはもちろんのこと、大学の講義を聴いたり、ビジネスの場面で高度な交渉をしたりできるレベルを目標とすると良いでしょう。
HSK6級の合格に必要な勉強時間は、もともとの語学の得意不得意、これまでの中国語学習経験、どれだけ効率よく勉強を進められるか、そして現在の中国語レベルによって大きく変わってきます。
あくまで目安ですが、既にHSK5級に合格している場合、HSK5級に必要な単語数が2500語、HSK6級では5000語なので、単純計算して5級までの2倍の時間が必要ということになります。
もし中国語の学習を始めたばかりの方であれば、何年という月日を費やすことが一般的です。
半年での合格という高い目標を掲げるなら、1日にどれくらいの勉強時間を確保できるか具体的に計画し、それを着実に実行していく強い意志と環境づくりが重要です。
また、時間だけでなく、質の高い学習方法を取り入れることも合格への近道となるでしょう。
もし半年という期間でHSK6級の合格を目指すのであれば、学習を開始する時点である程度の中国語能力を備えていることが理想的です。



HSK5級で240点以上、もしくは解いてみて「簡単だな」と余裕を感じるレベルであれば、HSK6級半年での合格も可能性が高くなります。
HSK5級レベルの知識がしっかりと身についていない状態でHSK6級の対策を始めてしまうと、学習内容をなかなか理解できず、効率も悪くなってしまいます。
HSK5級で学ぶ内容は、HSK6級の学習を進める上での土台となる部分です。



まずは過去問題などで現在の実力を知るところから始めましょう。
5級真题:5级 – 中文考试服务网
6級真题:6级 – 中文考试服务网
※上記リンク先の「资源」の中に実際の問題があり、リスニングも聞けます。


この章では、HSK6級に半年という短い期間で合格するための効率的な学習計画と、各期間で重点的に取り組むべき内容を分かりやすく紹介します。
大きく分けて次の3つのステップで進めていきます。
HSK5級が高得点で余裕の人以外は、HSK6級の勉強を始める前に土台を固めます。
5級までの内容が身についていない場合、直接6級の勉強を始めてしまうと分からないことだらけで勉強の効率が非常に悪くなります。
先にHSK5級の2500単語と5級までに登場した文法知識等をしっかりおさえておくことで、後の6級のリスニング、読解、作文といった応用的な学習がスムーズになります。
すでに持っている教材で十分ですので、丁寧に読み進め、各項目に対応する練習問題を解いて理解を深めておきましょう。
この1ヶ月の地道な努力が、半年後の合格を大きく左右するため、着実に知識を積み重ねていくことが肝心です。



焦らずじっくり進めましょう。
基礎固めを経た続く3ヶ月間は、HSK6級の主要な試験分野である「リスニング(听力)」「読解(阅读)」「作文(书写)」のそれぞれに特化した演習を集中的に行い、実践的な解答能力と各分野特有のスキルを徹底的に鍛え上げる重要な期間です。
HSK6級の各パートは、それぞれ異なる能力が試され、出題形式や時間配分も独特です。
実際の試験で得点に結びつけるためには、分野別の対策が欠かせません。



この期間は得意分野を伸ばしつつ、苦手分野を克服する学習を進めましょう。
分野別の学習方法は後述します。
HSK6級合格に向けた学習ロードマップの最終段階である最後の2ヶ月は、実際のHSK6級の過去問題を中心とした実践練習と総仕上げです。
過去問で試験の出題傾向、問題の難易度、時間配分、そして問題形式を把握し、確実に得点できる力を養っていきます。
最低でも過去5回分、できれば10回分程度の過去問題を用意し、リスニング約35分、読解50分、作文45分という本番と同じ時間制限を設けて、通しで解く練習をしましょう。



ここで注意することは、練習段階での点数に一喜一憂しないことです。
間違えた問題や、時間内に解けなかった問題を理解することはもちろんのこと、たとえ正答していても、なんとなく勘で当たったところをきちんと確認し、1つずつクリアしていくことが大切です。
また、試験日が近づいてきたら、本番と同じ時間に起床するなど生活リズムを整え、万全の体調で自信を持って臨めるように準備しましょう。
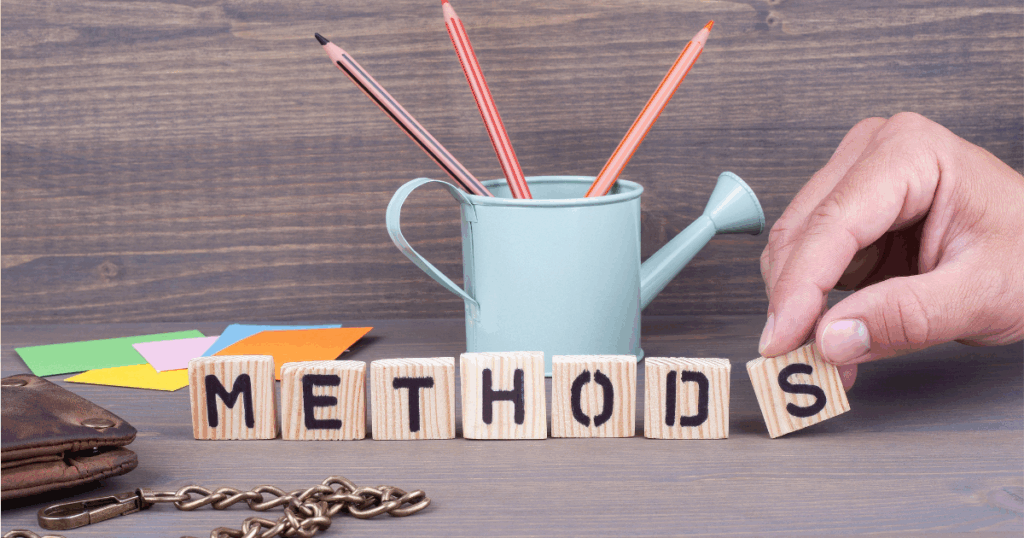
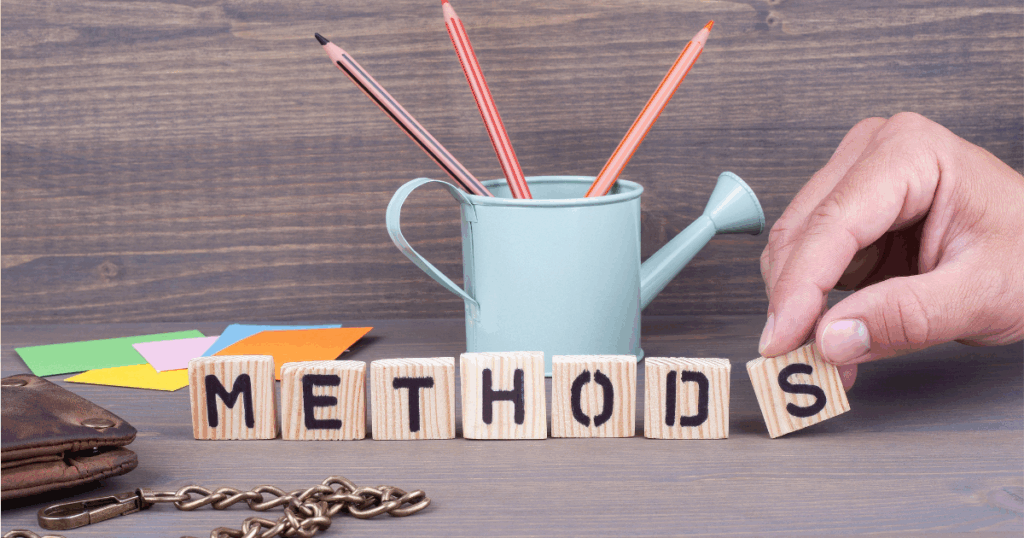
この章では、HSK6級の合格に必要な各分野の短期攻略法を紹介します。



HSK6級は中国語の試験の中でも難易度が高く、多くの学習者にとって大きな壁となっています。
しかし、ポイントを押さえて効率的に勉強を進めれば、半年といった期間でも合格レベルの能力を習得することは不可能ではありません。
HSK6級のリスニング試験は、長い中国語の音声が1度しか放送されません。
このリスニング能力を鍛える方法として「シャドーイング」という勉強法があります。
シャドーイングとは、聞こえてくる中国語の音声のすぐ後を追いかけるようにして、発音やイントネーション、リズムをそっくりそのまま真似て発声する練習法です。
中国語特有の音声に耳が慣れ、言葉を聞き取る力が自然と向上する効果があります。
また、内容を理解しながら追いかけることで、長文を聞き続けるための集中力を養う訓練にもなります。
HSK6級の過去問や対策本のリスニング音源と原稿を用意し、最初は文字を見ながら、アナウンサーの発音や話し方を真似ることから始めてみましょう。
慣れてきたら、文字を見ずに音声だけを頼りに挑戦します。



毎日15分から30分程度でも良いので、継続することが上達への重要なポイントです。
HSK6級の読解セクションは、非常に多くの中国語の文章を限られた時間内に読まなければなりません。
HSK6級の読解問題は4つの形式で構成されています。
文法的な誤りを見つける問題は一見するとどれも正しく見えてしまいますが、よく出題される誤りのパターンがあります。
語順の間違い、不要な単語の重複、接続詞や介詞が正しくないなど、問題集を通してチェックしておきましょう。
長い文章を読む問題では、まず設問に目を通し、何が問われているのかを把握してから本文を読むのが有効です。
全ての文章を一字一句完璧に理解しようとするのではなく、答えの根拠となる部分やキーワードを素早く見つけ出す練習を重ねましょう。
HSK6級の作文試験は、他の級とは異なり、約1000字の中国語の文章をわずか10分間で読み、その後35分という限られた時間でその内容を400字程度の文章に要約するという形式です。
毎回使える「要約のテンプレート」を用意し、それに従って練習すると書きやすいです。
テンプレート例
この「導入・展開・結論」という型を常に意識しながら、HSK6級の過去問や模範解答、練習問題の文章を使って、実際に要約文を書く練習を繰り返し行いましょう。
最初は時間を気にせず、丁寧に型に当てはめていく練習から始め、徐々に慣れてきたら本番同様の制限時間を設けて取り組むのが効果的です。
◎HSK6級の作文についてはHSK6級の作文の書き方のコツは?の記事でも詳しく解説しています。
HSK6級に必要な単語数は5000語以上ですが、すでにHSK5級レベルを習得済みであれば、残る単語は2500語です。
前提として、試験は満点を取る必要はない上に作文以外は選択問題なので、全ての単語を完璧に覚えなくても、前後の文脈から判断するなどして設問には答えられることがあります。
単語は多く知っているに越したことはないですが、単語暗記だけに時間を取られてしまってはHSK6級合格が遠のいてしまいます。
単語は通勤・通学の車内などスキマ時間を有効活用し、他の分野の勉強に十分な時間をかけられるようにしましょう。
その上で単語を覚える際、「1日10個、10日で100個」のような覚え方は、10日目には1日目の単語の多くを忘れてしまいます。
仮に同じ「10日で100個」なら、サラッとでいいので「1日に100個」を10日繰り返した方が覚えられる単語は多くなります。
HSK6級半年合格という目標がある場合、半年は約25週間あります。
この25週間で2500語を覚えるには、1週間で100語の計算です。
1日目100個見る→2日目同じ100個を見る→3日目同じ100個を見る…と続けていきます。
1つの単語と例文を見る時間を15秒程度にすれば、100個あっても25分程度で終わります。
上記の覚え方は一例ですが、忘却曲線に基づいて、「忘れる前に繰り返し復習する」ことが何よりも大切です。
また、単語学習は単語の意味だけを覚えるのではなく、例文や文章を通して使われている場面をイメージしながら覚えると記憶に残りやすくなります。



音声を聞きながら五感をフル活用しましょう。


この章ではHSK6級対策におすすめ教材を紹介します。
HSK6級という中国語学習における高いハードルを、特に半年といった限られた期間で効率的にクリアするためには、質の高い教材を選び、それを最大限に活かす工夫が不可欠です。
HSK6級合格に必須なのは公式過去問題集です。
2025年現在、最新版は「2021年版」で、5回分の過去問が収録されています。
公式過去問集の最大の特徴は、単なる過去問題と解答の掲載ではなく、詳しい解説があることです。
全ての中国語に日本語訳が付いており、HSK6級受験者の多くが苦戦する「間違っている文を選ぶ」問題には訂正例が、「要約」の問題にも解答例がついています。
公式過去問題集を購入したら、まず冒頭にある「試験概要」を熟読し、試験全体の問題構成と流れを把握しましょう。
各パートごとにまとめられている重要ポイントを読み、はじめは時間を気にせず一問一問じっくり取り組みます。



問題を解いた後は必ず解説を確認し、理解を深めましょう。
リスニングはスマホに音声をダウンロードできます。
そして、本番前には制限時間どおりに通して実施し、時間配分に慣れていきます。
このように過去問を「解いて終わり」にするのではなく、各パートの対策教材として深く掘り下げ、知識を蓄積していくことがHSK6級短期合格への道筋となります。
参考:教材について | HSK 日本で一番受けられている中国語検定
HSK6級の単語は5000語以上ですが、HSK5級が2500語のため、新たに覚えるのは残りの2500語です。
単語帳のおすすめは以下の2つです。
HSK6級はリスニングの比重も大きく、単語を正しい音で理解していなければ聞き取ることが困難です。
また、文字情報だけでなく、耳からの音声情報も合わせてインプットすることで、単語の記憶定着率が向上しやすくなります。
単語は目で見るだけでなく、耳で聞き、口で発音するという五感を活用した学習で効率的に覚えましょう。
公式過去問集で練習が足りない場合や、特定の分野の弱点補強をしたい場合は、次の教材がおすすめです。
上述の単語で紹介した『合格奪取!』シリーズです。
このシリーズは5級以下や中検の対策本もあり、わかりやすい解説と豊富な問題演習に定評があります。



HSK6級向けで日本語の解説がある教材は数が少ないのが現状です。
6級受験となればある程度の中国語が読めるはずなので、中国語の解説の教本を使うという方法もあります。
また、公式過去問集は中古で以前のものも手に入りますので、最新版だけでなく旧版もあわせて使うのも戦略の1つです。


この章では、難しいHSK6級に短期合格を目指す際に陥りがちな「落とし穴」と、それを乗り越えて最後まで走り抜くための具体的な「挫折しないコツ」を紹介します。
HSK6級の短期合格を目指す場合、まず完璧主義を捨てましょう。
試験範囲の全ての単語を完璧に覚え、全ての文法を完全に理解し、どんな難解な長文もすらすら読めて聞けて書ける状態を目指すのは、限られた時間の中では現実的ではありません。
むしろ、そのような完璧さを追求しすぎることが、途中で「もう無理だ」と挫折してしまう大きな原因になりかねないのです。
短期合格を本気で目指すのであれば、全てを網羅しようとするのではなく、いかに効率よく「合格点」を取るかに集中する方が得策です。
HSK6級は合格不合格の記載はありませんが、一般的に180点(300点満点中)で合格と言われています。
出題頻度の高い重要単語や文法項目に的を絞って学習したり、得意な分野で確実に得点し、苦手な分野は最低限の失点に抑えるといった割り切りも時には必要です。
学習範囲に優先順位をつけ、「合格点を取るために必要なこと」に集中する。この思考の転換が、短期合格と挫折回避の最初の大きな一歩となるでしょう。
HSK6級合格という高い目標に向かって、半年間という決して短くはない期間、集中的に学習を続けるためには、何よりも「モチベーションの維持」が鍵となります。
特にHSK6級レベルの学習は、覚えるべき単語の多さや文章の複雑さから、単調で孤独な努力を強いられる場面も少なくありません。
思うように成果が上がらない時期や、勉強に疲れてしまった時など、どうしてもやる気が低下してしまうことは誰にでもあります。
大切なのは、そのような時にどうやって自分を奮い立たせ、学習を継続できるかです。
そのためには、学習を「やらなければならない苦しいもの」として捉えるのではなく、生活の一部として自然に、そして前向きに取り組めるような「学習習慣」を確立することが重要です。
例えば、毎日決まった時間に学習を開始するルーティンを作る、週ごとや日ごとの小さな目標を設定して達成感を積み重ねる、SNSの学習アカウントやオンラインコミュニティで同じ目標を持つ仲間と交流し励まし合う、といった方法が考えられます。
また、合格した後の自分の姿(中国語を活かして仕事で活躍している、中国の大学で学んでいるなど)を具体的にイメージすることも、学習意欲を高めるのに役立ちます。



学習記録をつけて自分の頑張りを可視化したり、定期的にささやかなご褒美を設定したりするのも良いでしょう。
自分に合ったモチベーション維持法を見つけ出し、それを学習習慣に組み込むことで、困難な道のりも楽しみながら乗り越えやすくなります。
HSK6級のような高度なレベルの試験勉強を進めていると、一生懸命努力しているにもかかわらず、なかなか成績が上がらなかったり、以前は解けていた問題が解けなくなったりする「伸び悩み」の時期、いわゆるスランプに陥ることがあります。



これは多くの学習者が経験することで、決してあなただけではありません。
大切なのは、そんな時に「もうダメだ」と諦めてしまうのではなく、なぜ伸び悩んでいるのか原因を冷静に分析し、具体的な対策を講じることです。
同じ学習方法をただ闇雲に続けていても、効果が頭打ちになってしまうことはよくあります。
例えば、書籍の単語帳をアプリに変えてみる、過去問だけでなく弱点補強教材を使う、ドラマやニュースなど生きた中国語に触れる機会を増やす、作文なら一度プロの先生に添削を依頼してみるなど、学習方法やアプローチに変化を加えてみましょう。
時には、数日間思い切って勉強から離れて気分転換をし、心身をリフレッシュさせることも必要かもしれません。
伸び悩みは、学習が次のステップに進むための準備期間と捉え、焦らず、自分に合った対処法を試行錯誤しながら見つけていくことが重要です。
この壁を乗り越えることで、合格がぐっと近づいてくるはずです。


HSK6級に半年で合格するための道のりは平坦ではありませんが、現在のレベルと効率的な勉強法、継続的な努力があれば達成は不可能ではありません。
まずはHSK5~6級の過去問で実力を知るところから始めましょう。
HSK5級で高得点が取れるならば半年で6級合格の可能性も高まります。
HSK6級の試験対策は公式過去問集の徹底活用が有効的です。
全てを完璧に仕上げるのではなく、300点満点で180点以上取ることに集中して学習を進めましょう。
毎日中国語では本気で中国語を身につけたい人のサポートをしています。



中国語学習情報を配信している公式LINEもあわせてご覧くださいね。
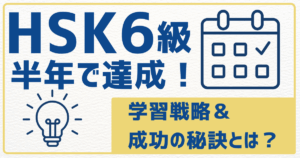
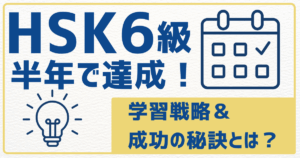
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
