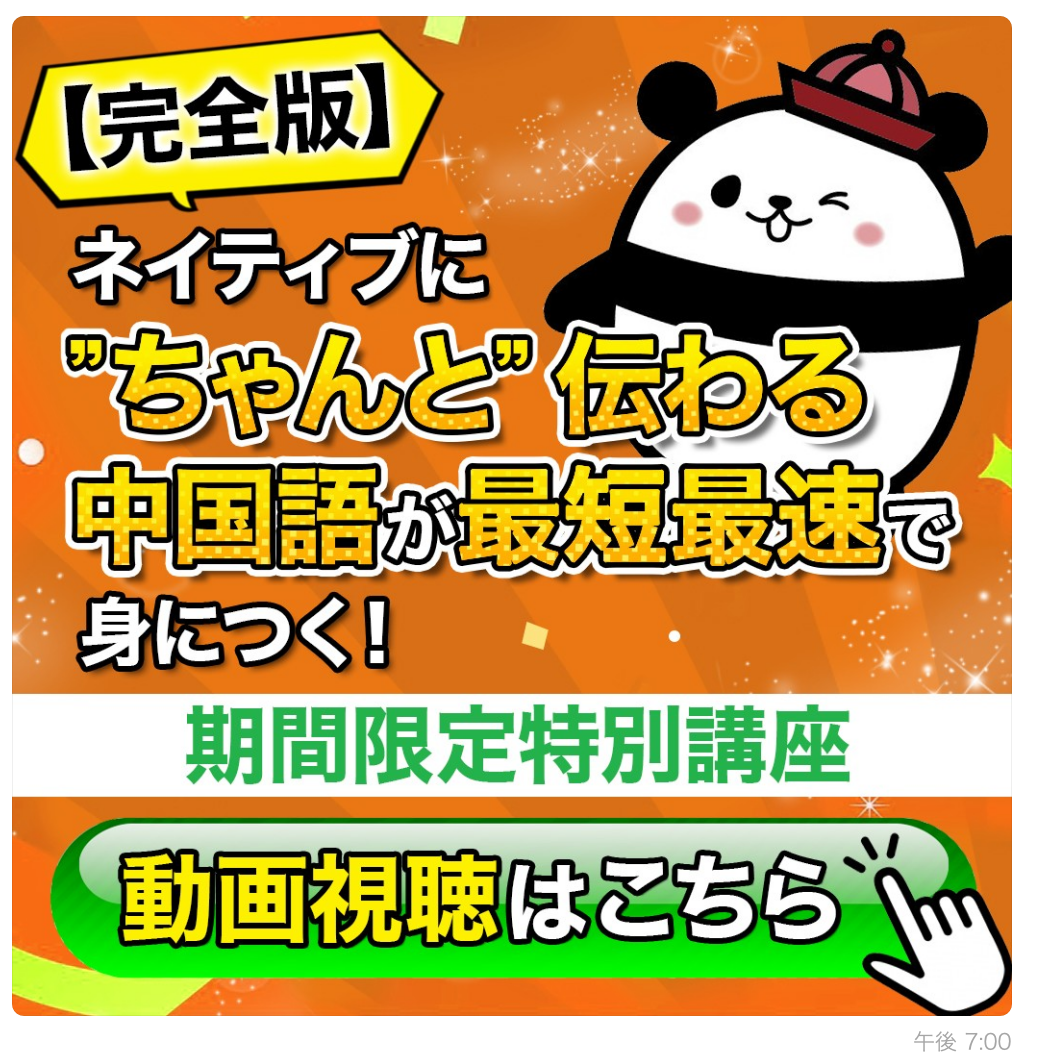
\ 期間限定動画無料配布中 /

英語と中国語はどっちがいいですか?
キャリアアップや将来性を見据えると悩ましい問題ですよね。
英語と中国語はそれぞれ異なる強みがあります。
この記事では求人需要や市場規模、学習の難易度から英語と中国語を比較します。



あなたへの最適な答えを見つけ、未来を切り開いていきましょう!


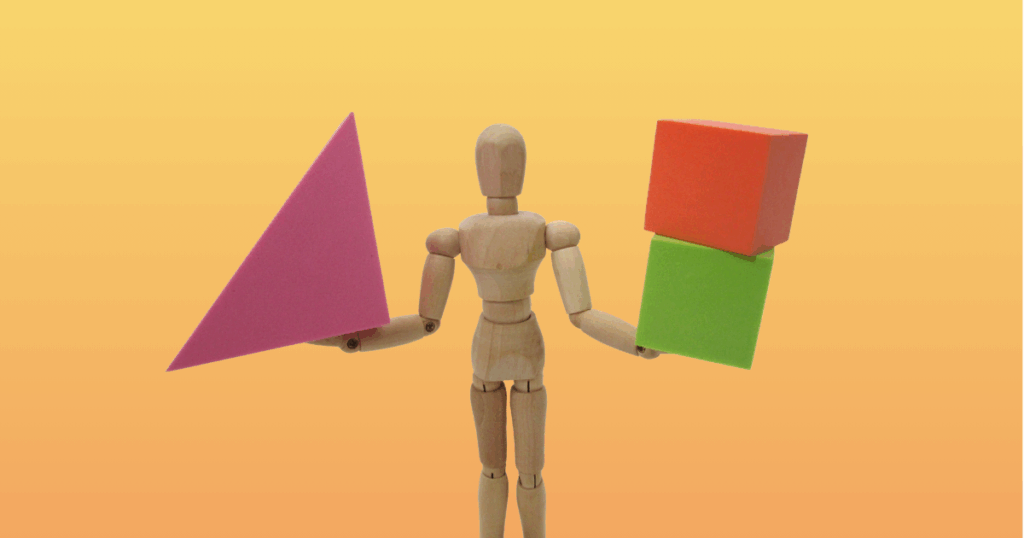
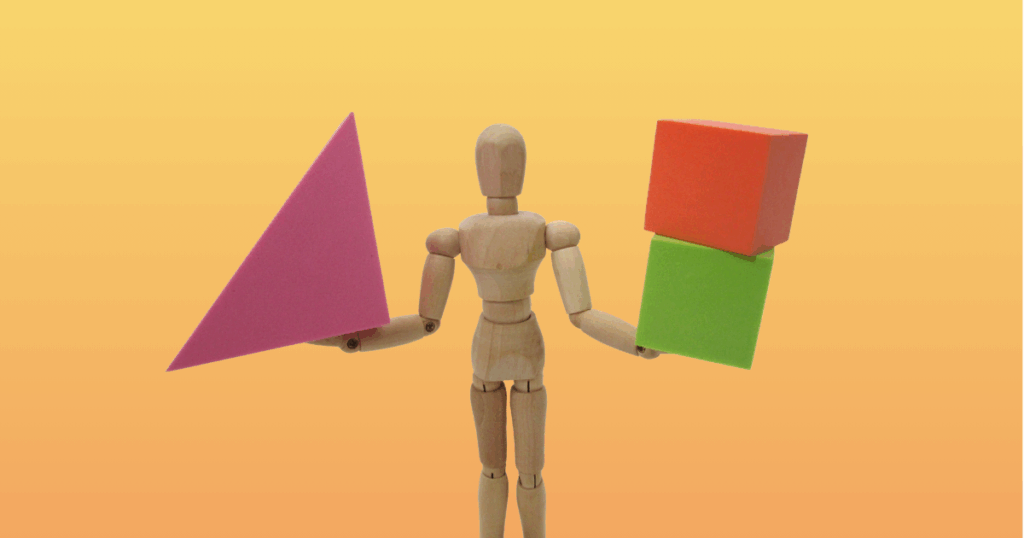
まず、英語と中国語のどちらが将来的により価値の高い投資となるかを、客観的なデータに基づいて4点解説します。
英語は母語以外の話者も含めると世界各国約15億人の人が話すグローバル言語です。
アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、シンガポール、インドなど多様な経済圏で母語もしくは公用語・準公用語として使用されています。
教育としても重視されており、日本を含めて英語を話す人は世界中にいます。
一方で、中国語の話者は約11.8億人で、そのうち8〜9割ほどが中国本土に集中しています。
中国は世界第2位の経済大国であり、特に越境EC市場(インターネットを用いた外国向けの電子商取引)では、中国だけで全世界の50%超のシェアを占めています。
この規模の単一市場の影響力は無視できません。
参考:What is the most spoken language? | Ethnologue Free
参考:eMarketer
2025年7月現在、Daijob.comでは英語の求人が約7700件、中国語(標準語)の求人が約670件です。
英語を使う求人数は中国語の10倍以上です。
年収面では、英語をビジネスレベルで使える50代男性は平均と比べて263万円高く、女性では303万円高いという結果が出ています。
出典:AI時代の「英語力」、年収との関係を Daijob.com が独自調査
実際に、英語力を求める求人では高年収の傾向が顕著で、たとえば外資系の営業職で年収500万円以上、ITエンジニアで700万円以上、金融・コンサル職では800万円以上と、業種を問わず“英語ができること”が収入アップにつながっているのが現状です。
中国語は求人総数こそ少ないものの、経験やスキルによっては、ゲームローカライズで年収600万~1000万円、越境ECマーケティングで700万~1200万円といった高収入の専門職案件があります。
年齢に関わらず、英語や中国語のスキルは「年収プレミアム」を生み出す武器になっていると言えるでしょう。
AI翻訳の進化により、定型的な文書処理や基本的な意思疎通はAIに代替されつつあります。
一方、商談・交渉・文化的ニュアンスを伴う高度なコミュニケーションは人間にしかできない領域であり、その価値はむしろ高まっています。
中国語は方言や文化的背景が複雑なため、WeChatやWeibo、小红书など独自のSNS文化への理解も必要です。
そのため、ビジネスの現場では依然として人間ならではのスキルが重要視されています。
英語においても、グローバルチームを率いるリーダーシップや多国籍会議を仕切るファシリテーション能力が重視されつつあります。
今後5年では、TOEIC600点レベルの英語力の価値は低下し、一方でTOEIC850点以上の高度なコミュニケーション能力が新たな差別化要因となる見通しです。
日本向け越境ECにおける中国人消費者の購入額は2兆4301億円(前年比+7.7%)と、アメリカの1兆4798億円を大きく上回っています。
参考:令和5年度 電子商取引に関する市場調査 – 経済産業省
インバウンド観光においても、中国人観光客の消費単価は最高水準であり、中国語対応が直接売上につながることが実証されています。
一方で英語は、東南アジアや欧米など様々な人への対応ができ、安定した顧客層の確保に役立ちます。
即効的に売上を伸ばしたいEC・観光事業者には中国語を優先するのが有効で、長期的な事業基盤の強化には英語が適していると言えるでしょう。


続いて、日本人にとって英語と中国語のどちらが習得しやすいかを、以下の点から具体的に解説します。
日本人にとって、英語は中学・高校で合計6年以上学ぶ科目です。
「あまり話せない」と感じていてもなんらかの基礎知識はあり、簡単な単語(apple, go, school など)や日常表現(How are you? I’m fine. Thank you.)は、意識せずとも理解できる人が大半です。
一方、中国語はほとんどの人にとってゼロからのスタートになります。
漢字を使うとはいえ、発音や文法、語順などは日本語とも英語とも異なるため、最初は戸惑う人も少なくありません。
特に「声調(四声)」や「ピンイン」といった発音のルールは、英語以上にハードルに感じることもあります。
英語に多少の苦手意識があっても、過去に習った内容が再学習の助けになるため、ゼロから始める中国語よりもスタート地点が有利なことは事実です。
ただし、裏を返せば、中国語はほぼ誰もが「横一線でのスタート」になるため、やる気次第で周囲と差をつけやすい言語とも言えます。
将来的に「中国語ができる人材」として重宝される可能性も高く、英語と比べてライバルが少ない点は大きなメリットです。
皆さんご存知のとおり、英語はabc…のアルファベット、中国語は漢字で単語や文が構成されています。
英語のアルファベットは26字しかないものの(大文字と小文字なら52字)、computerや buildingのように、単語ごとにスペルを覚えなければなりません。
一方、中国語は漢字数が膨大で、中国では小学校卒業までに約3000字習います(日本は1026字)。
数こそ多いものの共通している漢字や見た目が似ている漢字も多く、例えば「日本」は中国語でも「日本」と書き、「中国」も同じく「中国」と書きます。
また、中国本土では「车(車)」「电话(電話)」のような簡略化された「簡体字」を使用していますが、漢字に慣れている日本人にとっめは他の国の人と比べると大きなアドバンテージがあります。
注意すべき点は、「ピンイン」と呼ばれる発音表記を新たに覚える必要があることです。
「谢谢(ありがとう)」は「xiè xie」と表記します。
このピンイン習得には多くの人が時間を要しています。
英語と中国語は、どちらも日本語にない発音が含まれていますが、カタコトの発音ではほとんど通じないのが中国語です。
英語は「think」と「sink」、「right」と「light」のようなR音、L音、TH音の発音の区別に苦労することが多いですよね。
中国語は声調言語で四声と呼ばれる4種類の声調があり、同じ「ma」という音でも声調によって「母」、「麻」、「馬」、「罵る」とまったく違う意味になります。



さらに母音と子音も日本語より複雑で、日本人には同じように聞こえてしまう発音が多数あります。
漢字の親しみやすさから中国語は習得しやすいように感じることもありますが、通じる発音を習得するには英語以上に練習が必要です。
日本人にとって中国語の発音は英語より難しいですが、文法は比較的シンプルです。
中国語の文法の大きな特徴は、英語のような時制や人称による動詞の変化が存在しないことです。
英語では「eat – ate – eaten」(食べる)と覚えるところ、中国語は主語が誰でも時制がいつでも「吃」で、動詞そのものが変化しません。
また、中国語には「一杯水(1杯の水)」のような日本語に似た助数詞の概念もあり、日本人には理解しやすい面があります。
英語は中学・高校の6年間英語を学んだ人が多く、さらに大学でも英語を勉強したとするとおよそ10年です。
それでもビジネスレベルには足りず、さらに努力を必要としている人も多いことでしょう。
英語を学習している人は多いため、初級〜中級レベルでは市場価値が低く、高いレベルが前提条件となることが少なくありません。
今後必要な学習時間は、現在のレベルと1日にできる学習時間によって大きく異なりますが、苦手意識が強い場合、現実問題として学習を続けること自体が苦痛なこともあります。
一方、中国語は多くの人がゼロからのスタートです。
早い人で、半年で中級レベルのHSK4級、1年半程度でさらに上の5級に合格しているツワモノもいます。
中国語は英語に比べて学習者が少ないため、就職・転職の際に、他の求職者との差別化が図りやすいというメリットもあります。
しかし、語学習得は個人差が非常に大きく、特に仕事をしながらだと勉強にさける時間がどうしても限られてしまいます。
中国語のビジネスレベルには少なくとも数年はかかると考えておいた方が良いでしょう。


この章では、あなたの目標に応じてどちらの言語を選ぶべきか、その判断基準を解説します。ポイントは3つです。
転職や就職を目指す場合は、あなたが志望する業界と現在の語学レベルを考慮して言語を選びましょう。
英語は外資系企業やIT・金融・コンサルといった業界で幅広く評価されますが、その世界ではTOEIC800点以上も少なくなく、競争が激烈です。
一方で中国語は、ゲーム・エンタメ、越境EC、製造・貿易といった業界で希少価値が高く、HSK4〜5級程度のスキルでも評価されることがあります。
競合状況を踏まえると、英語は新卒就活生の約3割が「ビジネスレベルで使える」と回答している一方で、中国語ができる学生は全体の1%未満にとどまります。
そのため、中国語ができる人材は極めて希少であり、差別化の大きな武器となります。
趣味や教養として言語を学ぶ場合は、実用性よりも「楽しく続けられるか」を重視しましょう。
その言語や文化に興味があり、学習を続けられることが何より大切です。
英語の文化ならハリウッド映画や洋楽、英語圏の小説、BBCやCNNのニュースなどが楽しめますし、中国語の文化なら中国のドラマや映画、C-POP、中国古典文学、中華料理といったものに触れられます。
Netflixの海外作品、YouTubeの動画、現地のSNSなどを活用しましょう。
交流の機会も、英語なら英会話カフェや国際交流イベント、中国語なら在日中国人コミュニティへの参加や中華料理店で中国語で注文するなど、さまざまな選択肢があります。
ビジネスで言語を活用する場合は、ターゲット市場の規模や成長性、自社事業との相性に基づいて判断する必要があります。
重要なのは投資対効果(ROI)で、狙う市場の購買力・成長率・競合状況によって、英語と中国語のどちらに価値があるかが変わってきます。
例えば越境ECの中国市場は世界の50%以上を占め、中国語対応のライブコマースで売上が3倍になった事例もあります。
中国語に対応すれば客単価、リピート率ともに向上するといった即効性が期待できます。
英語圏の市場を見ると、アメリカ単独の大規模市場に加え、東南アジアやインドなど英語が通用する新興マーケットも控えています。
英語を使うことで多国籍に展開し、リスク分散を図る効果が見込めます。
まず売上の半分を占める中国市場に対して中国語を活用し、その上で英語を導入し市場を多様化させる戦略が、短期的な売上アップと長期的な事業安定化の両方を実現できるでしょう。
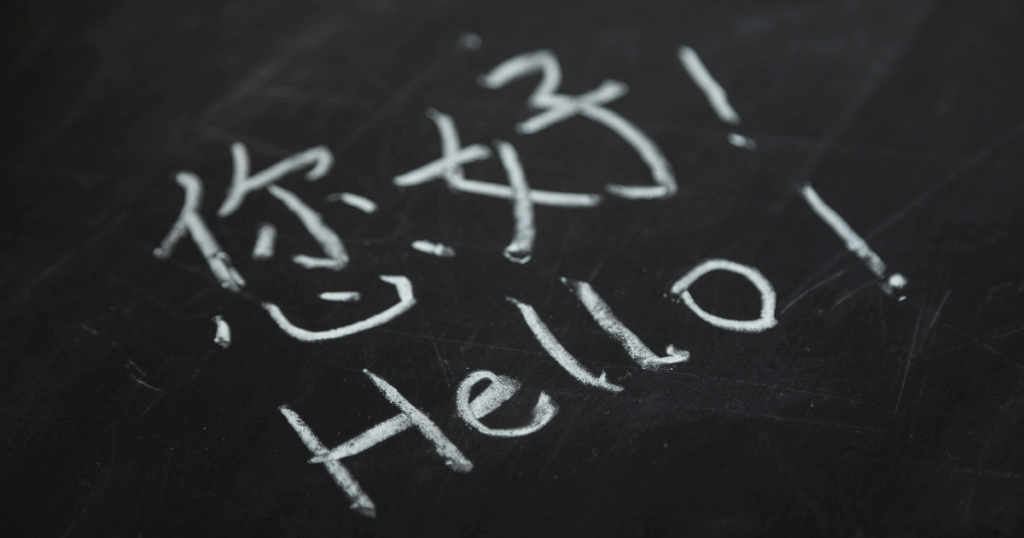
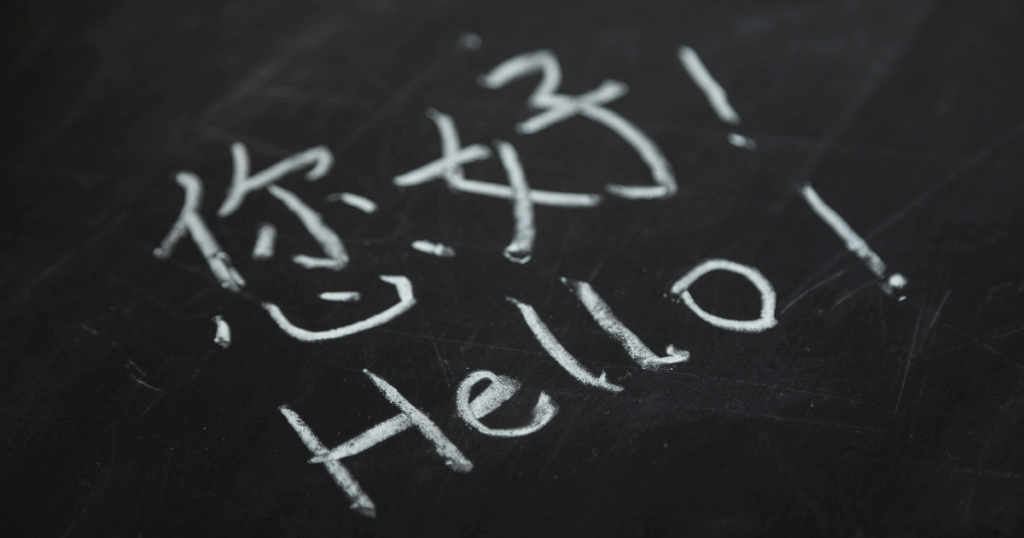
英語と中国語を同時に学習することは、確かに高いリターンが期待できます。
両方の言語を習得できれば、市場価値が飛躍的に向上し、英語の持つ安定した強みと中国語の持つ希少な強みを同時に手に入れられます。
年収1000万円超えも視野に入り、世界中の顧客に対応できるようになるでしょう。
しかし同時学習には、それ相応のデメリットもあります。
学習時間は単純計算で2倍必要になります。
また、英語と中国語とでは発音や文法の体系が異なるため、頭の中が混乱しやすく、挫折率も跳ね上がります。
英語の文法と中国語の語順を混同してしまったり、発音練習で二言語がごっちゃになるといった弊害が典型的です。
とはいえ、もし同時習得に成功し高い専門スキルがあれば、外資系の中国企業から年収1500万円規模のオファーを得ることも夢ではありません。
十分な学習時間を確保でき、かつ強い学習意欲がある場合は挑戦する価値があります。


英語と中国語のどちらを選ぶべきかは、あなたの現状や目標、使える時間によって変わってきます。
一概に「こちらが正解」というものはなく、英語と中国語それぞれに異なる強みがあります。
英語は世界各国多様な国で通用する一方、学習者が多いため高いレベルが前提となります。
中国語は日本人の学習者がまだまだ少なく、就活で他の学生に差をつけることが可能です。
いずれにしても、一度「この言語をやる」と決めたら、その後は継続的に学習を続けることが最も重要である点は忘れないでください。



未来への第一歩を毎日中国語で始めませんか?詳細は公式LINEまで!
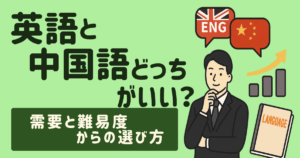
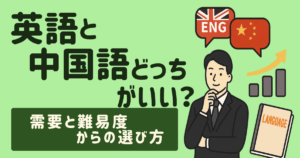
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
