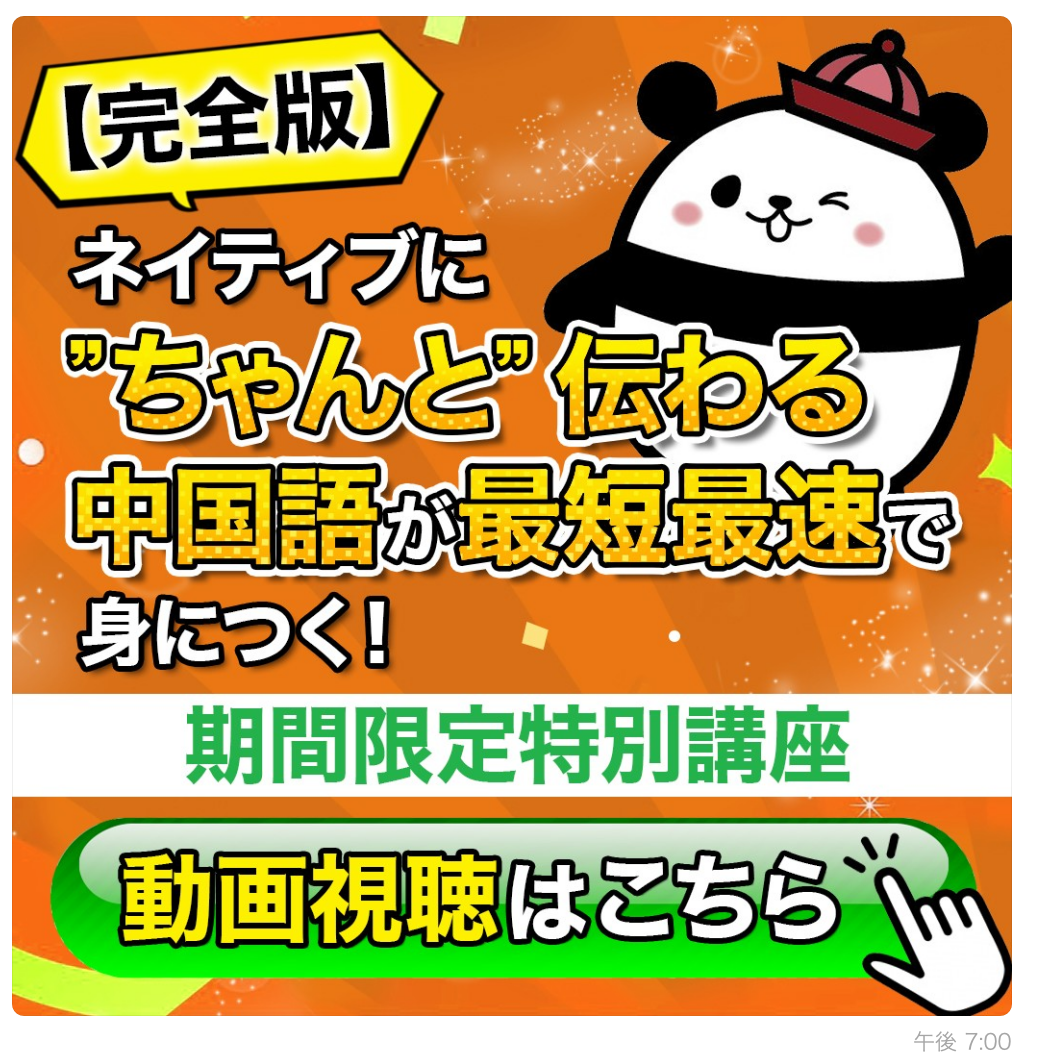
\ 期間限定動画無料配布中 /

中国語検定のために学校を探したい!でも本当に合格できるのかしら?費用も心配…。
中検は準4級から1級まで出題内容が決められています。
独学では教材選びから日々の学習まで自分1人でやらなければならないところ、中検対策のある学校なら、出題傾向や問題形式に沿った学習が可能です。
学校にはさまざまなタイプがあり、今の自分のレベル、通学の利便性、学校の雰囲気、先生との相性、予算などを総合的に考慮して選ぶことが大切です。



この記事では、それぞれの学校の特徴、学校に通う利点と注意点、学校選びのポイント、中検合格への対策方法を紹介します。
あなたに合った学習方法で合格を目指しましょう!




中国語検定の対策ができる学校は数多くありますが、ここでは代表的な5つの学習スタイルを取り上げ、それぞれの特徴を比較します。
◎中検について詳しくは【中検準4級~2級】試験時間と日程|問題構成&時間配分テクも紹介の記事で紹介しています。
専門学校は「専門士」という公的な学歴を得られるため、これから進学する場合は1つの選択肢になります。
(※「専門士」とは一定の要件を満たす2年以上の専門学校を卒業した人に与えられる称号で、就職の際には短大卒と同等にみなされることが多い。)
中国語をメインとする学科や、英語とともに学ぶ学科、観光業などと一緒に中国語を学ぶ学科があります。
いずれもその先の就職を見据えたカリキュラムになっており、同じ目標を持つクラスメイトと切磋琢磨しながら実践的な中国語を集中的に学べることが多いです。
ただし、中国語を学べる専門学校は数が限られています。
大学で中国語を学ぶ最大の魅力は、言葉だけでなく、その背景にある文化や社会まで深く探求できる点にあります。
外国語学部や国際関係学部などで、中国の歴史、文化、経済、社会情勢といった専門分野の知識を深めながら、中国語を学習できます。
卒業すれば「学士(大卒)」の学位が得られるのはもちろん、キャンパス内で留学生と交流したり、大学の図書館で専門的な資料を調べたりと、大学ならではの恵まれた環境を最大限に活用できるのも大きなメリットです。
一方、大学の授業は学術的な探求が中心となるため、必ずしも中国語検定試験の対策に直結するとは限りません。
中検合格が第一の目標であるならば、大学での学習と並行して、自分での対策が必要になることもあります。
仕事や学校帰りに通えて、対面でしっかり学べるのは、駅近などアクセスしやすい場所にある通学型の民間語学スクールです。
平日夜間や土日のクラス、少人数制のグループレッスンやマンツーマンレッスンなど、多様なコースがあります。
中国語検定合格を目指す場合は、検定対策コースがあるスクールが適しています。
例えば、B-Chineseには検定対策コースが設けられています。
多くのスクールが無料体験レッスンを実施しているので、まずは雰囲気を味わってみるのがおすすめです。
通学の時間をかけずに自宅から受講できるのがオンラインレッスンです。
早朝から深夜まで開講されていることが多く、インターネット環境さえあれば、自分の都合の良い時間に学習することができます。
費用も比較的安価なタイプから選べます。
講師の自己紹介や受講生の声を参考に、自分と相性のいい先生を自由に選べるのもメリットです。
一方で、オンラインレッスンのネイティブ講師は、HSK(汉语水平考试)の対策はしてくれても、日本の中国語検定を知らないことがあります。
中検には翻訳問題があるため、講師の日本語知識も不可欠です。
中検対策としてオンラインレッスンを利用する際は、中検を熟知している先生を選びましょう。
例えば、謝先生の中国語オンラインレッスンには中国語検定対策コースがあります。
コーチングは学習者の目標設定から日々の学習状況、さらには学習の継続に欠かせない精神面まで精鋭されたコーチがサポートします。
「いつ、何を、どれくらい」勉強すればいいのかがわかるため、遠回りすることなく最短で目標達成できるのが最大のポイントです。
中国語学習は目標設定、学習の継続、モチベーション維持、良質な教材が欠かせません。
コーチングならこれら全てが揃う学習環境があります。



\お問い合わせは毎日中国語公式LINEまで/


中国語検定のために時間や費用を投資して学校に通うのですから、確かな保証が欲しいですよね。
この章では合格への道を切り拓く4つのメリットを具体的に解説します。
中国語検定対策の学校に通うメリットの1つは、独学では習得が非常に難しい「発音」の指導を受けられる点です。
実は中国語検定は上級の準1級と1級以外は面接試験がありません。
初級から中級の試験は自分で発音できなくても合格することは可能です。
しかし、中国語の根幹をなしているのはピンインと声調(四声)と呼ばれる発音です。
実際、中検の試験問題でも準4級から3級までは発音の問題が多く出題されています。
中国語の発音は日本語より複雑で種類が多いため、日本人にとっては同じように聞こえてしまう発音が少なくありません。
この違いを聞き分けて正しく覚えるためには、自分でも正しく発音することが最大の近道です。
さらに「試験には合格したけれどさっぱり話せない」という事態を回避するためにも、発音は学習初期の段階でしっかりとプロに教わるのがおすすめです。
語学の学習は、時に孤独で長い道のりに感じられることがあります。
そんな時、学校には「中国語検定合格」という同じ目標を共有する仲間がいるため、モチベーションを維持しながら学習を続けられます。
事実、ある調査では、独学者よりスクール受講者の方が挫折率が低いというデータがあるそうです。
授業でクラスメイトとペアを組んで会話練習をしたり、休憩時間に試験の情報を交換したりと、自然な交流が生まれます。
仲間の頑張りが「自分も負けていられない」という良い刺激になり、つまずいた時には相談できる相手がいるという安心感もあります。
授業後に一緒にご飯を食べたりと、勉強以外のつながりを持っている人も多くいます。
中国語検定対策ができる学校では、指導経験豊富な専門家が長年のノウハウを基に作成したカリキュラムが用意されています。
これに沿って学習を進めることで、無駄なく効率的に実力を伸ばせるのは大きなメリットです。
独学でありがちなのが、「何から手をつける?」「どの教材がベスト?」という計画段階での迷走です。
気づけば、貴重な学習時間を情報収集だけで浪費してしまいかねません。
学校に通えばその必要はなく、受講生は目の前の課題に集中できます。
入門期は発音と基本文法、次に応用表現、そして試験直前は過去問演習と、段階に応じた最適な学習が体系的に組まれています。
特に、中検特有の「日中・中日翻訳問題」など、独学では対策しにくい分野もしっかりカバーされているため、安心して学習に専念できるのです。
中国語検定に合格するためには、過去問の分析や出題傾向の把握が不可欠です。
学校に通うことで、個人では収集が難しいこれらの情報を得ることができます。
多くの語学学校は、毎年多数の受験者を送り出しているため、膨大な試験データと合格ノウハウが蓄積されています。
講師陣は常に過去問題を研究・分析しており、「最近は翻訳問題にはインターネットや環境問題が増え、作文問題が追加された」といった具体的なアドバイスを授業で直接受けることができます。
出題形式の変更点や、申込期間、試験会場の情報など、うっかり見逃しがちな事務的な連絡をリマインドしてもらえるのも安心です。
こうした情報力が、合格の可能性をさらに高めてくれるでしょう。


中国語検定のための学校選びは、良い面だけでなく、デメリットにも注意が必要です。
ここでは「費用」「時間」「学習環境」の観点から、契約前に知っておきたい4つのポイントをお伝えします。
中国語検定のための学校で最も大きなハードルは、やはり費用面でしょう。
数千円の教材費から始められる独学に比べ、学校に通う場合は授業料や入学金など、まとまった費用が必要になります。
もちろんこれは、質の高い講師陣、快適な学習環境、そして長年のノウハウが詰まったオリジナル教材といった、質の高いサービスを受けるための「投資」とも言えます。
費用の目安として、通学型の語学スクールでは月額2〜5万円、専門学校では年間50万円以上かかることもあります。
この投資に見合う効果が得られるか、複数の学校の資料を請求し、慎重に比較検討することが大切です。
費用負担を軽減するために、国が支援する教育訓練給付金制度や、学校独自の奨学金制度が利用できないかも確認してみましょう。
通学型の学校を選ぶ場合、授業が固定の曜日・時間に行われるため、自分のスケジュールをそれに合わせる必要があります。
特に社会人や学生の場合、「急な残業で行けない!」「サークルの予定と重なった…」といった理由で授業を欠席せざるを得ない場面も出てくるでしょう。
これが続くと、学習の継続が難しくなってしまいます。
また、授業時間そのものに加えて、教室までの往復の通学時間も考慮しなければなりません。
例えば、片道30分の場所にある学校に週1回通うと、移動だけで毎週1時間が費やされることになります。
中検のための学校選びは、欠席した際に「振替制度」があるか、ライフスタイルと照らし合わせて無理なく続けられるかが重要ポイントです。
グループレッスン形式のクラスでは、自分の中国語のレベルと、クラス全体のレベルが微妙にマッチしていないことがあります。
もしクラスのレベルが自分より低いと、「今日の授業は簡単すぎたな…」と物足りなさを感じ、成長が実感できないかもしれません。
逆にレベルが高すぎると、「周りのペースが速くてついていけない…」と劣等感を抱き、モチベーション低下につながってしまいます。
このようなミスマッチを防ぐためには、入学前に必ずレベルチェックテストや体験レッスンを受け、自分の実力に合っているか肌で感じることが大切です。
もし少しでも不安を感じたら、完全に自分のペースで学習を進められるマンツーマンレッスンを選択するか、レベル設定が細かく分かれている実績豊富な学校を選びましょう。
語学学習の効果は、講師の指導力や知識だけでなく、その教え方や人柄といった「相性」にも大きく左右されます。
どれだけ優秀な講師であっても、自分との相性が合わなければ、学習意欲が削がれてしまう可能性があります。
例えば、理論的に1つ1つ理解したい生徒と、実践的な練習重視の講師では、互いに消化不良を起こしてしまうかもしれません。
人によって合う・合わないの感じ方はさまざまで、厳しくて「質問しにくい」と感じる場合もあれば、優し過ぎて物足りないと感じることもあります。
受講前には体験レッスンで実際にその講師との相性を確認しましょう。
受講開始後でも担当を変更できる制度がある学校を選ぶと、より安心して学習をスタートできます。


ここまでのメリット・デメリットを踏まえ、いよいよ学校選びです。
数ある選択肢の中から「ここなら頑張れる!」と心から思える1校を見つけ出すために、4つのチェックポイントを具体的にお伝えします。
中国語検定のために通う学校は、今の自分のレベルから目標とする級を目指せるコースがあるか確認しましょう。
例えば、ゼロから中検2級を目指す人と、すでに3級を持っていて2級を目指す人とでは学習内容が異なります。
ゼロから始める場合は、発音や文法の基礎から段階的にレベルアップできる形式が適しています。
すでに1つ前の級を持っているならば、目標級に特化したコースが効率的です。
また、日本の中検はHSKとは試験形式が違うため、中検が目標の場合はHSK対策では内容をカバーできません。
学校のウェブサイトやパンフレットで「中検対策コース」といったコース名を探し、カリキュラム内容をチェックしましょう。
もし自分の目指すべき級が分からない場合は、カウンセリングで相談に乗ってくれる学校や、レベルチェックが充実している学校を選ぶのが安心です。
学習を継続するためには、費用が予算内で無理なく通えるという現実的な条件クリアが不可欠です。
どんなに評判の良い学校でも、授業料が高すぎて生活を圧迫したり、通学が面倒で足が遠のいてしまったりしては本末転倒です。
料金については、月謝制か一括払いか、入学金や教材費は別途必要なのかといった総費用を計算しましょう。
立地については、Googleマップなどで実際の移動時間を調べ、残業後でも通えるかなどを具体的にシミュレーションしてみると実感しやすくなります。
また、予算内だからといって安さだけで判断せず、総合的な費用対効果を考えることも大切です。
パンフレットやウェブサイトの情報だけでは分からないのが、「授業のリアルな空気感」や「講師との相性」です。
学習のモチベーションは、講師の教え方や人柄、クラスメイトとの関係性といった、実際にその場に身を置いてみないと分からない要素に大きく左右されます。
体験レッスンでは、「講師は質問しやすい雰囲気か」「授業のペースは自分に合っているか」「他の生徒のレベルや熱意はどうか」といった点を重点的にチェックしましょう。
オンラインスクールの場合は、「システムの操作は簡単か」「音声や映像はクリアか」も重要な確認項目です。
多くの学校が無料体験レッスンを提供していますので、2〜3校は参加し、「楽しい」「分かりやすい」という直感を大切にしながら比較検討することが、失敗しない学校選びの最も確実な方法です。
学校の広告や宣伝文句だけでなく、第三者による客観的な評価である「口コミ」と、指導力の証明となる「具体的な合格実績」は重要な判断材料です。
口コミからは、実際に通った人でなければ分からないリアルな長所や短所を知ることができます。
GoogleマップのレビューやSNSなど複数の情報源を比較して、総合的に判断しましょう。
また、合格実績は、その学校の検定対策ノウハウが本物であるかを判断するための信頼できる指標です。
「2024年度 中検2級 合格率90%」のように、具体的な数字で公表している学校は信頼性が高いと言えます。
「合格者多数」といった曖昧な表現には注意しましょう。
体験レッスンでの主観的な感想と、口コミや実績という客観的なデータが納得できる学校選びにつながります。
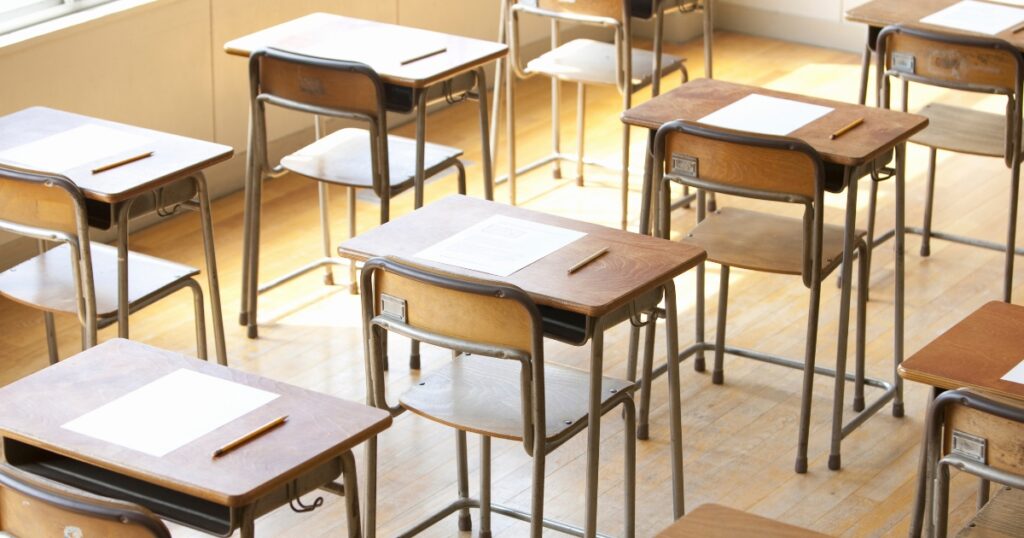
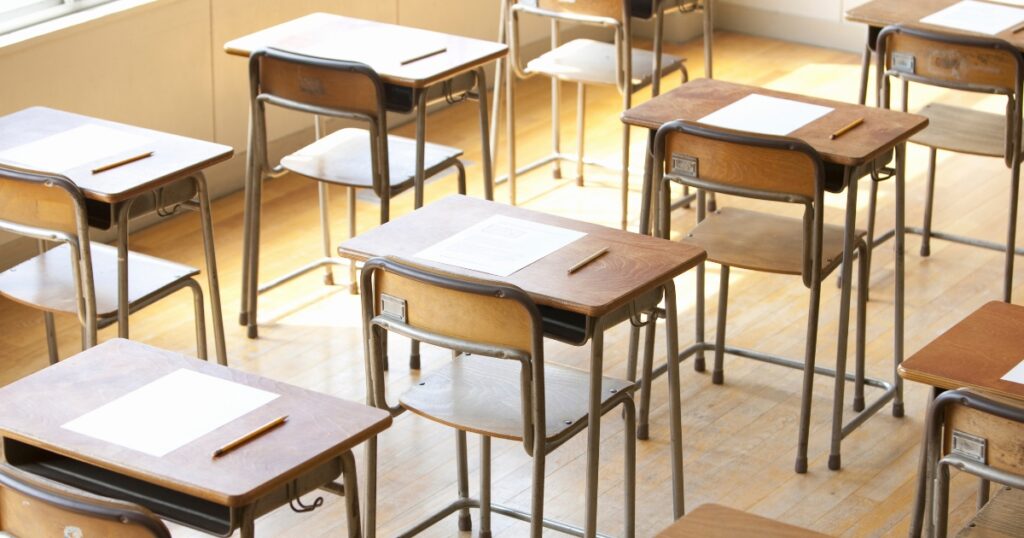
学校に通わず独学で中国語検定に合格している人もいます。
市販のテキストや問題集を活用した「完全独学」スタイルは、何と言ってもコストを最小限に抑えられるのが魅力です。
学習する時間や場所を一切選ばないため、ライフスタイルに合わせて柔軟な計画を立てられます。
まずは、中検公式サイトにある試験問題・解答や、かんたんレベルチェックで、現在の実力を知るところから始めましょう。
目標級が定まったら、検定対策用の市販教材で勉強を進めます。
「合格奪取!」シリーズや、「出るとこだけ!合格一直線」シリーズ、「キクタン」シリーズは定評があります。
基礎固めがまだの場合は、スマートフォンの学習アプリも手軽に利用できて便利です。
ただし、学習計画の管理やモチベーションの維持をすべて自分で行う必要があり、質問できる相手がいない点が大きな課題です。
強い意志と自己管理能力が必要です。
◎具体的な勉強法は、中国語検定に合格できる勉強法とは?おすすめの参考書も紹介!の記事で紹介しています。
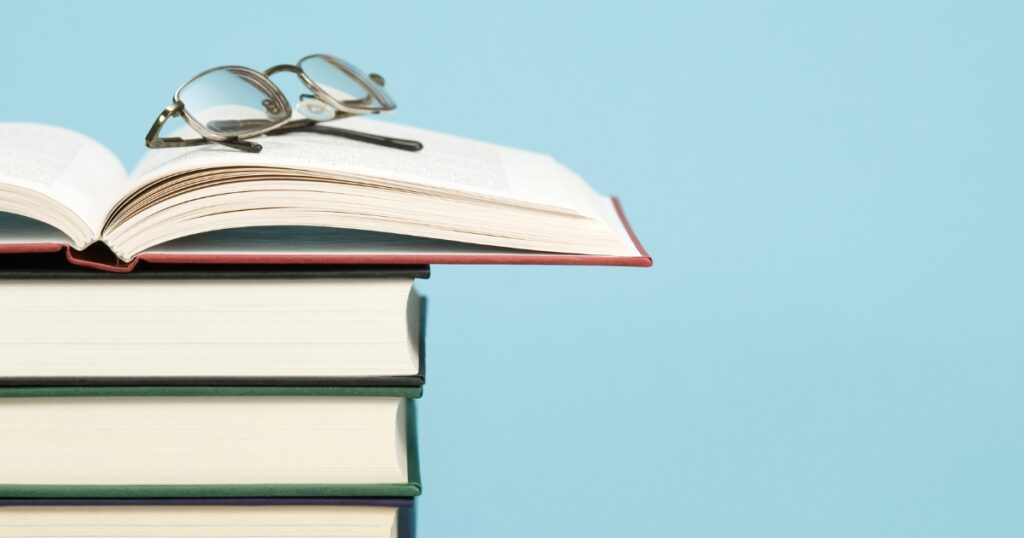
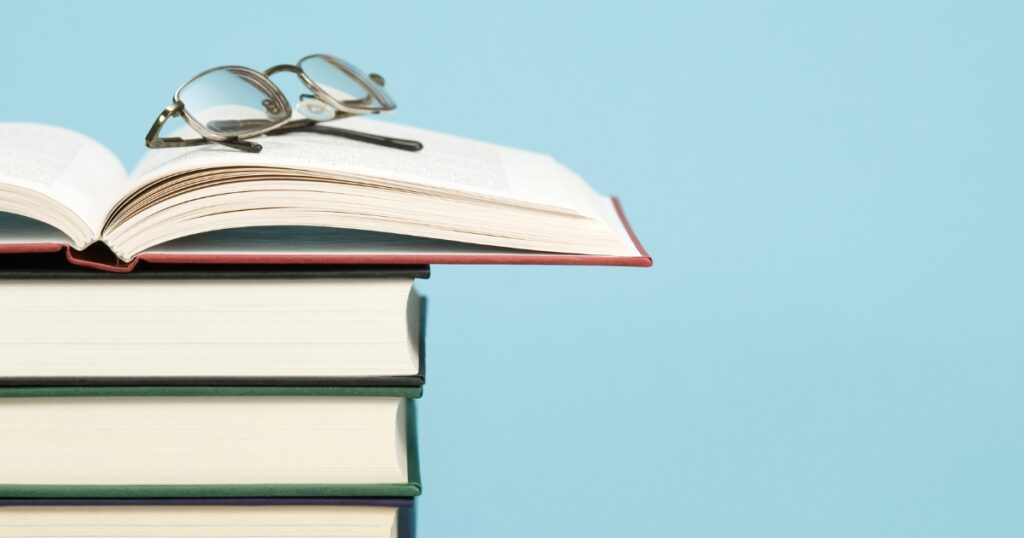
中国語検定は日本語を母語とする人のための中国語の試験で、短期合格には相応の試験対策が必要です。
中国語検定対策コースのある中国語学校なら、出題内容や形式に熟知した講師から直接指導を受けることができます。
学校は通学タイプ、オンライン、グループ、マンツーマンなどさまざまなタイプがあります。
予算や通学時間など現実的な面をはじめ、自分のレベル、講師との相性、雰囲気、合格実績や口コミなどを総合的に判断して選びましょう。
中国語学習は継続した学習が最も大切です。
毎日中国語は精鋭コーチ陣が毎日の中国語学習をサポートします。



詳しくは毎日中国語公式LINEまで!
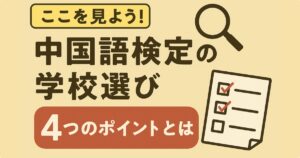
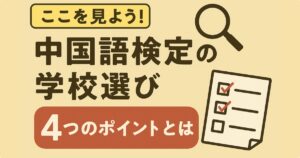
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
