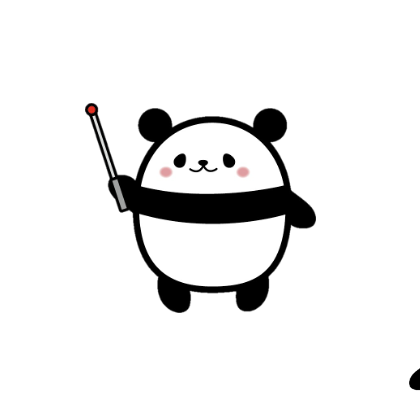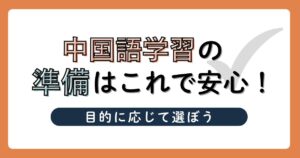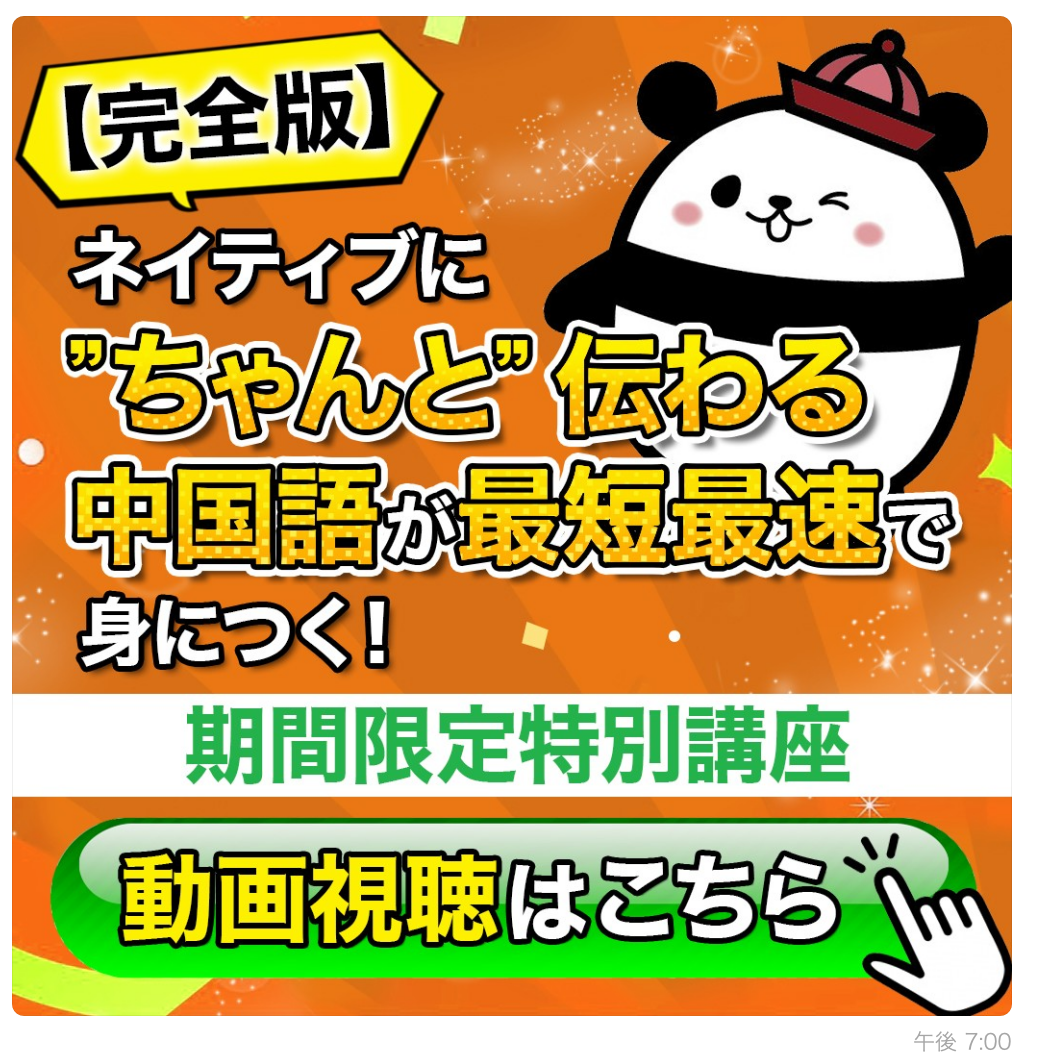
中国語学習の準備はこれで安心|目的に応じて勉強方法と目標を選ぼう!
この記事でわかること
- 中国語学習の準備は具体的な目標を立てることからスタート
- 中国語学習の教材は目的にあったものを選択
- 学習準備が整ったら発音から始めよう!

中国語の学習を始めたいけれど何を準備したらいいですか?
語学学習というと「教科書とノート」というイメージがありますよね。
これも1つの勉強方法ですが、今は便利なアプリや動画もあります。
そして、教材だけでなく、学習時間や学習環境、さらには「心構え」も必要です。
いざはりきって勉強を始めたけれど、「難しくて挫折してしまった」、「続けられず三日坊主になってしまった」とならないためにも、準備をしてから学習を開始しましょう。
この記事では、中国語学習を始める目的にあわせた準備方法と、どの学習者にも共通して準備しておきたい事項を解説します。
準備万端でスムーズに中国語学習の一歩を踏み出しましょう!
目次
まずは中国語学習への「心」と「時間」を準備しよう!
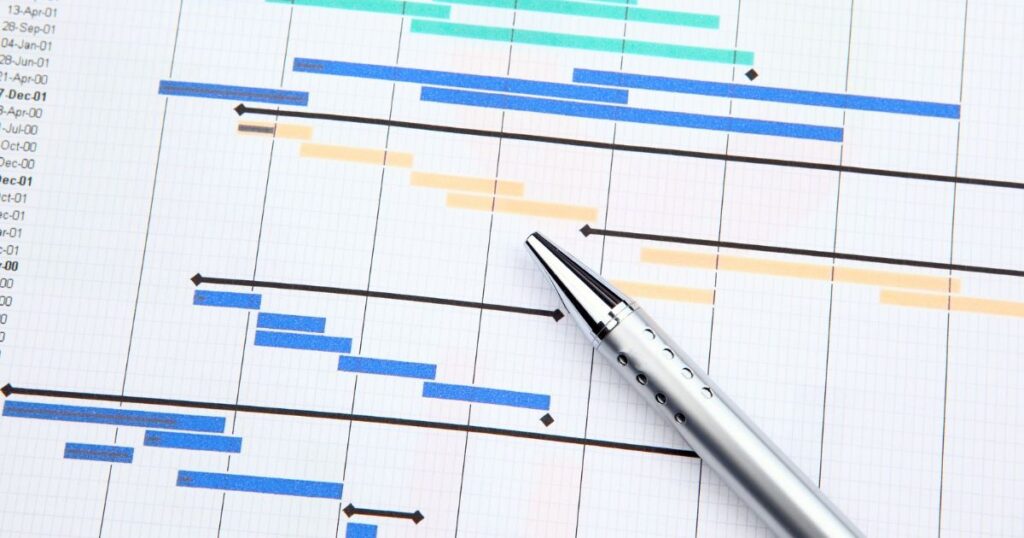
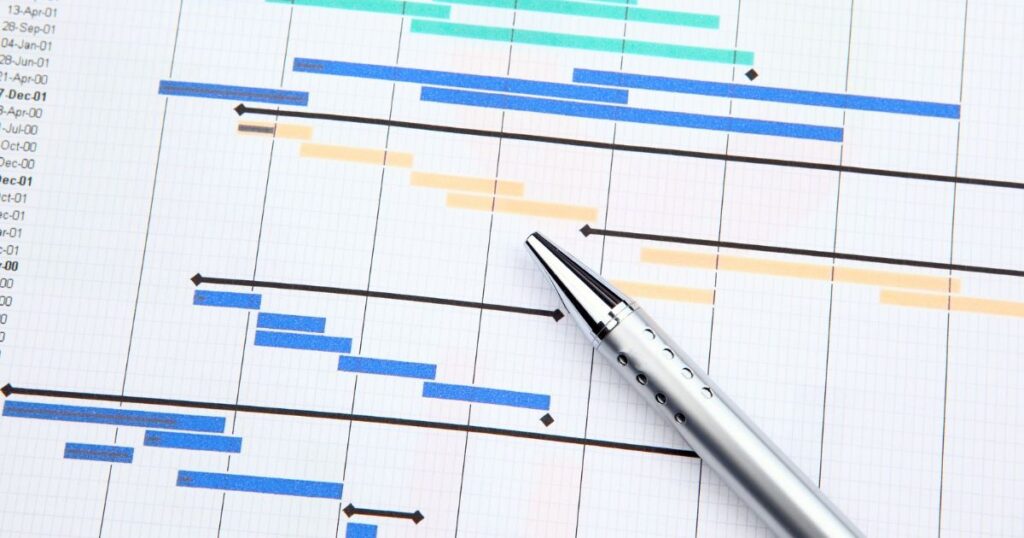
中国語を学び始める前に、まず大切なのは「心」と「時間」の準備です。
なんとなく思い付きで勉強を始めてしまうと、あれもこれも手を出してしまい、結局どれも中途半端になってしまうことがあります。
ここでは、学習をスムーズに進めるために意識しておきたい3つのポイントを紹介します。
- 学習目標を明確にする
- 学習時間を確保する
- モチベーションを保つ工夫
準備(1)学習目標を明確にする
中国語学習を続けていく上で、一番の土台になるのが「なぜ中国語を学ぶのか」という目的です。
ただ「なんとなく話せるようになりたいな」と思うだけでは、学習の優先順位があいまいになり、続けにくくなってしまいます。
例えば、次のように目標を立ててみましょう。
・旅行が目的 → 「6か月後の上海旅行で、レストラン注文や道案内を中国語でこなす」
・キャリアが目的 → 「1年以内にHSK4級に合格して、ビジネスシーンで基本的なやり取りができるようになる」
このように具体的に描けると、必要な単語や表現が絞られ、効率よく学習できます。
「自分はなぜ中国語を学びたいのか?」を、まずは紙に書き出してみるのもおすすめです。
準備(2)学習時間を確保する
社会人や学生の方にとって、毎日まとまった時間をとるのはなかなか難しいですよね。
でも、10分を数回に分けて学ぶだけでも効果はしっかりあります。
- 通勤時間にアプリで単語チェック
- 昼休みにリスニング練習
- 朝の30分を「朝活」として勉強
こうしたスキマ時間の積み重ねが、大きな力になります。
また、できるだけ毎日同じ時間に学習を組み込むと習慣化しやすくなります。



最近は分散学習にぴったりのアプリも多いので、上手に活用して学習を続けましょう。
準備(3)モチベーションを保つ工夫
完璧を求めすぎると、「できなかった…」と落ち込みやすくなってしまいます。
大切なのは 「80点でOK!」という気持ちです。
多少の間違いがあっても、はじめは「伝われば十分」です。
その姿勢こそが上達を早めます。
また、モチベーションは感情に左右されやすいので、仕組みで管理してしまうのがおすすめです。
例:
・スケジュール表で進捗を見える化
・SNSで学習仲間と交流
・「字幕なしで中国ドラマを理解する」など、楽しみながらできる目標を組み込む
小さな成功体験を積み重ねれば、自然と学習が習慣になります。
「楽しい」「できた!」を感じながら、焦らず続けていきましょう。
【目的別】中国語学習の準備
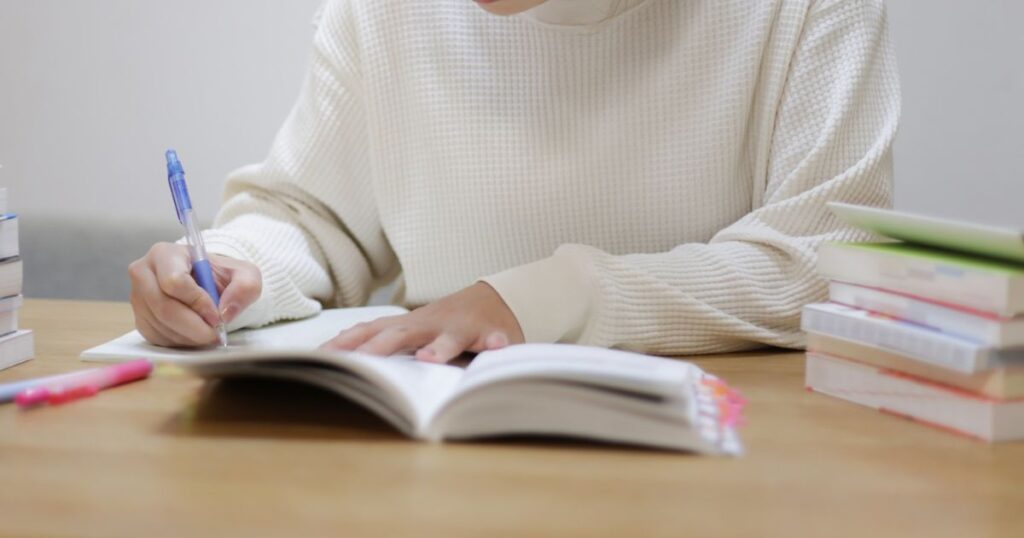
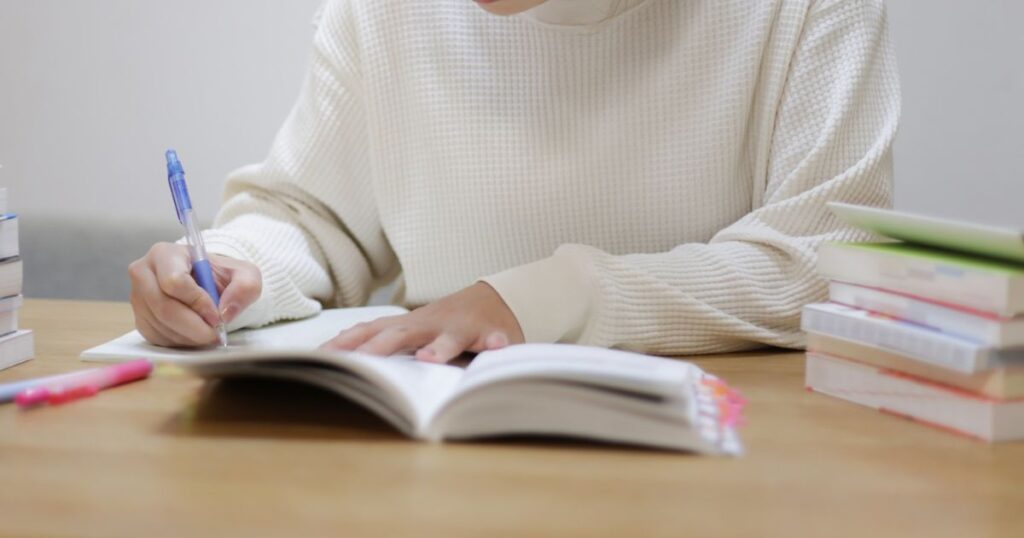
「中国語を学びたい!」と思ったとき、その理由は人によってさまざまですよね。
実は、目的によっておすすめの教材や学習スタイルは大きく変わります。
この章では、学習目的ごとに「まず準備しておきたい教材」や「学習の進め方」を紹介します。
あなたに合った方法を選んで、効率的に続けていきましょう。
- 仕事で必要な場合
- 大学の専攻・第二外国語で学ぶ場合
- 資格試験(HSK・中検)に挑戦する場合
- 趣味として楽しく学ぶ場合
- 中国のドラマや映画が好きな場合
- 中国旅行のために学ぶ場合
目的(1)仕事で必要な場合
・HSKの参考書で基礎固め
・ビジネス用語や専門用語の学習書
・実践的なビジネス会話集
ビジネスの現場では、日常会話だけでなく専門的な表現も必要になります。
まずは HSK4級レベル(日常会話ができる程度)を目標に基礎を固め、そのうえで業務に必要な専門用語を追加していくのがおすすめです。
目的(2)大学の専攻・第二外国語で学ぶ場合
・授業で使う教科書とノート
・先生からの指示に沿った教材
・信頼できる辞書アプリや学習アプリ
中国語を専攻する場合は、卒業までに HSK6級や留学を目指すことも珍しくありません。
辞書は有料のしっかりしたもの(例:小学館『中日・日中辞典』)を使うと安心です。
第二外国語で学ぶ場合は授業の範囲は限られますが、「単位を取るだけ」ではもったいないかも。
これをきっかけに、資格試験に挑戦するのも良いステップになります。
目的(3)資格試験(HSK・中検)に挑戦する場合
・基礎を学べる入門書や学習アプリ
・受験級に対応した対策本(HSK公式テキスト、合格奪取シリーズなど)
・過去問題集
HSKと中国語検定(中検)は出題傾向が異なります。
まずはアプリなどで基礎を固め、その後は受ける級に合わせた対策本や過去問演習をしっかり進めていくのが合格への近道です。
目的(4)趣味として楽しく学ぶ場合
・イラストや図解が豊富な入門書(例:『ゼロからスタート中国語』シリーズ)
・ゲーム感覚で学べるアプリ(Duolingo、HelloChineseなど)
・YouTubeなどの動画教材
趣味で学ぶなら「楽しいこと」が一番大切です。
机に向かう勉強が続かなくても大丈夫。
アプリや動画で少しずつ取り入れて、気軽に中国語に触れる習慣を作ってみましょう。
目的(5)中国の音楽・ドラマが好きな場合
・好きな作品そのもの(音楽・ドラマ)
・歌詞やセリフを書き写すノートやアプリ
・翻訳アプリ
ドラマや歌のセリフには難しい表現も多いですが、翻訳アプリを使えば ピンイン(発音)や意味を確認できます。
最初は丸ごと理解しようとせず、好きなフレーズを真似して口にしてみるのがおすすめです。
「推し作品」で学べると、モチベーションも長続きしますよ。
目的(6)中国旅行のために学ぶ場合
・発音を学べる学習アプリ
・旅行会話フレーズ集
・翻訳アプリ
旅行では「道を聞く」「食事を注文する」など限られた表現が中心です。
ただし中国語は発音が違うと伝わりにくい言語なので、まずは発音練習をしておくと安心です。
さらに、現地では聞き取れない場面も多いので、翻訳アプリを準備しておくと心強い味方になります。
独学か先生に習うか ― 学習スタイルを決める
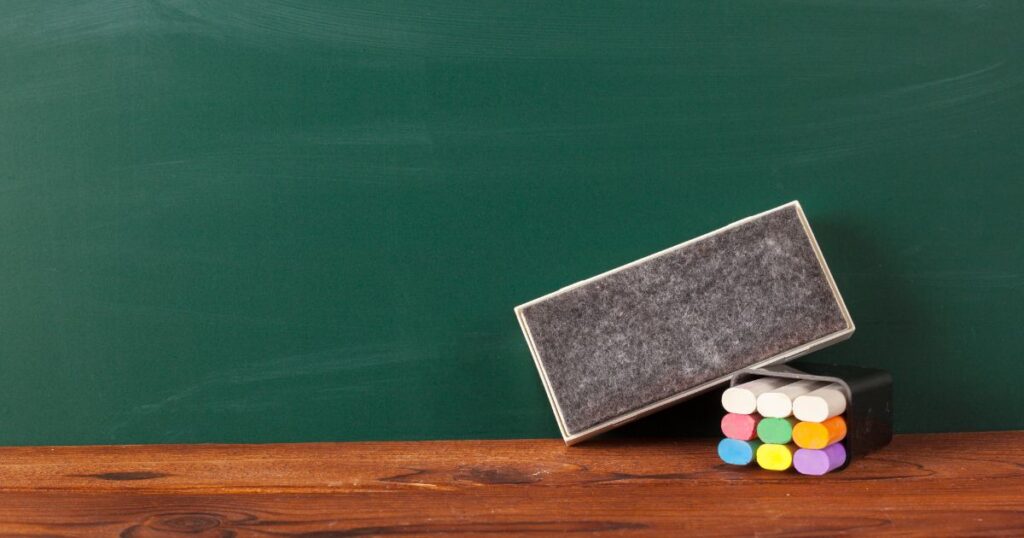
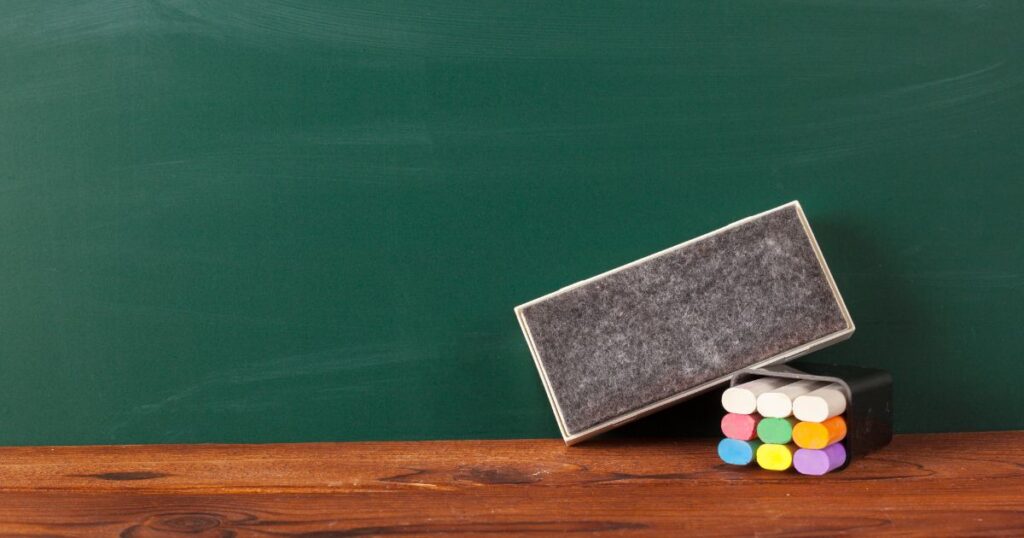
中国語学習を始めるとき、最初の大きな決断が 「独学で進めるか」「先生に習うか」 という学習スタイルの選択です。
それぞれにメリット・デメリットがあり、目的やライフスタイルによって最適な方法は変わります。
この章では代表的な3つの学び方を紹介します。
- 完全独学(教材・アプリ中心)
- オンラインレッスン(ネイティブとの会話練習)
- パーソナルコーチング(徹底サポート型)
学習スタイル(1)完全独学(教材・アプリ中心)
メリット
・数千円程度の教材費で始められ、費用を大幅に抑えられる
・自分のペースで、苦手分野を重点的に学習できる自由度の高さ
・アプリや音声機能を使って効率よく学べる(速度調整・リピート再生など)
デメリット
・発音を客観的にチェックしてもらえない
・質問相手がいない
・モチベーション維持が難しい
2025年現在はアプリや教材が大幅に進化しており、正しい勉強法を押さえれば半年で簡単な会話ができるレベルに到達することも可能です。
中には数年の独学でHSK6級に合格した実例もあります。
「コストを抑えたい」「自分でコツコツ続けたい」という人におすすめです。
学習スタイル(2)オンラインレッスンを受ける
メリット
・独学で不足しがちな発音指導をネイティブから直接受けられる
・実際の会話を通して「通じる中国語」を身につけられる
・時間や場所を選ばず、気軽に受講できる
費用の一例(2025年毎日中国語調べ):
- CCレッスン :平日毎日25分 月額9,020円(税込)
- NetChai :平日毎日25分 月額8,980円(税込)
- 天天中文 :週3日25分 月額9,300円(税込)
※他にも複数料金プランがあります。詳細は各スクール公式サイトをご覧ください。
週に1回週末だけのレッスンではなかなか上達しないので、可能ならば毎日の受講がおすすめです。
レッスン日以外は独学して、発音と会話練習のみオンラインレッスンを受けるハイブリッド型も費用を抑えられる賢い利用法です。
学習スタイル(3)コーチングを受ける
メリット
・個人の学習目標や生活リズムに合わせた学習計画を作ってくれる
・弱点分析、効率的な学習プラン、モチベーション管理を一括でサポート
・忙しい社会人でも短期間で結果が出やすい
独学やオンラインより費用は高額ですが、「短期間で確実に成果を出したい」「自己管理が苦手」という人には最適です。



ご相談は毎日中国語公式LINEまで。
避けよう!よくある中国語学習準備の失敗例
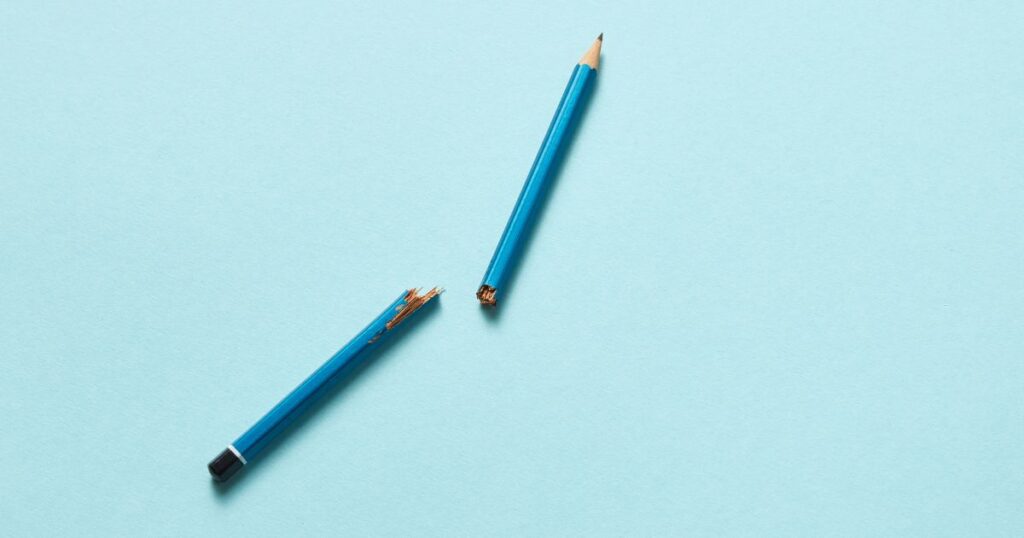
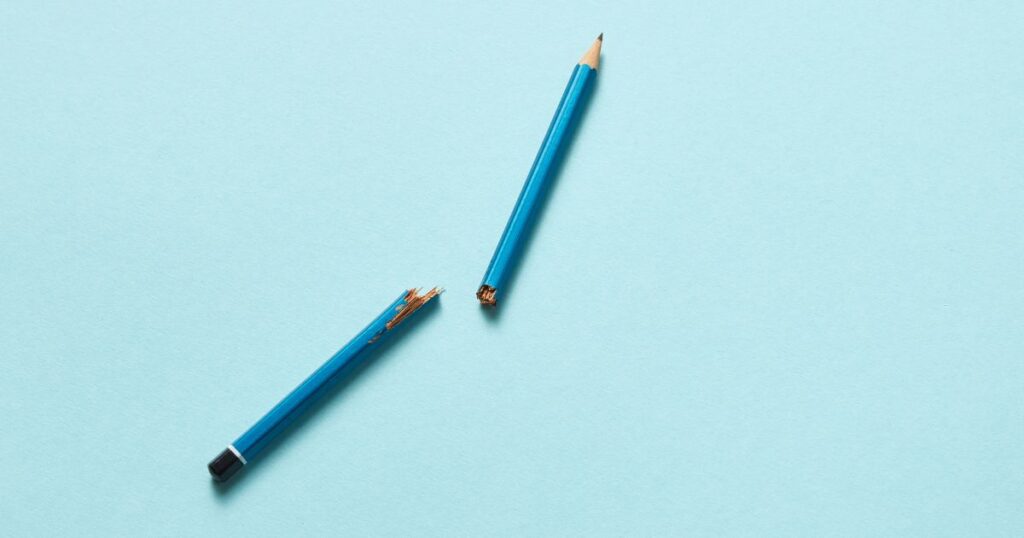
さあ中国語を勉強しよう!と思っても、準備が間違っていると思うように進まず、途中で嫌になってしまったり挫折してしまったりします。
この章では、ありがちな準備の失敗例を紹介します。
あなたも心当たりありませんか?
- 目標と学習計画なしに気分で始める
- 教材を買ったが進んでいない
- 単語と文法中心で発音は後回し
失敗(1)目標と学習計画なしに気分で始める
「とりあえず中国語を勉強してみよう!」と勢いで始めるのは悪いことではありません。
ただ、ゴールがはっきりしていないと途中で「何のためにやっているんだろう?」と迷ってしまい、勉強が続かなくなることが多いです。
例えば「旅行で買い物ができるようになりたい」「半年後にHSK3級を受けたい」など、小さくても具体的な目標を設定することが大切です。
そこから逆算して「毎日10分アプリ」「1週間でテキストを1課ずつ」などシンプルな計画を立てれば、学習の道筋が見えて挫折しにくくなります。
失敗(2)教材を買ったが進んでいない
入門書、単語帳、アプリ、問題集……「形から入る」タイプの人がやりがちな失敗です。
たくさんの教材をそろえたのに、結局どれも最初の数ページで止まってしまう、なんてことありませんか?
実際には、教材は1~2つを集中してやり切ることが一番の近道です。
最後まで終えれば自信がつき、「自分は続けられる」という成功体験になります。
もし教材選びに迷うなら、まずは「発音解説がある入門書+学習アプリ」のセットをスタートラインにするのがおすすめです。
失敗(3)単語と文法中心で発音は後回し
「文字は漢字だから、意味は何となくわかるし大丈夫!」と感じて、単語暗記や文法ばかりに集中してしまう初心者は少なくありません。
ところが、発音を後回しにすると 「書ける・読めるのに全然通じない」 という壁にぶつかります。
中国語は声調が違うと意味が変わるため、最初のうちにピンインと声調を徹底的に練習しておくことがとても重要です。
アプリの音声リピート機能や、オンラインレッスンで講師にチェックしてもらうと、自己流のクセを防げます。
準備が整ったら「発音」からスタートしよう!


準備はできましたか?いよいよ中国語学習のスタートです。
中国語学習で、最初に取り組むべきは 声調(四声)とピンイン です。
中国語には4種類の声調(音の高低)があります。
また、日本語は「ひらがな」や「カタカナ」で漢字の読み方を書きますが、中国語は「ピンインと呼ばれる」アルファベットを使った発音表記で漢字の読み方を記します。
発音から始めるのには大きな理由があります。
・声調を間違えると、意味が変わって通じなくなる
・ピンインをおろそかにすると、聞き取れない・発音できない
中国語の学習は、この2つを土台にするとスムーズに進みます。
アプリや教材に付属の音声、YouTube動画などを活用して、まずは声調とピンインから始めましょう!
◎発音以降の学習方法については「【2025年版】中国語学習ロードマップ完全ガイド|初心者から上級者までの学習法」の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧くださいね。
まとめ


中国語の学習は、まず正しい準備から始まります。
準備をせずに勢いで進めてしまうと、行き当たりばったりになったり、途中で方向性を見失って挫折につながってしまうこともあります。
だからこそ、最初に「旅行」「資格」「ビジネス」などの目的を明確にすることが大切です。
その上で、目的に合った教材を選び、自分に合った学習スタイルを決めれば、迷わず着実に進められますよ。
もし「短期間でしっかり成果を出したい」「効率的なやり方を知りたい」と思ったら、ぜひ一度ご相談ください。
毎日中国語公式LINEでは、伝わる中国語を身につけるための学習情報やヒントをお届けしています。



あなたの中国語学習を全力でサポートします!