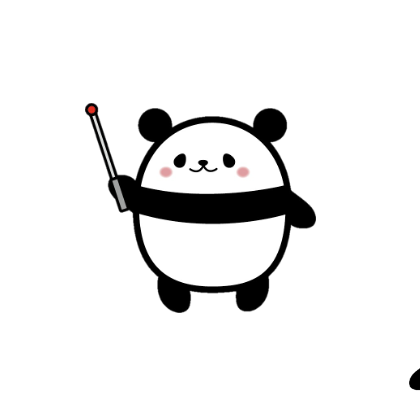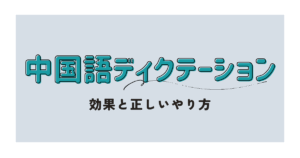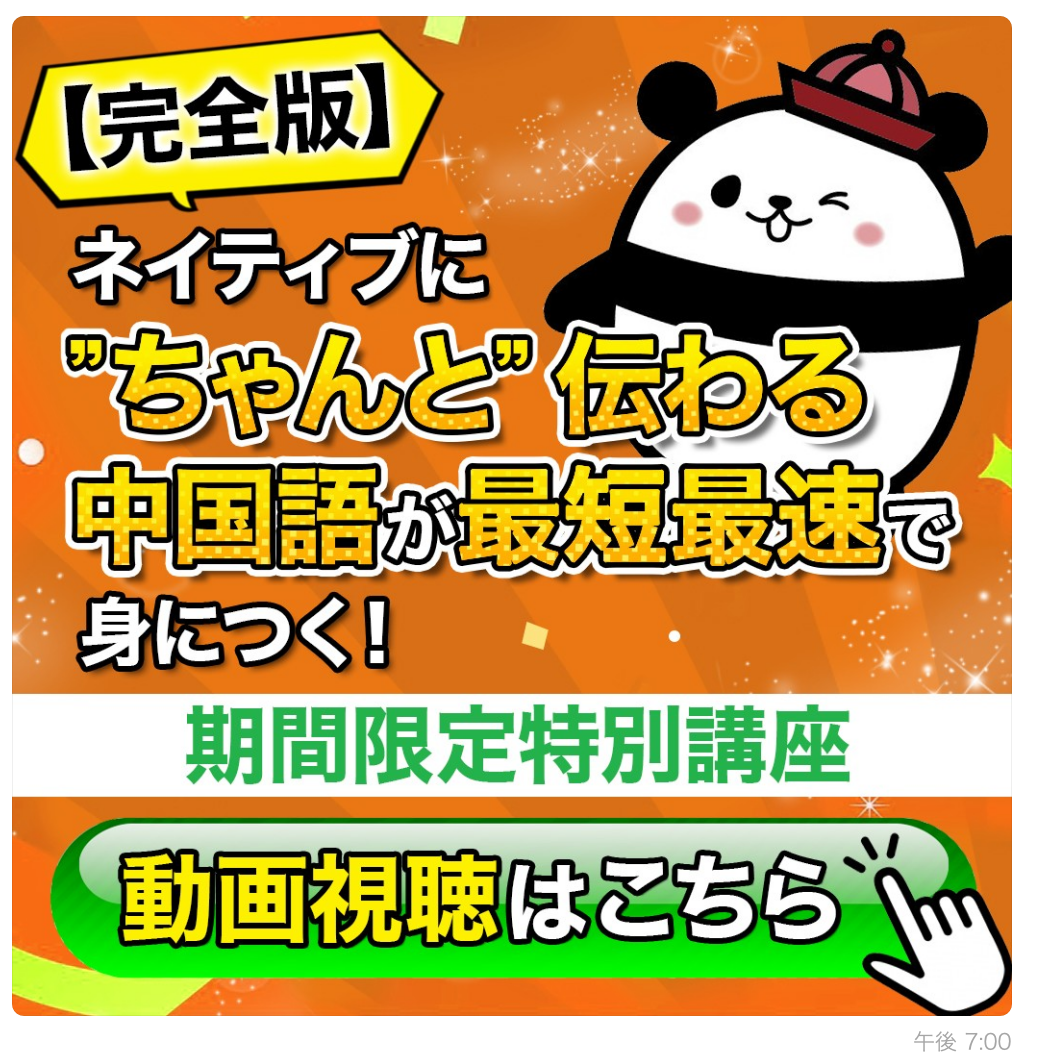
中国語ディクテーションの効果と正しいやり方|教材も紹介
この記事でわかること
- ディクテーションとは聞いた音声をそのまま書き取る練習法のこと
- 中国語のディクテーションは聞き取りだけでなく、総合的な中国語力強化につながる
- 中国語のディクテーションは、短い文のピンインと声調を書くことから始めよう!

中国語のディクテーションは効果がありますか?どうやったらいいですか?
「ディクテーション」と聞くと、なんだか難しそうでハードルが高い感じがしますよね。
実際、母国語の日本語でも、聞いた音声を1文字も間違えずにそのまま書き取るのは意外と難しいものです。
書き取るより音声のスピードの方が速いので、短時間でサッと終わらせることはできません。
それでも、細部まで耳を澄ませて書き取る練習をすると、普段は聞き流していた部分が「実は分かっていなかった」と気づけます。
つまり、ディクテーションは弱点発見につながる学習法なのです。
この記事では、中国語のディクテーションの効果と正しいやり方、さらにレベル別のおすすめ教材を紹介します。



まずは「1日1文」から、チャレンジしてみましょう!
目次
中国語のディクテーションとは?
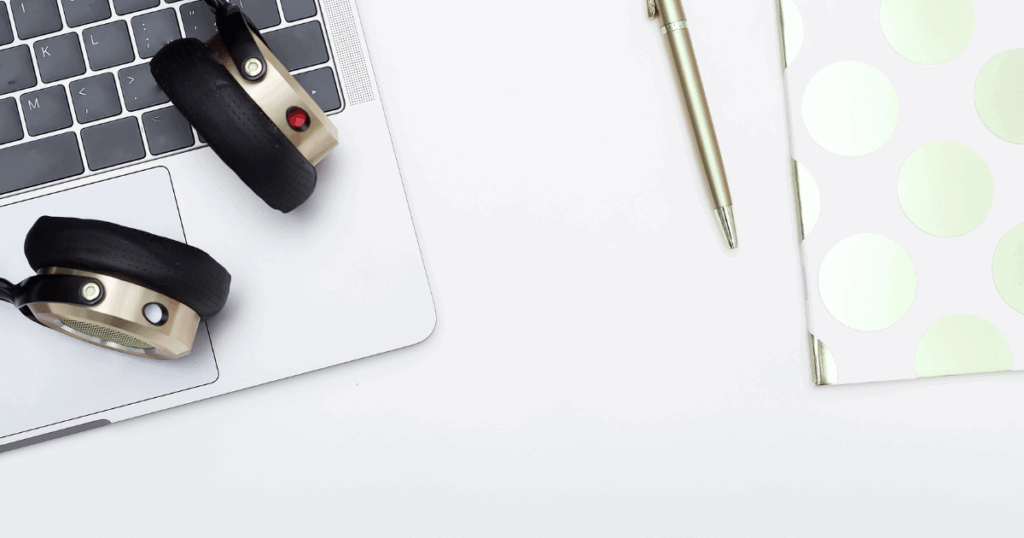
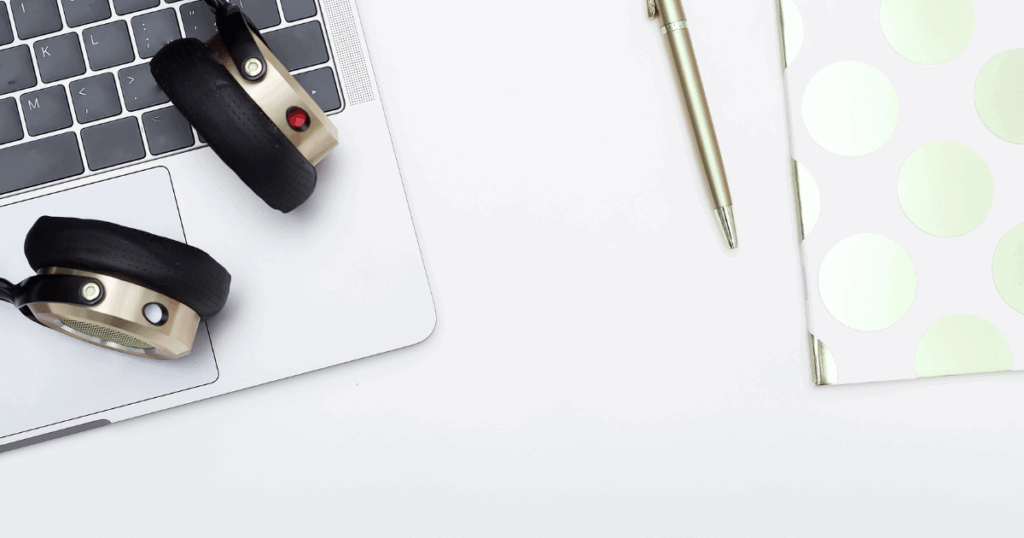
「ディクテーション」とは、音声を聞いて、そのまま文字に書き取る学習法のことです。
一見シンプルですが、実際に取り組むとさまざまな弱点が見えてきます。
例:
- 聞き取れていない音
- 覚えていない単語
- 理解できていない文法
こうした「抜け落ち」を可視化できるのが、ディクテーションの大きな特徴です。
中国語学習においても、ディクテーションは1つの学習方法として広く取り入れられており、リスニング力を伸ばしながら、単語・文法理解も深めることができます。
さらに、ただ耳で聞くだけでなく「書く」という動作を伴うため、視覚・聴覚・運動(書き取り)の3つの記憶回路を同時に刺激できるのも大きな利点です。
それでは次の章で、ディクテーションの具体的なメリットと、実際にどう取り組めばよいかを見ていきましょう。
中国語ディクテーションのメリット
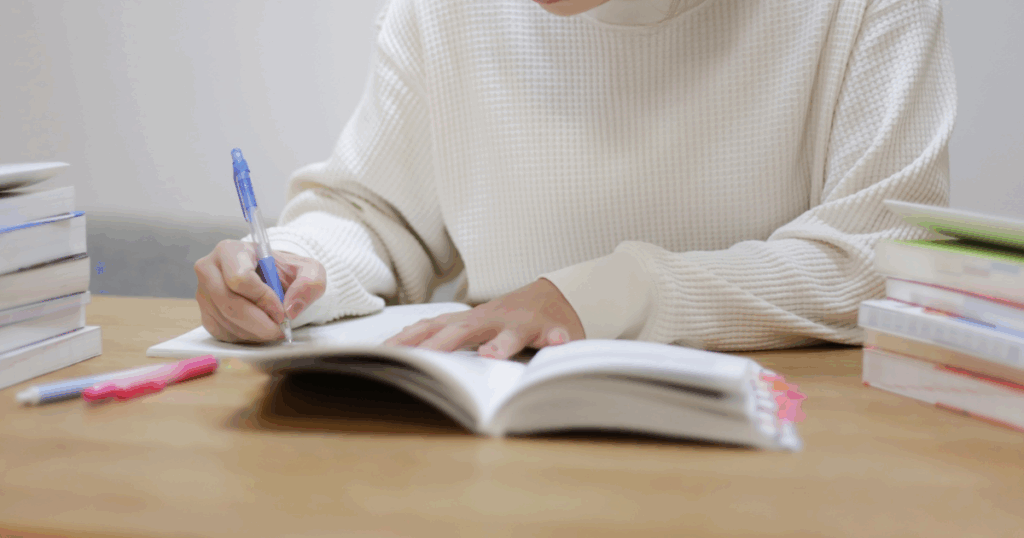
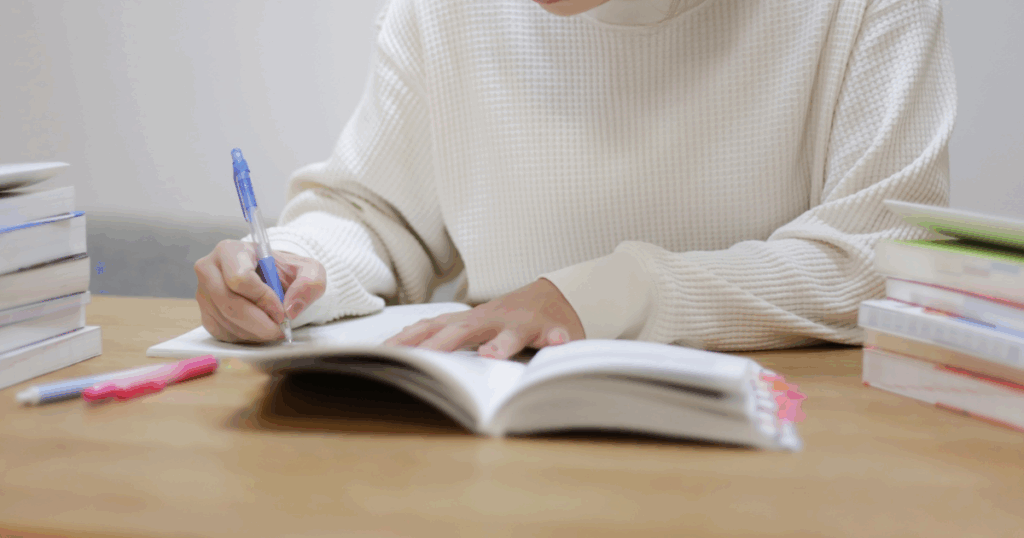
ここでは、中国語学習におけるディクテーションのメリットを具体的に見ていきましょう。
大きく分けると次の4つのメリットがあります。
- メリット(1)リスニング力の向上
- メリット(2)単語力と文法理解の同時強化
- メリット(3)弱点を可視化でき、学習計画を立てやすい
- メリット(4)シャドーイングとの相乗効果
メリット(1)リスニング力の向上
ディクテーションの大きな効果は、リスニングの「音の解像度」を高められることです。
中国語には4つの声調と、日本人には区別しにくい似た音が豊富にあります。
例:
- chi と qi(どちらも「ち」に聞こえる)
- an / ang / eng(どれも「あん」に近く聞こえる)
- z / zh / j(全部「じ」に聞こえる)
聞き流すだけでは「全部同じ」に聞こえてしまうこれらの音も、ディクテーションでピンインと声調を意識して書き取る練習をすることで、「あ、ここは qi だ」「これは eng だ」と少しずつ違いに気づけるようになります。
この過程を繰り返すことで、脳内に正確な「音のデータベース」が構築されます。
「なんとなく聞こえる」から「はっきり区別できる」へとステップアップできるのです。
メリット(2)単語力と文法理解の同時強化
ディクテーションはリスニングだけでなく、単語力と文法理解を同時に鍛えられる学習法です。
中国語をただ聞き流していると「なんとなく意味はわかるけれど、細部があいまいなまま」になりがちです。
しかし、実際に書き取ろうとすると、語順や使われている単語を正確に判断しなければならないため、自然と文法や語彙の知識に意識が向きます。
例えば、次のような聞き間違いが起こります。
❌ 他 经常 花花。
⭕️ 他 经常 画画。(彼はよく絵を描く)
→ 動詞“画 / huà”(描く)を、名詞“花 / huā”に聞き間違えるケース。文法的にここは動詞が来る位置なので、“花”だと不自然。
❌ 他 去门 了。
⭕️ 他 出门 了。(彼は出かけた)
→ “出 / chū”と“去 / qù”を聞き間違えるケース。どちらも「ちゅう」に聞こえがちだが、「門に行った」は不自然。
このように、ディクテーションでは単語を正しく聞き取り、正しい文法で書き出す過程そのものが、単語学習と文法復習を同時に兼ねています。
メリット(3)弱点を可視化でき、学習計画を立てやすい
ディクテーションの大きな特徴は、自分の弱点が具体的に分かることです。
聞き流すだけでは「よく分からなかったな…」で終わってしまいますが、ディクテーションでは「書けなかった部分」としてはっきり残るため、弱点が見える化されます。
聞き取れなかった原因は大きく分けて3つに整理できます。
- そもそも単語や文法を知らなかった
→ 知識不足が明確になるので、語彙や文法の復習につなげられる。 - 知っている単語や文法なのに聞き取れなかった
→ 発音の認識があいまい、あるいは音の連続で聞き落としたことが分かる。 - スピードについていけなかった
→ 単語も文法も分かっているのに処理が追いつかない。シャドーイングや反復練習で改善できる。
このように、ディクテーションは「自分がどこでつまずいているのか」を分類して教えてくれる練習法です。
弱点の正体を知ることで、復習の優先順位を決めやすくなり、効率的に学習を進めることができます。
メリット(4)シャドーイングとの併用効果
ディクテーションは、それ単体でも効果的ですが、シャドーイングと組み合わせることでさらに力を発揮します。
ディクテーションでは「聞き取れない部分」が可視化され、自分の弱点が明確になります。
次にその音声を使ってシャドーイング(音声を聞きながらすぐ後を追って発音する練習)をすると、聞き取れなかった箇所を意識しながら声に出すことができるのです。
メリット(3)で挙げた例を使って見てみましょう。
- 「他经常画画」(彼はよく絵を描く)のディクテーションで、“画”を“花”と聞き間違えた。
→ 声調の違いや文構造に注意する。 - 「他出门了」(彼は出かけた)を「他去门了」と聞き間違えた。
→ “出 / chū”と“去 / qù”の発音の違いに注意しながら、「出门」の形を定着させる。
このように、ディクテーションで 「弱点を発見」 → シャドーイングで 「繰り返し口に出して克服」 という流れを作ることで、リスニング力とスピーキング力を効率的につなげることができます。
中国語ディクテーションの正しいやり方
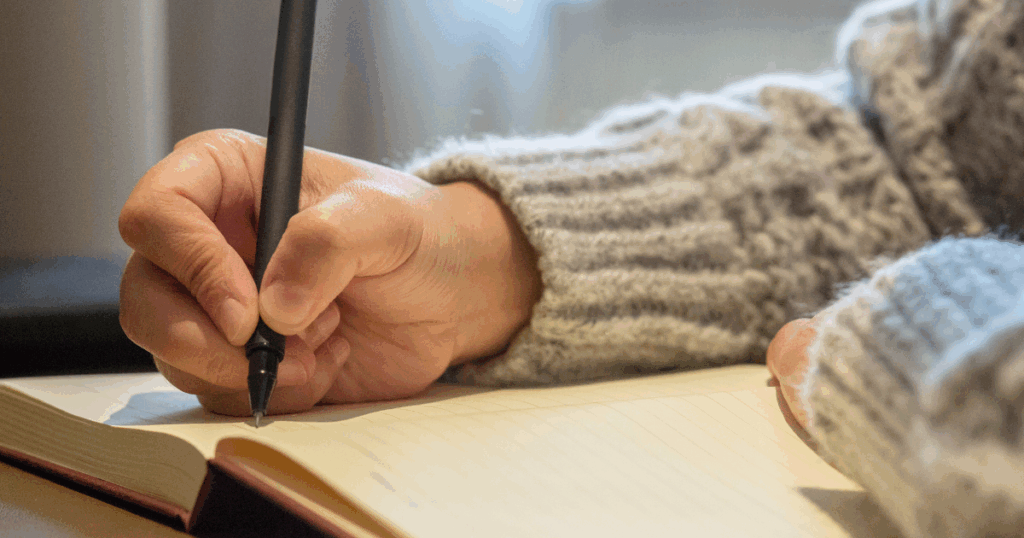
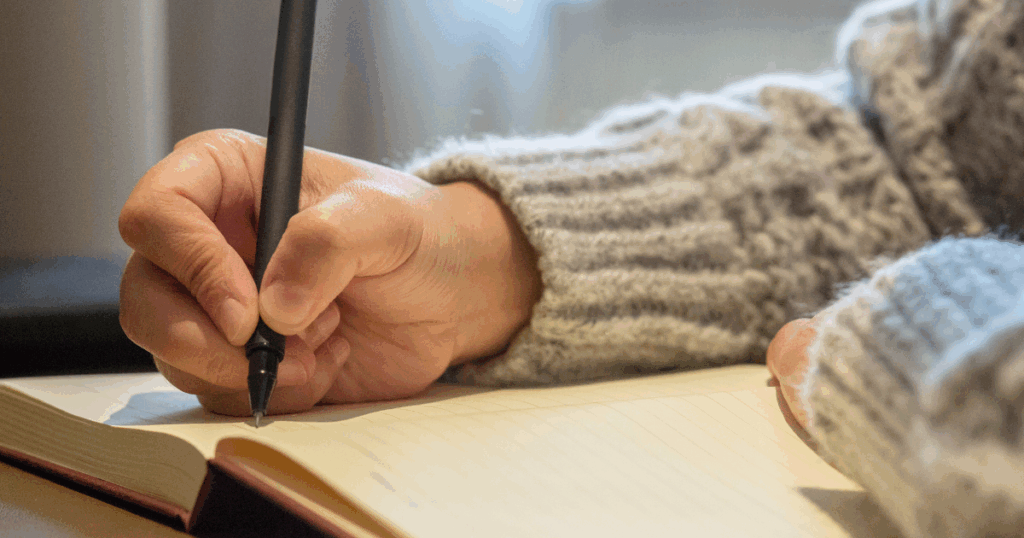
ディクテーションは「聞こえた音をそのまま書き取る」というシンプルな学習法ですが、やり方を間違えると効果が半減してしまいます。
特に初心者は、最初から長い文章に挑戦したり、漢字ばかりに頼ってしまうと挫折しやすくなります。
ここでは、無理なく続けられて効果を実感できる5つの手順を紹介します。
- 手順(1)短い音声を選ぶ手順
- 手順(2)聞こえたままピンインと声調で書き取る
- 手順(3)原文と答え合わせをする
- 手順(4)ピンインを見ながら再度聞く
- 手順(5)仕上げにシャドーイングにつなげる
手順(1)短い音声を選ぶ
はじめからいきなりニュース番組や1分以上の長い会話をディクテーションしようとすると、なかなか書ききれないので、5〜10秒程度の短いフレーズから始めましょう。
例えば、自己紹介の1文「我是日本人」や、簡単な会話のやり取り「你喜欢喝咖啡吗?」など、ワンセンテンス単位の音声から始めると無理がありません。
聞く回数は3回を目安にし、多くても5回までに留めます。
- 1回目:大まかに書き取る
- 2回目:細かい部分を補う
- 3回目:全文を完成させる
このように段階を踏むことで「できた!」という小さな達成感を積み重ねることができ、それがディクテーションを継続する原動力になります。
手順(2)聞こえたままピンインと声調で書き取る
日本人学習者は漢字に慣れているので、最初から漢字で書き取ってしまう人が多いですが、これだと「音を正しく聞き取る」練習になりにくくなります。
中国語では発音が違えば漢字が同じでも意味が変わるため、まずはピンインと声調で正確に書き取ることを優先しましょう。
例えば「画」と「花」はどちらも漢字としてはすぐに書けますが、ディクテーションで大切なのは、「huà」と「huā」の違いを聞き分けられるかどうかです。
このとき、耳で聞いた音をそのまま 「huà」「huā」もしくは「hua4」「hua1」 と書き分けることで、自分がどこまで区別できているかを客観的に確認できます。
日本人にとっては「意味の分かる漢字を書く」のではなく、ピンインと声調にこだわって書き取ることが、音を正しく認識する力を育てるために重要です。
手順(3)原文と答え合わせをする
書き取った後は必ずスクリプトと照らし合わせて、どこが違うかをチェックします。
同時に漢字と日本語の意味も確認しましょう。
ここで重要なのは正解率ではなく、間違えた理由を分析することです。
- 知らない単語だった → 語彙不足なので復習が必要
- 知っているはずなのに聞き取れなかった → 発音の聞き分けが弱い
- 単語も発音も分かっているのに追いつけなかった → スピード処理に課題がある
例:
⭕️ wǒ qù chī fàn(我去吃饭/私はご飯を食べに行く)
❌ wǒ qù qī fàn(七饭※実際には不自然な言い方)
→ chī と qī の区別に弱い
「どの音を間違えたか」「なぜ間違えたのか」を知り、そこを重点的に復習しましょう。
手順(4)ピンインを見ながら再度聞く
答え合わせと原因分析まで終わったら、次はスクリプトを見ながら再度聞きます。
ポイントは、ディクテーションでつまずいた部分を意識して耳を慣らすことです。
例:
- 聞こえない音
- 区別がつかない音
- 知らない単語
ディクテーションは1回やって終わりではなく、繰り返し復習することで効果を発揮します。
正しいピンインを目で確認しながら何度も聞くことで、中国語特有の音のパターンが少しずつ脳に定着し、次のディクテーションやリスニング練習のときに「聞こえる!」という実感につながります。
手順(5)仕上げにシャドーイングにつなげる
日本人学習者の多くは、リスニングよりも「声を出す」機会が圧倒的に少ない傾向があります。
そのため、ディクテーションで弱点が見えた後は、声に出す練習(=シャドーイング) を組み合わせると効果UPです。
このとき、ただ発音するだけでなく、自分の声を録音して聞き返すとさらに効果が増します。
日本語の音に引っ張られている部分や声調の崩れが、自分の耳で確認できるからです。
ディクテーションで 「聞いて理解する力」 を鍛え、シャドーイングで 「口に出して使う力」 を定着させる。
この2ステップを意識することで、リスニングとスピーキングを同時に強化できます。
中国語ディクテーションの注意点


中国語ディクテーションは効果的な学習法ですが、完璧な万能法ではありません。
取り組むうえでのデメリットや注意点も知っておかないと、途中で「思ったほど効果がない」と感じて挫折してしまうこともあります。
ここでは、始める前に知っておきたい3つの注意点を紹介します。
- 注意点(1)慣れるまでに時間がかかる
- 注意点(2)正しいやり方を知らないと効果が薄い
- 注意点(3)継続には工夫が必要
これらを理解したうえで始めれば、無理なく継続でき、効果を実感しやすくなります。
注意点(1)ディクテーションは時間がかかる学習法である
ディクテーションは音声を聞き取るだけでなく、実際に書き取る作業を伴うため、どうしても時間がかかります。
例えば30秒の音声でも、何度も聞き直したり、間違えた部分を確認したりするうちに数十分かかることも珍しくありません。
忙しい学習者にとっては負担に感じてしまいますよね。
解決法:「1日1文だけ」「10分だけ」と割り切り、短いフレーズで取り組むようにしましょう。限られた時間でも積み重ねれば十分に効果があります。
注意点(2)正しいやり方を知らないと効果が薄い
ただ音声を聞きながら何となく聞こえた漢字を書き取るだけでは、あまり効果は期待できません。
ピンインと声調を意識して書き取る、答え合わせで間違えた理由を分析する、そして復習、シャドーイングといった正しい手順を踏むことで初めて成果につながります。
やり方を理解せずに自己流で続けると「時間をかけたのに上達しない」と感じてしまうことがあります。
解決法:学習の流れを「ピンインと声調を聞き取る→答え合わせ→復習→シャドーイング」と固定して、毎回同じ手順で取り組みましょう。
注意点(3)継続には工夫が必要
ディクテーションは音声教材と紙とペンを用意してから始めなければならないので、どうしても「よし!はじめよう!」というまでにちょっと腰が重くなってしまいます。
また、集中力を必要とする練習なので、どうしても疲れやすく、続けにくい面があります。
解決法:勉強を「特別なこと」にせず、日々のルーティンに組み込むのが効果的です。例えば「朝活の10分」など、毎日決まったタイミングで机にノートを広げる習慣を作りましょう。短い時間でも繰り返すことで、自然に続けられるようになります。
レベル別おすすめ教材とアプリ・サイト


ディクテーションを効果的に続けるには、自分のレベルに合った教材を選ぶことが大切です。
難しすぎる素材を使うと挫折しやすく、逆に簡単すぎると練習効果が薄れてしまいます。
ここでは、初心者から上級者まで段階に応じて取り入れやすい教材やアプリを紹介します。
- 初心者向け:基礎教材と無料アプリ
- 中級者向け:リスニング教材、HSK対策教材の活用
- 上級者向け:ニュース・映画・ドラマ・音楽活用術
初心者向け:基礎教材と無料アプリ
中国語のディクテーションは、リスニング力だけでなく、発音や声調、語彙力、文法力などを総合的に鍛えるのに役立ちます。
特に初心者は、次の条件を満たす教材を選ぶと安心です。
・音声がクリアで、自然な発音であること
・文章の長さが短く、難しすぎないこと
・スクリプト(原文)と日本語訳がついていること
・ピンインや声調も併記されていること
これらを満たす教材の中から、おすすめを3種類紹介します。
おすすめ① 音読に特化した教材
- 『はじめよう中国語音読 初級編』(李 軼倫 著)
→ 自然な文章が豊富に掲載されています。ネイティブらしい発音や音の繋がりを意識して練習するのに適しています。
→ 音声はSpotifyなどポッドキャストでも配信されています。
おすすめ② 検定試験対策の教材
- HSK1級・2級の公式問題集
→ 基本的な単語と文法で構成されているため、総合的に学習しながらディクテーション練習もできます。
おすすめ③ 無料スマホアプリ
- SuperChinese(スーパー・チャイニーズ)
→ ゲーム感覚で楽しく学べるアプリで、ピンインや声調の聞き分けに特化したトレーニングもあります。手軽に無理なく続けられるのが魅力です。
ご自身のレベルや学習スタイルに合わせて、使いやすい教材を選んでみましょう。
中級者向け:リスニング教材、HSK対策教材の活用
ディクテーションに慣れてきた中級者には、日常会話や身近なニュースなど多様なトピックを扱う教材がおすすめです。
以下にいくつかピックアップしました。
おすすめ① リスニングに特化した教材
- 『耳が喜ぶ中国語 リスニング体得トレーニング』
→ ニュースや社会問題など、幅広いテーマの文章が収録されています。ネイティブの自然なスピードで話されているので、聞き取り訓練に効果的です。 - 『聴読中国語』
→ 短文の会話集ではなく、200〜400字程度の文章を読みながら単語や文脈を覚える構成です。ディクテーションを通じて、長文を素早く理解する力が身につきます。
おすすめ② HSKの対策問題集
- HSK3級・4級の公式問題集
→ HSK3~4級は日常会話の表現が豊富です。実際の試験は選択問題ですが、ディクテーションすることで、より深く聞き取る力を養えます。
上級者向け:ニュース・映画・ドラマ・音楽活用術
上級者になると、ディクテーションは単語や文法を聞き取る練習から、話者の意図や背景、感情さらには専門的な語彙までを読み解くトレーニングへと変わります。
以下に、上級者におすすめの教材をピックアップします。
おすすめ① ニュースやドキュメンタリー
- CCTV(中国中央電視台)のニュースや番組
→ 政治、経済、社会問題など、幅広いテーマを扱っており、ネイティブの速い話し方や専門用語に触れることができます。 - CCTV记录のドキュメンタリー
→ 話し手の感情や口調、アクセントのニュアンスまで聞き取る練習になります。 - 最新日本国际新闻 | 中国語簡体字ニュース | NHK WORLD-JAPAN News
→ 日本語のニュースを中国語で聞くことができます。内容が日本語で先にわかっているため、難易度が高すぎず、聞き取りに集中しやすいです。
※アプリもあります
おすすめ② ドラマ・映画・音楽の活用
- 好きな作品を選ぶ
→ 好きな俳優のセリフや歌詞のワンフレーズを聞いて書きとってみましょう。感情のこもった言い回しや、情緒豊かな表現を習得できます。
まとめ


中国語のディクテーションは、聞き流し学習では気づけない弱点を見える可し、リスニング力を中心に総合的な中国語力を伸ばす学習法です。
今回紹介したように、短い音声から始めてピンインで書き取り、答え合わせと復習を経てシャドーイングへとつなげる流れを習慣化すれば、確実に成果が表れます。
もちろん、ディクテーションは時間がかかり、集中力も必要です。
だからこそ「毎日10分」「1日1文」といった小さなステップで続けることが成功の秘訣です。
まずは今日、手元にある教材やアプリで「1文だけ」ディクテーションに挑戦してみましょう。
それが継続と上達への第一歩になります。



毎日中国語公式LINEの中国語学習情報もあわせてご覧くださいね!