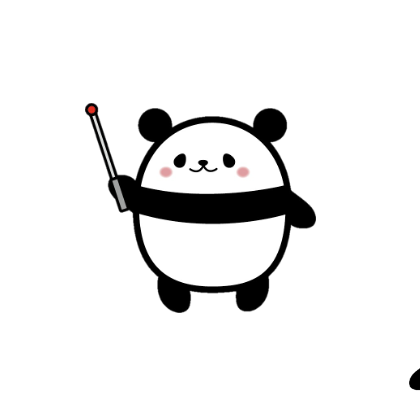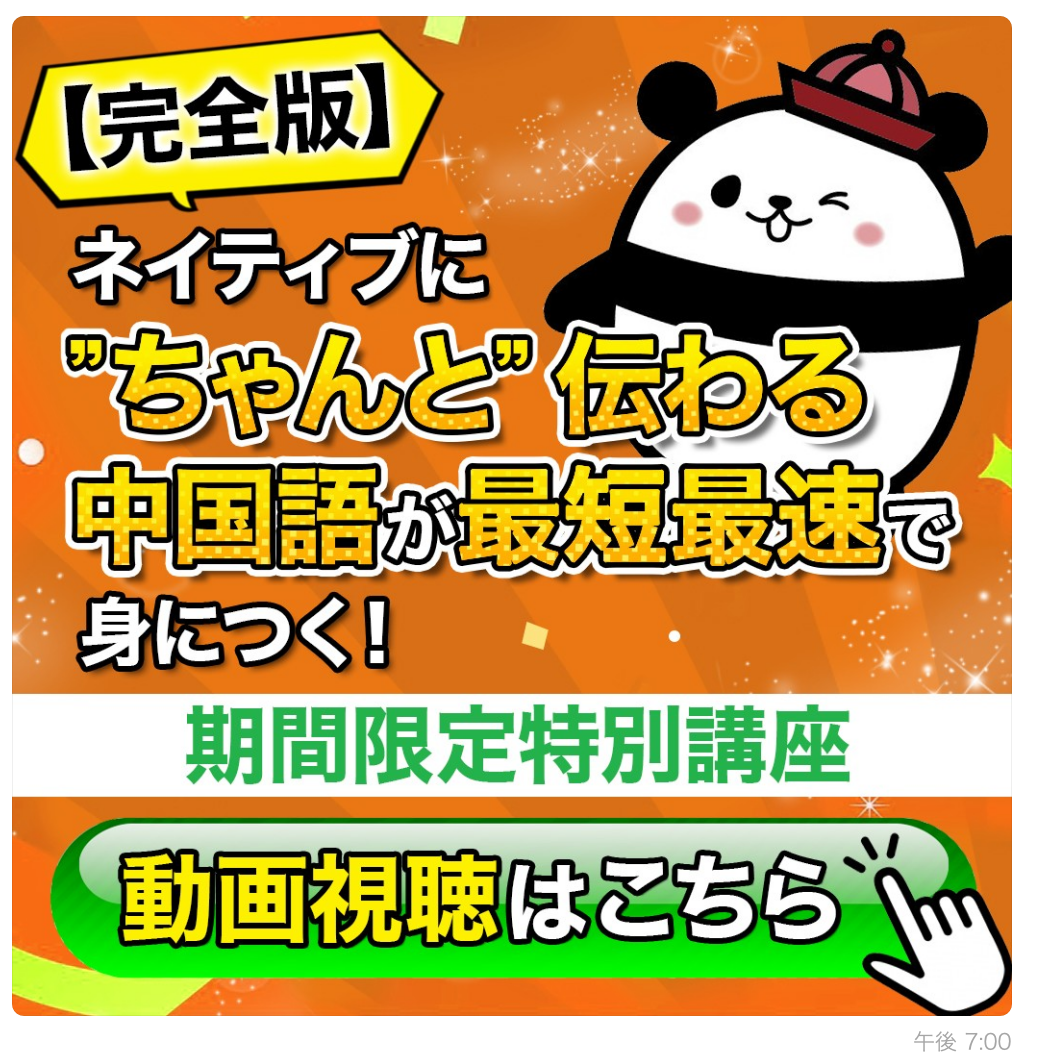
中国語の常用漢字数は?日本人向け学習範囲と覚え方を解説
この記事でわかること
- 中国政府が定めた最も基礎となる常用漢字は3,500字
- 日本人は日本語と形や意味が異なる漢字に注意
- 漢字の形だけでなく、「単語」で発音と使い方を一緒に覚えよう!

中国語の常用漢字数は何字ですか?
中国語は全てが漢字なので、次から次へと知らない漢字が出てきて途方に暮れてしまいますよね。
中国政府が定める公式基準では、基本的な教育や文化を満たせると定められている漢字が3,500字です。



日本人はもともと漢字の知識があるため、すでに知っている漢字も多く含まれています。
また、旅行や簡単な日常会話が目標の場合は、もっと限られた範囲の漢字数でも交流が可能です。
この記事では、中国政府が公布した基準に基づく漢字数、日本語の常用漢字との比較、中国語の漢字を学習する際のポイントをお伝えします。
日本人ならではの知識を活かしつつ、効率的に覚えていきましょう!
目次
中国語の常用漢字数と分類


まずこの章では、中国語の常用漢字の基準である『通用規範漢字表』を元に、学習の目標となる漢字数を、段階的にわかりやすく解説します。
- 分類(1)学習の最重要目標:「一級字表」の3,500字
- 分類(2)より専門的な領域へ:「二級字表」の3,000字
- 分類(3)専門家レベル:「三級字表」の1,605字
分類(1)学習の最重要目標:「一級字表」の3,500字
現在の中国語学習における最初の大きな目標は、中国政府が2013年に定めた『通用規範漢字表』の「一級字表」に含まれる3,500字です。
これは、中国の基礎教育や社会生活で必須とされる、いわば「現代中国語の核」となる文字群です。
この3,500字を習得すれば、一般的な文章の大半をカバーできるとされています。
日本語の常用漢字(2,136字)より数は多いですが、数字や身の回りの物など基本中の基本から、社会的な語彙まで幅広く含まれています。
中国語学習は、この3,500字を目標に学習を進めましょう。
分類(2)より専門的な領域へ:「二級字表」の3,000字
一級字表の3,500字をマスターした学習者が、さらに高度なレベルを目指す際に目標となるのが「二級字表」の3,000字です。
これらの漢字は、一級字表の次に使用頻度が高い文字群で、より専門的な書籍や学術的な文章を読みこなすために必要となります。
例えば、人名や特定の分野で使われる「皙(色が白い)」や「慄(おののく)」といった、表現の幅を広げる文字が含まれています。
一般の学習者が最初から覚える必要はありませんが、中国語を深く学びたい、専門分野で活用したいという場合の次のステップとして位置づけられています。
分類(3)専門家レベル:「三級字表」の1,605字
『通用規範漢字表』の最終レベルが「三級字表」の1,605字です。
ここには、人名、地名、科学技術用語といった非常に専門的な分野で使われる漢字や、歴史的な文脈で価値を持つ文字などが含まれています。
例えば、「仝(「同」の異体字)」や「邨(「村」の異体字)」など、一般の文章ではほとんど見かけない文字がこの分類に入ります。
このレベルは研究者や特定分野の専門家向けの領域であり、ほとんどの学習者にとっては学習の直接的な目標にはなりません。
これら全てを合計すると、公式な規範漢字は8,105字となります。
日本語の常用漢字との比較
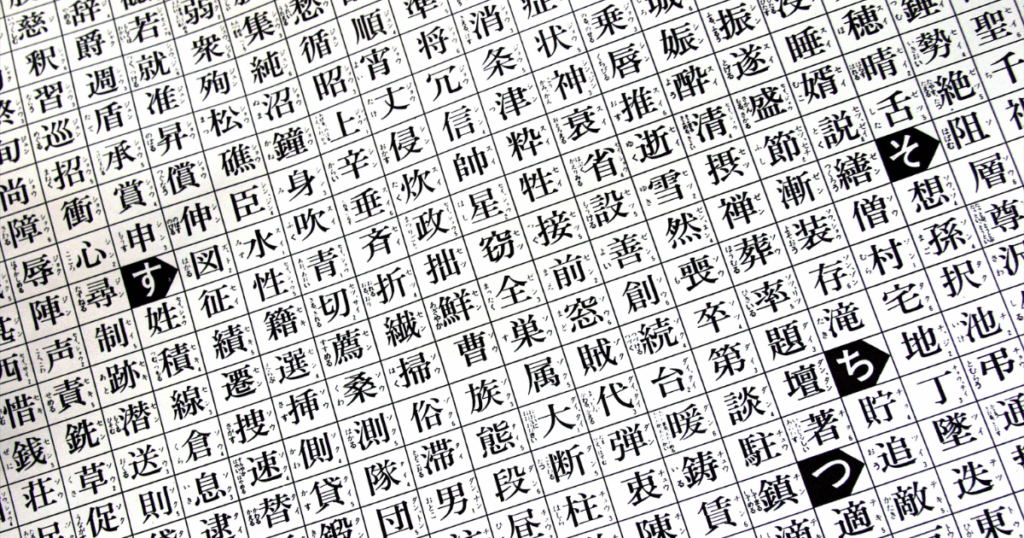
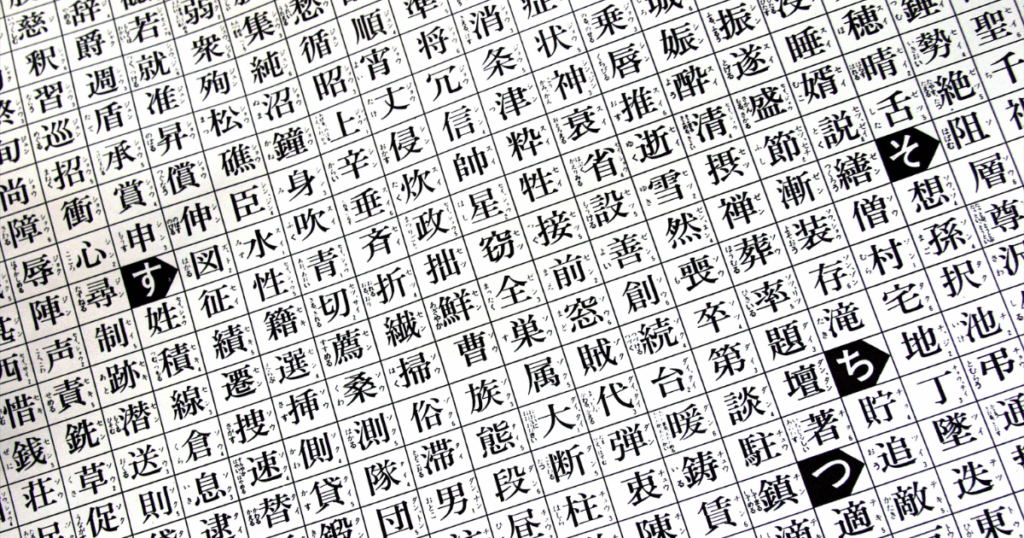
この章では、中国語の常用漢字と日本語の常用漢字を比較します。



日本人にとっては日本語の漢字知識を活かしたいですよね。
学習の際に有利な点と注意すべき点を見ていきましょう。
- 比較(1)覚えるべき漢字数:3,500字 vs 2,136字
- 比較(2)字形の共通点と相違点
- 比較(3)意味が同じ漢字と異なる漢字
- 比較(4)日本人が学習しやすい理由と注意点
比較(1)覚えるべき漢字数:3,500字 vs 2,136字
まず、学習のゴールとなる漢字数を比較してみましょう。
中国語の基本となるのは『通用規範漢字表』一級字表の3,500字、一方、日本の常用漢字は2,136字です。
数字だけ見ると中国語の方が多いですが、日本人学習者には大きなアドバンテージがあります。
両言語で使われる漢字には多くの共通点があるため、全くのゼロから覚えるわけではないからです。
日本の語彙の多くは漢字(漢語)を使った言葉で、私たちはすでに膨大な漢字の知識を持っています。
この「知っている」という土台があるため、アメリカやヨーロッパなど他言語話者と比べて圧倒的に有利なスタートを切れるのです。
比較(2)字形の共通点と相違点
中国大陸で使われる「簡体字」と日本の漢字(新字体)は、形が全く同じもの、少しだけ違うもの、全く違うものがあります。
例えば、「学校」「大学生」は同じですが、「図書館」は中国語で「图书馆」となり、字が簡略化されています。
こうした違いが生まれたのは、1950年代に中国で行われた文字改革が背景にあります。
一方で、日本でも戦後に漢字の簡略化が行われました。
両国がそれぞれ独自に簡略化を進めた結果、同じ簡略化をした字もあれば、「發→発(日本)/发(簡体字)」のように異なる形になった字も生まれました。
こうした字形の違いは、パターンとして覚えていくと効率的です。
比較(3)意味が同じ漢字と異なる漢字
日本人学習者が注意したいのは、同じ漢字もしくは似ている字形なのに意味が全く違う単語です。
意味が同じ「学校」「電話(电话)」「音楽(音乐)」などはラッキーですが、うっかり日本語の感覚で使うと大きな誤解を招く単語も少なくありません。
例えば、中国語の「手纸(shǒuzhǐ)」はトイレットペーパーを指すことがあります。
また、「爱人(àiren)」は日本語の「不倫相手」ではなく、公式な場で使われる「配偶者(夫または妻)」のことです。
他にも、「老婆(lǎopó)」は「妻」、「娘(niáng)」は「お母さん」を指す場合があるなど、知らずに使うと驚かれてしまう単語があります。
このような意味が全く異なってしまう漢字は数が限られているので、リストアップして集中的に覚えるのが効果的です。
比較(4)日本人が学習しやすい理由と注意点
日本人にとって最大の強みは、漢字の「形」と「意味」の概念をすでに理解していることです。
これが大きなアドバンテージであることは間違いありません。
しかし、そのアドバンテージが「知っているつもり」という油断につながることもあります。
特に注意が必要なのは発音です。
中国語には「声調(四声)」があり、同じ「ma」という音でも声の高さによって「母・麻・馬・罵」のように全く意味が変わります。
漢字の知識を活かしつつも、発音は全く新しい言語としてゼロから学ぶ、という意識を持つことが、上達への一番の近道です。
簡体字と繁体字の違いと選び方


中国語の漢字には、「簡体字(かんたいじ)」と「繁体字(はんたいじ)」という2つの表記体系があります。
どちらも「中国語」ですが、使われる地域と目的が少し違います。
この章では、それぞれの字体の特徴と、学ぶ時の選択基準を解説します。
- 漢字(1)簡体字とは?
- 漢字(2)繁体字とは?
- 漢字(3)簡体字と繁体字どちらを学ぶか
漢字(1)簡体字とは?
簡体字(jiǎntǐzì)は、中国大陸(中国本土)で使われている文字体系です。
1950年代の「文字改革」によって、複雑な漢字の形がよりシンプルに統一されました。
画数を減らして覚えやすくすることが目的で、約2,000字以上が簡略化されています。
現在、中国本土・シンガポール・マレーシアではこの簡体字が公用です。
新聞、書籍、公式文書、SNSなど、あらゆる媒体で簡体字が使われています。
また、中国語の検定試験であるHSKや中検もすべて簡体字で実施されています。
例:
| 簡体字 | 日本 |
| 爱 | 愛 |
| 车 | 車 |
| 马 | 馬 |
| 读 | 読 |
| 药 | 薬 |
| 乐 | 楽 |
漢字(2)繁体字とは?
繁体字(fántǐzì)は、簡体字が生まれる前から使われていた伝統的な漢字の形です。
形が複雑で画数が多いですが、そのぶん意味の成り立ちが分かりやすく、文化的・美的な価値が高い文字体系です。
現在、台湾・香港・マカオでは繁体字が正式な表記として使われています。
台湾の教育や出版もすべて繁体字が基本です。
※台湾の中国語能力試験 TOCFL(華語文能力測驗)は、簡体字で受験することも可能です。
例:
| 繁体字 | 日本 |
| 讀 | 読 |
| 藥 | 薬 |
| 樂 | 楽 |
| 學 | 学 |
| 國 | 国 |
| 體 | 体 |
漢字(3)簡体字と繁体字どちらを学ぶか
特にこだわりがなければ、まずは簡体字から学ぶのがおすすめです。
世界標準の中国語能力試験であるHSKは簡体字で実施されますし、市販のテキストや学習アプリのほとんどが簡体字を基本としています。
画数が少なく覚える負担が少ないというメリットもあります。
現代の中国のSNSやエンタメコンテンツもほとんどが簡体字なので、学習してすぐに使える場面が多いのも魅力です。
また、簡体字で中国語の基礎を固めれば、繁体字はある程度類推して読めるようになります。
簡体字と繁体字は、日本語のひらがなとカタカナのように、どちらか一方を学べばもう一方の理解も早まる関係にあります。
まずは教材が豊富な簡体字でスタートし、自信がついたら興味のある地域の繁体字に挑戦してみるのが、挫折しにくいおすすめの進め方です
学習目的別に必要な語彙数
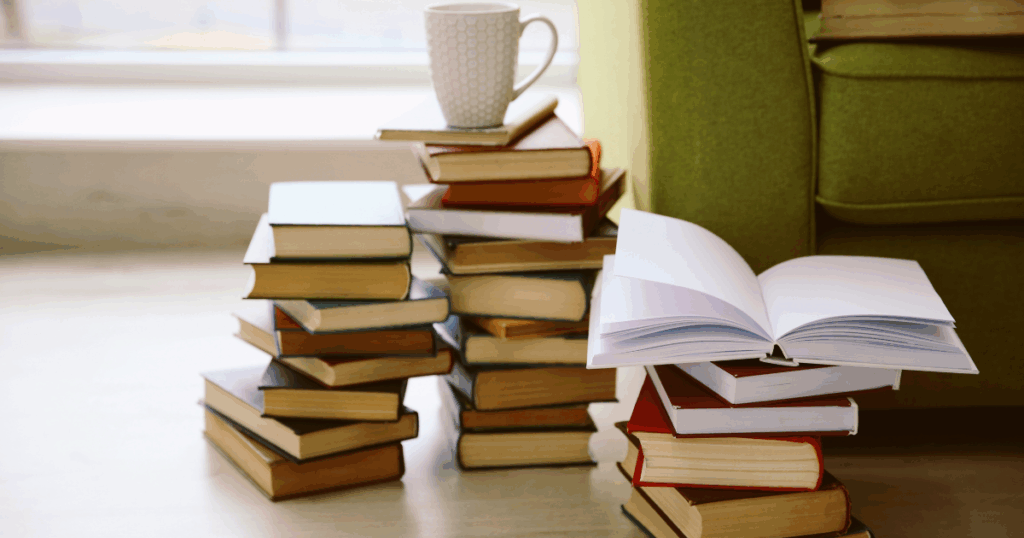
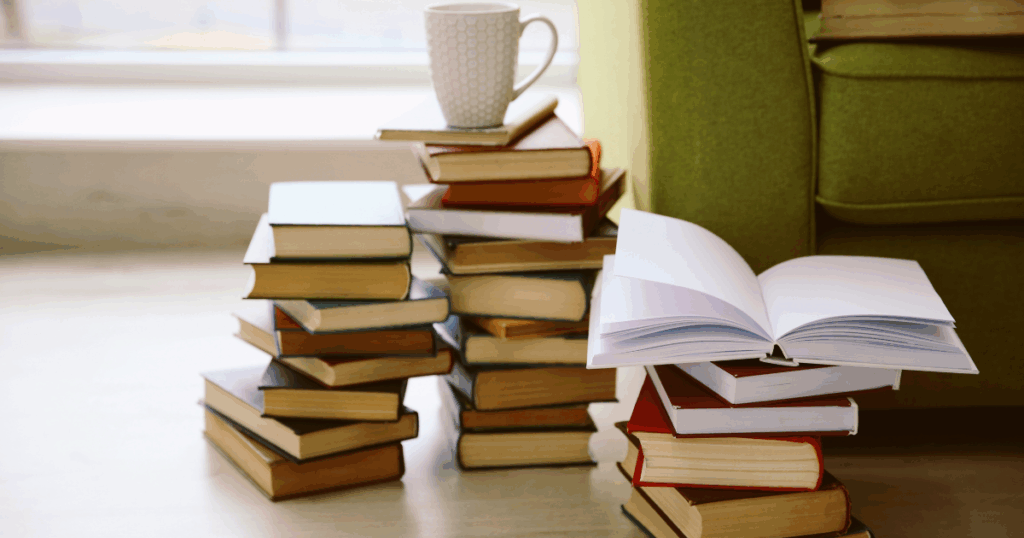
「3,500字が目標なのはわかったけど、自分の目的ならどこまでやればいいの?」と感じる方も多いでしょう。
この章では、中国語の目標別に必要な語彙数を、中国語の試験であるHSKを指標にして解説します。
- 目安(1)旅行・日常会話ならHSK3級(600語)が目標
- 目安(2)ビジネス・大学留学ならHSK4級(1,200語)以上を目指そう
- 目安(3)新聞・小説読解はHSK5級・6級レベル
- 注意点:将来の基準「新HSK(3.0)」について
目安(1)旅行・日常会話ならHSK3級(600語)が目標
旅行先で簡単なコミュニケーションを取りたい、日常的な会話を楽しみたい、という目的なら、HSK3級で求められる600語の習得が最初の目標になります。
このレベルに達すると、「这个多少钱?(これいくらですか?)」「我要去这里(ここに行きたいです)」といった基本的な旅行会話はもちろん、簡単な自己紹介や趣味について話すことができるようになります。
まずはHSK3級と同等のレベルを目指すことで、中国語を使う楽しさを実感できるでしょう。
目安(2)ビジネス・大学留学ならHSK4級(1,200語)以上を目指そう
ビジネスで中国語を使いたい人や、中国の大学への留学を考えている人は、まずHSK4級(約1,200語)を目標にするのがおすすめです。
HSK4級は履歴書にも書けるレベルとして広く認知されていて、企業や大学では「基礎力の証明」として評価されることが多いです。
ただし実際、HSK4級に合格しても、ネイティブの会話をスムーズに聞き取るのはまだ難しいと感じる人が多いのも現状です。
ここからは、実際に話す・聞く練習を重ねて、少しずつ「使える中国語」にしていく段階です
さらに自然な会話力や専門的な中国語を使いたい場合は、HSK5級(約2,500語)やHSK6級(約5,000語以上)を目指してステップアップしていきましょう。
目安(3)新聞・小説読解はHSK5級・6級レベル
中国の新聞や雑誌を読んだり、映画やドラマを字幕で楽しんだりするには、HSK5級(2,500語)以上の語彙力が必要になります。
さらに、専門書や小説を深く味わうには、HSK6級(5,000語以上)が目標となります。
5,000語に到達すると、書き言葉や話し言葉を問わず、中国語の情報をスムーズに理解し、自分の意見を流暢に表現できるようになります。
これは、先に述べた『通用規範漢字表』の一級字表3,500字の習得とほぼ重なるレベル感です。
注意点:将来の基準「新HSK(3.0)」について
現在、HSKは将来的に「3段階9レベル」構成(通称HSK3.0)へと変更される移行期間にあります。
この新基準は2021年に発表され、すでに上級レベル(7〜9級)の試験は2022年から開始されています。
新基準では全ての級で求められる語彙数や漢字数が大幅に増えます。
例えば、新基準の3級では2,245語で、現行の3級(600語)の3倍以上になります。
現時点(2025年10月)で1〜6級の試験がいつ新基準に移行するかは未定ですが、これから本格的に学習する方は、将来的に求められるレベルが上がることを念頭に置いておくと良いでしょう。
日本人向け効率的な漢字学習法
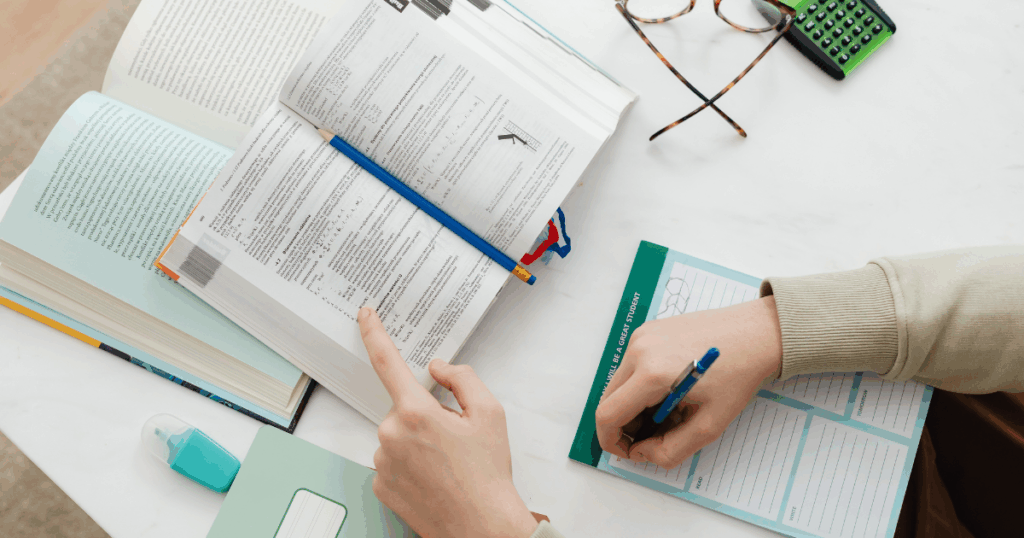
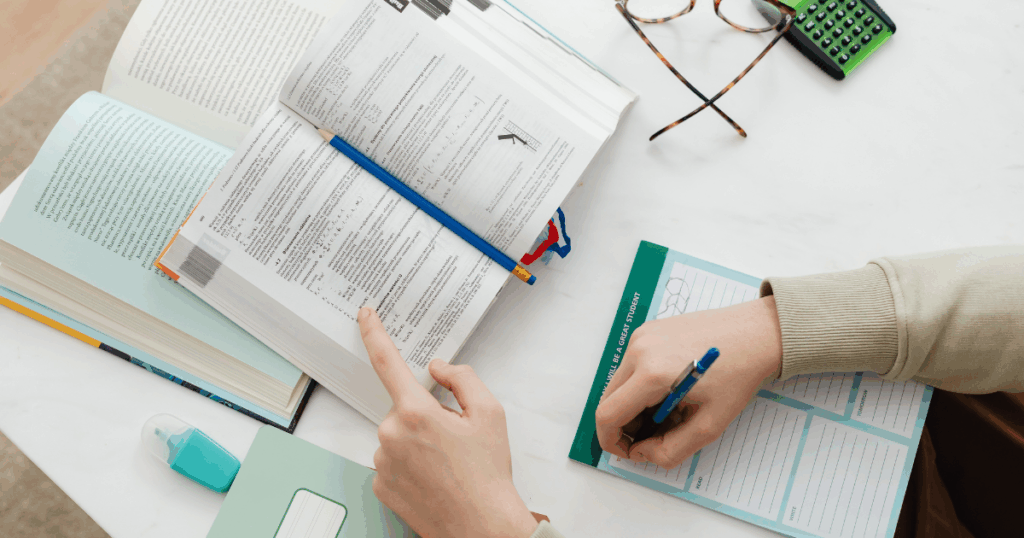
それでは実際に、中国語の漢字を覚えていきましょう。
この章では、日本人学習者向けに、効率よく中国語の漢字を学習する方法を紹介します。
- 方法(1)HSKに沿って「単語」で覚える
- 方法(2)ピンインと漢字を同時に習得
- 方法(3)部首・構造を利用した体系的学習
方法(1)HSKに沿って「単語」で覚える
中国語の漢字は、1文字だけで覚えるよりも「単語」としてセットで覚えるほうがずっと効果的です。
なぜなら、中国語では多くの言葉が文字の組み合わせで使われるからです。
例:
- 「学(学ぶ)」+「习(習う)」= 学习(勉強する)
- 「开(開く)」+「会(会議)」= 开会(会議を開く)
このように、単語の中で使われることで意味が具体的に理解でき、記憶に残りやすくなります。
また、中国語検定であるHSK(中文水平考试)は、学習の進め方にとても役立つ道しるべになります。
HSKは1級から6級まであり、級が上がるごとに語彙の範囲と漢字のレベルも上がっていきます。
| 級 | 目安の語彙数 | 学習レベル |
| HSK1級 | 約150語 | あいさつ 基礎単語 |
| HSK2級 | 約300語 | 簡単な日常表現 |
| HSK3級 | 約600語 | 旅行 日常会話レベル |
| HSK4級 | 約1,200語 | ビジネス初級 留学準備 |
| HSK5級 | 約2,500語 | 新聞 ドラマ理解 |
| HSK6級 | 約5,000語 | 高度な文章 議論レベル |
1級から順に単語を学べば、自然と使用頻度の高い漢字から優先的に身につけることができます。
例文を読んで、どんな場面で使われるのかを確認し、実際の会話や読解で活かせる知識にしていきましょう。
方法(2)ピンインと漢字を同時に習得
中国語の漢字学習で絶対に欠かせないのが、発音表記である「ピンイン」とセットで覚えることです。
日本人は漢字の形と意味から意味を推測しがちですが、中国語はあくまで別の言語です。
漢字の形だけを覚えても、話すことも聞くこともできません。
新しい漢字を学ぶ際は、必ず「形・意味・音(ピンイン)」をワンセットでインプットする習慣をつけましょう。
音声付きの教材を使い、自分の口で発音しながら覚えることで、記憶の定着率が高まるだけでなく、実践的なコミュニケーション能力が身につきます。
方法(3)部首・構造を利用した体系的学習
中国語の漢字はパーツ(部首や構造)で理解するようにすると、学習効率がぐっと上がります。
多くの漢字は、実は以下のように2つの要素でできています。
- 意味を表す部分(形声文字の“形”)
- 音(発音)を表す部分(形声文字の“声”)
例:
- 氵(さんずい)→ 水に関係する漢字(河、海、洗、湖)
- 亻(にんべん)→ 人に関係する漢字(你、他、住、作)
- 扌(てへん)→ 手の動作に関する漢字(打、拉、推、拿)
- 艹(くさかんむり)→ 植物に関する漢字(花、茶、草、菜)
このように、部首には共通の意味グループがあるため、知らない漢字が出てきても「なんとなく意味を推測できる」ようになります。
また、同じ“音符”を持つ漢字もセットで覚えると、発音の予測もできるようになります。
例:
「青」→ 清(qīng)、情(qíng)、晴(qíng)、请(qǐng)など
→ 発音が似ていて、意味も「明るい・澄む」と関連しています。
こうして漢字の構造を意識して体系的に学ぶことで、記憶がネットワークのようにつながり、1文字ずつバラバラに覚えるよりもずっと忘れにくくなります。
まとめ


中国語の常用漢字は、教育部が定めた3,500字(一级字表)が基本です。
日本語の常用漢字(2,136字)よりは多いですが、日本語と共通する字も多く、日本人は3,500字全てを今から覚えなければならないわけではありません。
中国語の漢字を覚える際は、日本語と字体や意味の異なる漢字に特に注意し、よく使われるものから順に覚えていきましょう。
HSKなどの試験を目安に、漢字単体ではなく、2文字3文字の単語として読み方(発音)や使い方を同時に学ぶと、覚えやすいだけでなく実践でも使える知識になります。
毎日少しずつでも、継続した学習が中国語習得への近道です。
毎日中国語公式LINEで配信している中国語学習情報もあわせてご覧くださいね。