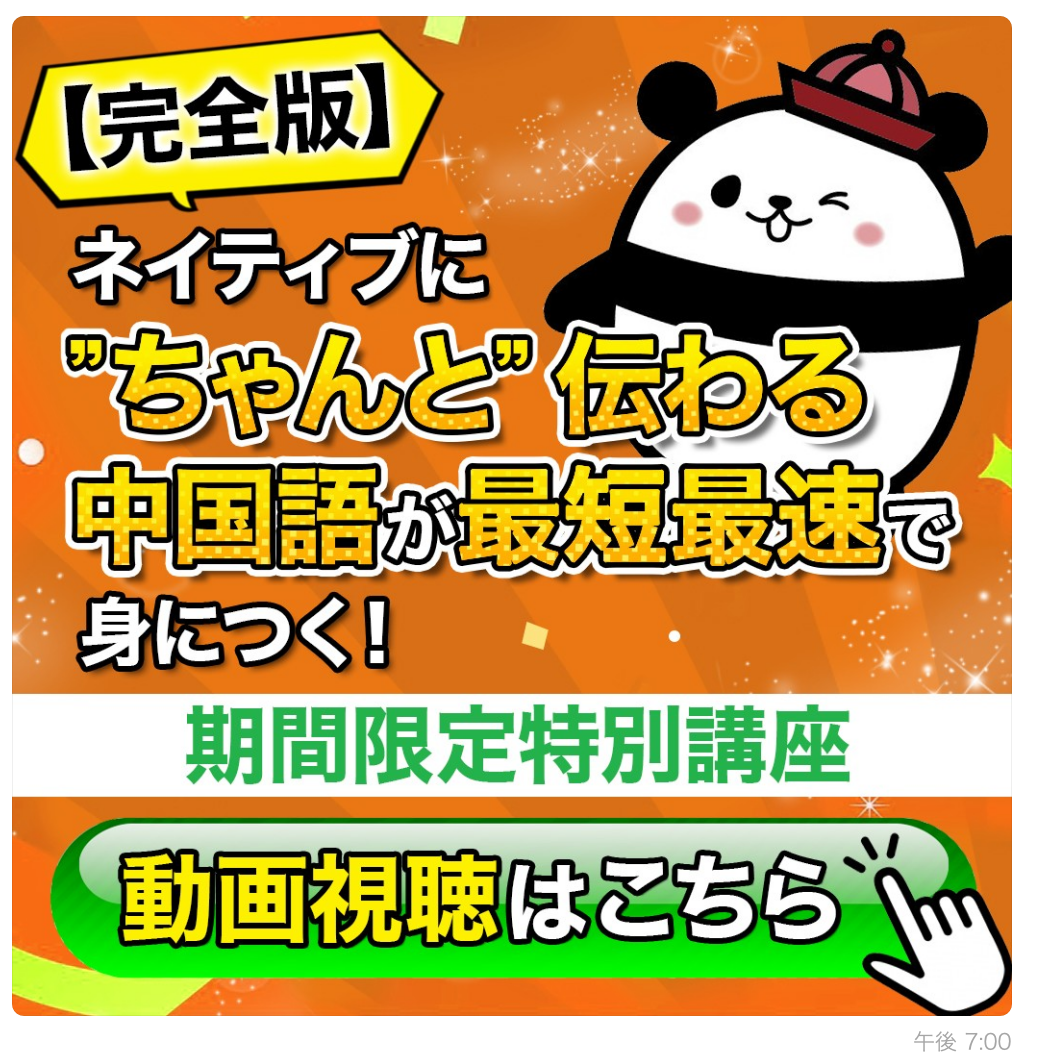
\ 期間限定動画無料配布中 /
参考書でたくさん勉強したのに、いざ話すとなると中国語がサッパリ出てこなくて何も話せない…。
そのお悩み、決してあなただけではありません。
本記事では、多くの学習者がつまずく「中国語を話せない」原因と今すぐできる実践方法を紹介します。

中国人のお友達との会話を楽しみましょう!




「中国語を勉強しているのに、なぜか話せない…」——そんなもどかしさを感じたことはありませんか?
HSKの点数は取れるし、単語や文法も覚えているのに、いざ会話になると口から言葉が出てこない。これは多くの学習者が経験する悩みです。
実は、中国語が話せないのにはいくつか共通する原因があります。
ここでは特によく見られる4つを紹介しますので、「あ、これ自分かも」と思いながら読んでみてくださいね。
原因(1)インプット中心でアウトプットが不足している
原因(2)発音やリスニングに自信がなく話すのが怖い
原因(3)完璧主義や間違える不安で発話を避けてしまう
原因(4)日本語で考えてから中国語に訳している
多くの学習者が最初に直面するのが、知識量と会話能力のギャップです。
単語帳やアプリで何百という単語を覚え、HSKの文法問題を解けるようになったとしても、それはあくまで知識を脳にインプットした段階に過ぎません。
実は、その知識を瞬時に引き出し、口を使って音声にするアウトプットの作業は、全く別のスキルなのです。
サッカーのルールを完璧に理解していても、実際にボールを蹴って練習しなければ試合で活躍できないのと同じで、中国語も実際に口に出す「口の筋トレ」がなければ、会話という試合では戦えません。
特に、試験勉強が中心になると、どうしても読む・聞くといったインプットに偏りがちです。
例えば、中国人の同僚との雑談で「週末は何をしていたの?」と聞かれた時、知っているはずの単語や表現が全く思い浮かばず、頭が真っ白になってしまう。



これは、あなたの知識が足りないのではなく、アウトプットの練習量が不足している典型的なサインです。
まずはこの事実を認識し、話すための練習へと意識を切り替えることが、上達への最初のそして最も重要な一歩となります。
中国語を話す上で、心理的なブレーキになりがちなのが「発音」への自信のなさです。
特に、中国語特有の声調(四声)や日本語にない発音は多くの日本人学習者にとって大きな壁であり、「自分の発音は通じないかもしれない」という不安が、口を開くことをためらわせます。



過去に勇気を出して話してみたものの、「啊?(えっ?)」と何度も聞き返されたりした経験が、一種のトラウマになっている方も少なくありません。
また、相手の言う中国語が聞き取れないと、焦ってしまったり、何度も聞き返すのが申し訳なくなったりして、話すのが怖くなってしまいます。
この恐怖心こそが、あなたの口を重くしている大きな原因なのです。
スマホの音声認識機能などを使えば、誰にも迷惑をかけず安心して何度でも練習できます。
まずは、伝えよう!という気持ちを大切にしましょう。



真面目に勉強を続けてきたあなただからこそ、陥りやすい罠があります。
それは、「正しく完璧な中国語を話さなければならない」という完璧主義です。
一字一句間違わずに、文法的にも非の打ち所がない文章を話そうとするあまり、頭の中で必死に言葉を組み立てているうちに、会話のテンポはあっという間に過ぎ去ってしまいます。
本来コミュニケーションの目的は、テストで100点を取ることではなく、相手に自分の意思を伝えることです。
「間違ったら恥ずかしい」という気持ちは、この本質的な目的を見失わせ、結果的に発言の機会そのものを奪ってしまうのです。
例:同僚との雑談中
「昨日見た映画はとても面白かった」と伝えたい!
↓
頭の中で「ええと、文法は…、発音は…」と推敲
↓
周りの会話は別のテーマに移ってしまう
本当は「昨天!电影!有意思!」と単語を並べるだけでも、気持ちは伝わったかもしれないですよね。
まずは「伝われば満点」という意識に切り替えましょう。
間違いは恥ではなく、あなたの中国語をより良くするための最高の学習機会なのです。
会話中に言葉がスムーズに出てこない最後の大きな原因は、多くの日本人学習者が無意識に行っている「頭の中での翻訳作業」です。
つまり、話したい内容を一度日本語で考え、それを中国語の単語と文法に当てはめてから口に出そうとする癖のことです。
これには、二つの大きな問題点があります。
日本語から中国語への変換にはどうしても時間がかかり、リアルタイムで進行する会話の流れから取り残されてしまいます。
また、日本語と中国語は、語順も表現の習慣も大きく異なります。
日本語の文章をそのまま直訳すると、どこかぎこちない、ネイティブが使わないような表現になってしまいがちです。
この癖から脱却するには、「中国語思考」のトレーニングが有効です。
身の回りの物を見て、日本語を介さず直接「桌子(zhuōzi)」「电脑(diànnǎo)」と考える。
この小さな習慣が、あなたの脳を中国語モードに切り替える第一歩となります。


この章では、多くの学習者が「話せない」ことで経験する3つの具体的な「つまずき」について解説します。



努力しているのに前に進めない感覚は、あなたに才能がないからではありません。
これは、ほとんどの人が通る道であり、その正体を知ることで、乗り越える準備ができます。
つまずき(1)覚えたはずの単語やフレーズが口から出ない
つまずき(2)ネイティブとの会話で聞き返されて自信を失う
つまずき(3)実践の場で沈黙してしまい落ち込む
参考書やアプリで熱心に勉強し、「この単語、知ってる!」「この文法、わかる!」という知識は着実に増えているはず。
それなのに、いざ中国語で話そうとすると、覚えたはずの言葉が喉まで出かかっているのに、どうしても口から出てこない。
やっとの思いで何か言っても、噛み噛みで発音も文法もめちゃくちゃ。
この現象の正体は、脳が情報を「見てわかる状態」で蓄えていることと、それを「自由に使える状態」にすることの間に、大きなギャップがあるからです。
会話は、脳の引き出しから瞬時に適切な言葉を取り出し、文章を組み立てて発声するという、非常に高度なスキルです。
この「引き出して使う」訓練を意識的に行わない限り、知識は脳の中で眠ったままになってしまいます。
これは、あなたが経験している極めて正常な学習段階なのです。



まずはその事実を理解し、自分を責める必要はないと知ることが大切です。



勇気を出して中国語で話しかけたのに、相手の反応は「啊?」
この一言に、心臓が凍りつくような感覚を覚えたことはありませんか。
一度でも「通じなかった」というネガティブな経験は、私たちの自信を根こそぎ奪い、話すことが怖くなってしまいます。
特に、日本人学習者にとって大きなハードルとなる発音が原因で聞き返されると、「やっぱり自分の発音は根本的にダメなんだ」と、すべての努力を否定されたような気持ちに陥りがちです。



もう二度と話したくなって、テキストメッセージばかりになりました
しかし、少し立ち止まって考えてみてください。
言語や文化が違う相手との会話で、聞き返されるのは本当に特別なことでしょうか。
ネイティブ同士の会話でも、周りがうるさかったり相手の声が小さかったりして聞き返すことは日常茶飯事です。
「自分のせいだ」と全てを抱え込むのではなく、まずは大きな声ではっきりと言い直してみましょう。
教室やアプリの中では、ある程度リラックスして言葉を口にできる。
しかし、上海や台湾への出張・旅行、あるいは中国人との会食といったリアルな実践の場になると、急にプレッシャーを感じ、一言も発せずに固まってしまう。



何のために勉強してきたんだろう…



これもまた、多くの学習者が経験する、非常に辛い壁の一つです。
この「思考停止」状態に陥るのには、明確な理由があります。
実際の会話は、予測不能でスピードも速いものです。
その中で、私たちは無意識に「話す内容を考え」「正しい文法を選び」「正確な発音を意識する」という複数のタスクを同時にこなそうとします。
その結果、脳が情報処理の限界を超えてしまい、フリーズしてしまうのです。
例えば、会食の席で周りが楽しそうに中国語で談笑している中、輪に入りたい気持ちは山々なのに、「気の利いたことを言わなきゃ」「下手な中国語で空気を壊したらどうしよう」と考えているうちに、結局相づちを打つだけで終わってしまった。
これは、あなたがコミュニケーションを心から望んでいる証拠であり、実はとても前向きな悩みと言えます。



最初から完璧な会話を目指す必要はありません。
まずは「真的吗?(本当ですか?)」のような短い相づちで輪に入る練習から始めることで、心の壁は少しずつ溶けていきます。


中国語が「話せない」と感じるときこそ、実践的なトレーニングを取り入れるチャンスです。
難しいテクニックは一切ありません。大切なのは、できるだけシンプルに考えて、声に出す習慣を積み重ねることです。
ここでは、今日からすぐに始められる4つの練習法を紹介します。
練習法(1)音読とシャドーイングで口慣らしをする
練習法(2)主語+動詞+目的語の3語から始める
練習法(3)子供に話しかけるような簡単な言葉で考える
練習法(4)ネイティブの言い方を真似して答える



あなたの自信を少しずつ育て、中国語を話すことへの恐怖心を和らげていきましょう。
中国語を話すという行為を、頭だけで考えるのではなく、スポーツのようなフィジカルトレーニングとして捉え直してみましょう。
そのための最も効果的な準備運動が、「音読」と「シャドーイング」です。
まず音読は、テキストを見ながら声を出すことで、文字と音をしっかりと結びつけ、記憶を強化する効果があります。
一方、シャドーイングは、お手本の音声を聞きながら、少し遅れて影(シャドー)のように真似て発音する練習法です。
これは、ネイティブの自然なリズム、スピード、イントネーションを体に直接叩き込むための訓練です。
聞こえてくる音をそっくりそのまま真似ることに集中することで、リスニング力とスピーキング力が同時に鍛えられていきます。



音声付きのHSK教材や、好きな中国ドラマのワンシーンなどを利用し、読んで意味が分かる程度の文章から始めましょう。
10分程度の短時間でいいので、毎日続けることが大切です。
この地道な「口慣らし」が、あなたの口の筋肉を中国語モードに切り替え、いざという時に言葉がスムーズに出てくるための土台を築いてくれるのです。
会話中に頭が真っ白になってしまう大きな原因の一つに、「完璧で長い文章を話そうとしすぎること」があります。
例えば、「昨日、会社の近くの新しいレストランで、同僚と餃子を食べました」と一気に言おうとすると、脳は膨大な情報を処理しきれずにフリーズしてしまいます。



そこでまずは「我吃饺子(私は餃子を食べる)」という3語の幹となる部分から始めるのです。
そこに「昨日」を表す「昨天」を主語の前後につけたら、「とりあえず伝える」ことは大成功です。
話している相手は人間ですので、その先は「誰と?」「どこで?」「おいしかった?」などと、自然に会話が膨らんでいきます。
このように「主語+動詞+目的語」の単純な構造に絞ることで、脳の負担は劇的に軽くなり、テンパることも減ります。
まずは自分の言いたいことをすべてこの「3語+α」のシンプルな形で表現する練習をしてみてください。
この意図的な「制限」こそが、あなたの会話の瞬発力を高め、自信の土台を築く確実な方法となります。
私たちは普段、大人として社会生活を送る中で、無意識に複雑で丁寧な言葉遣いをしています。
しかし、その思考の癖をそのまま外国語の会話に持ち込むと、途端に難易度が跳ね上がります。
「このプロジェクトの進捗に遅延が生じています」といった複雑な日本語を、そのまま中国語に翻訳しようとして言葉に詰まってしまうのです。
ここで有効なのが、「これを小学生に伝えるなら、どう言うだろう?」と、一度自分の頭の中で思考を翻訳し直す習慣です。
この思考のフィルターを通すことで、難しい専門用語や凝った言い回しを自然と避けることができ、自分がすでに知っている簡単で平易な単語や文法で表現する道筋が見えてきます。
例:
ぐっとシンプルな言葉で核心を伝えることができますよね。
話す前に一瞬だけ立ち止まり、この「子供に話しかける」という視点を取り入れてみてください。
あなたの知っている限られた語彙だけでも、十分に豊かで的確なコミュニケーションが取れることに、きっと驚くはずです。
スピーキング能力を効率的に向上させる秘訣の一つに、「模倣」、つまりネイティブの言い方をそっくり真似てしまうという方法があります。
私たちはつい、単語を一つ一つ拾い集めて、文法ルールに従ってゼロから文章を組み立てようとしてしまいますが、これでは時間もかかり、不自然な表現になりがちです。
まずは、ネイティブに何かを聞かれたら、それを真似して単語だけ入れ替えましょう。
例:
A:你喜欢听音乐吗?(音楽聴くの好き?)
B:我喜欢听音乐。(音楽聴くの好き)
A:你喜欢听什么?(何を聴くのが好き?)
B:我喜欢听○○。(○○を聴くのが好き)
また、ネイティブが言っていた言葉を覚えておいて、別の人との会話で使うのも効果的です。
会話の中で相手が言ったフレーズを場面をセットで記憶し、同様の場面で使ってみるのです。
スマートフォンに「中国語フレーズ帳」というメモを作り、日々の生活や学習の中で出会った「使えそうな表現」をストックしておくのも良い方法です。
これらの練習は、あなたの表現の幅を広げるだけでなく、ゼロから文章を考える負担を減らし、会話の瞬発力が劇的に高まりますよ。


中国語を何ヶ月も何年も勉強したのにうまく話せない!
その主な原因は、アウトプット不足と通じなかった時の不安です。
通じなかったらどうしようと思うと話せなくなる→話さないからうまくならない、という悪循環に陥ってしまうのですね。
この状況を打破するためには、まずは口を動かして中国語を言う練習をたくさんして、中国語を話すということそのものに慣れることが第一歩です。
音読やシャドーイングを通して練習しましょう。
また、日本語を介して中国語を考えると、どうしても長く難しい文を思い浮かべがちです。



子供に話しかけるように短くて簡単な言い回しを考えると比較的話しやすくなります。
主語+動詞+目的語の形をベースに話してみましょう。
そして何より、話すということは相手がいるものです。
発音も文法も何一つ間違いのない完璧な文を話すことよりも、相手に意思を伝え、会話を楽しむことの方がずっと大切です。



肩の力を抜いて、リラックスして話してみてくださいね。
毎日中国語公式LINEでも伝わるようになる1Day無料勉強会をご案内しています!


この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
