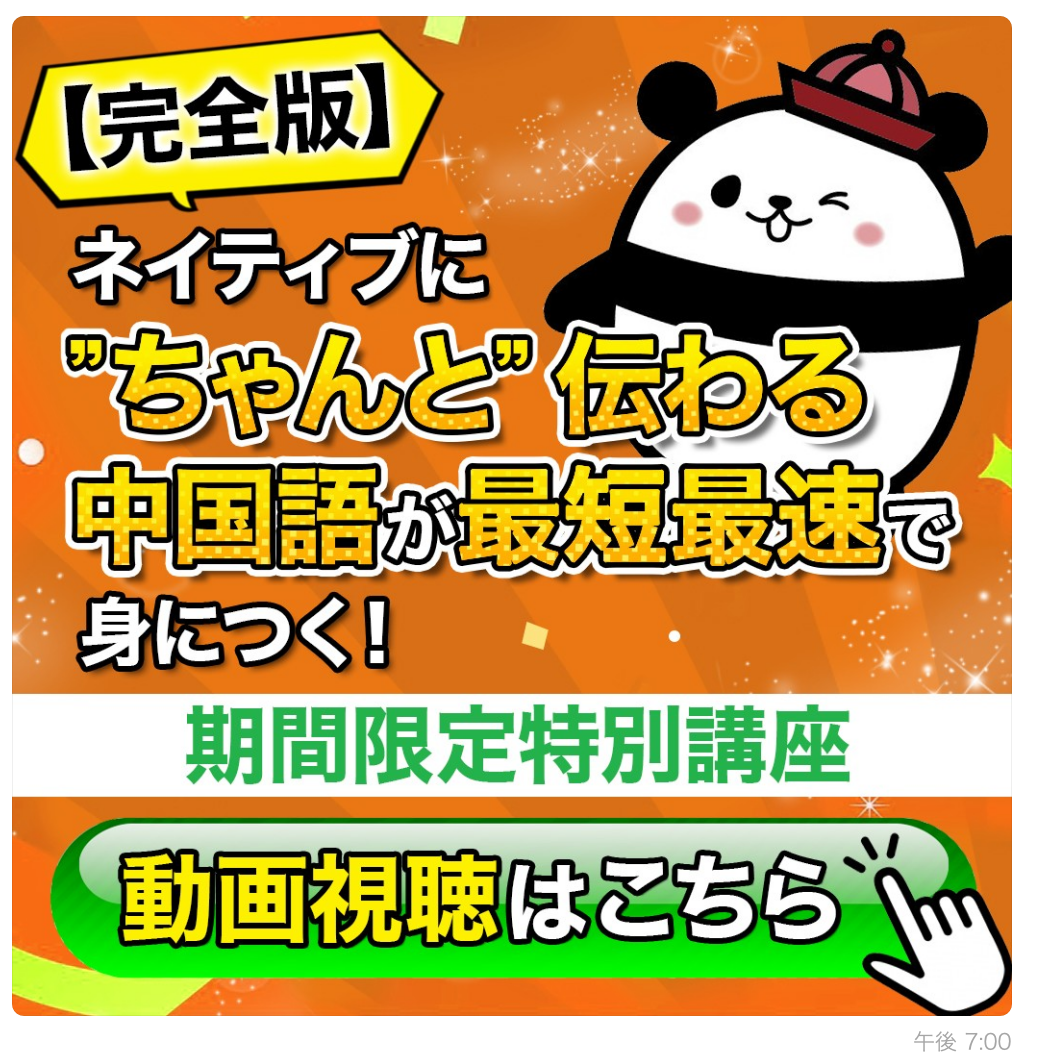
\ 期間限定動画無料配布中 /

スペイン語と中国語はどちらが将来性がありますか?
就職や転職において、外国語はアピール材料になりますよね。



「英語+αの語学を身につけたい」、もしくは「英語は得意でないので他の言語を始めたい」という方にとって、スペイン語や中国語は選択肢の1つです。
この記事では話者数、経済規模、活かせる職種、学習のしやすさなど多方面からスペイン語と中国語の将来性を比較します。
納得のいく選択で、自分の市場価値を高めましょう!




スペイン語と中国語、どちらが将来有望なのか、この章ではキャリアの可能性を客観的に判断する2つの指標を解説します。
2025年、中国語(標準語)を母語とする人は9.9億人で世界1位、スペイン語は4.84億で2位です。
総話者数で見ると、英語が1位、中国語(標準語)は11.84億で2位、スペイン語は5.58億人で4位です。
出典:What is the most spoken language? | Ethnologue Free
使用人口では中国語がスペイン語を圧倒していますが、「広がり」にも着目してみましょう。
中国語は中国大陸や台湾の他、シンガポールでも1つの公用語になっています。
マレーシアの中華系住民や、アメリカ・カナダ等の華僑コミニュティでも話されています。
スペイン語はスペインだけでなく、遠く離れたメキシコ、アルゼンチン、コロンビアなどのラテンアメリカ、アフリカの赤道ギニアなど約20カ国の公用語です。
そして、巨大市場のアメリカにも約4000万人のネイティブスピーカーがいます。
スペイン語は広範囲で分布しているため、特定の国の政治・経済情勢にキャリアが左右されにくいと言えるでしょう。
IMF統計の2024年名目GDPは、アメリカが1位で、中国は2位です。
スペイン語圏は各国を合計しても、中国の4分の1程度に留まります。
出典:世界の名目GDP 国別ランキング・推移(IMF) – GLOBAL NOTE
また、ロイターのエコノミスト調査によると、中国2025年通年のGDP成長率は約4.6%、2026年は4.2%とやや鈍化が予想されています。
出典:China’s GDP growth set to slow, raising pressure on policymakers
ラテンアメリカ・カリブのスペイン語圏においては、2025年予測がアルゼンチン+5.5%、ペルー+2.8%、メキシコ-0.3%と国によって差があり、平均するとラテンアメリカ・カリブもやや鈍化傾向です。
出典:IMF cuts GDP growth projection for Latin America and the Caribbean …
どちらも鈍化傾向ではあるものの、成長率でも中国がスペイン語圏を上回っています。


では、スペイン語学習の魅力はどこにあるのでしょうか。
本章では3つの観点から、その魅力を深掘りします。
中国語とスペイン語の両言語とも国連公用語の地位を持っていますが、スペイン語は国連、WHO、IMF、世界銀行などの主要国際機関で広く使用されています。
特にラテンアメリカ諸国の多くが民主主義国家であるため、日本の価値観と親和性が高く、外交・国際協力分野でのキャリア機会があります。
日本のJICA事業においても、ペルー、チリ、コロンビアなどへの大規模ODAプロジェクトでスペイン語人材の需要が高まっています。
グローバルな事業開発や国際機関で働くことを視野に入れるなら、多国間で協力体制を築きやすいスペイン語が長期的なキャリアに有利になる可能性が高いでしょう。
スペイン語は、日本人にとって発音しやすい言語の1つです。
スペイン語の発音は、日本語の五十音にかなり近く、ローマ字読みで通じる単語が多いのが特徴です。
例)
文法面に関しては、スペイン語は動詞の活用が多いと言われますが、規則的なパターンを体系的に学習することで習得可能です。
また、名詞に「男性名詞」「女性名詞」の区別がある点も、多くは「-o」で終わる語が男性名詞、「-a」で終わる語が女性名詞といった直感的に理解できるルールがあります。
日本の観光・サービス業界ではスペイン語人材の供給不足が深刻で、好条件で即戦力採用される可能性があります。
インバウンド観光でスペイン語圏からの訪日客は年々増加していますが、中国語と比較してスペイン語対応可能な人材が圧倒的に不足しており、「希少性のプレミアム」が働いています。
観光・サービス業でのスペイン語経験は、その後の総合商社やIT企業への転職時にも実務経験のある希少人材として高く評価される差別化要因となります。


この章では、スペイン語学習における懸念事項を解説します。
スペイン語を始める前に知っておきましょう。
スペイン語は国内での求人数が絶対的に少ないです。
例えばIndeedで検索すると、英語関連の求人は24万件以上、中国語関連は6万件以上見つかるのに対し、スペイン語は約2,000件です。(2025年7月時点)
せっかくスペイン語を学んでも、就職・転職活動における選択肢が狭く、スペイン語を使う求人は以下のような業種に限定されがちです。



これは、日本とスペイン語圏の貿易・投資関係が限定的で、言語のニーズが経済規模ほどには拡大していないためです。
また、実務上は英語を共通語としてやり取りするビジネスが主流のため、スペイン語が必須とされる場面が少ないのです。
スペイン語は日本人にとって発音しやすいため、学習初期の頃は取り組みやすさがあります。
しかし、ビジネスで通用する上級レベルに達するには、想像以上の学習時間を要します。
英語学習で「I have」「He has」のような三人称単数形や、「eat-ate-eaten」のような不規則動詞に苦労した人も多いのではないでしょうか。
スペイン語の動詞は、例えば「hablar(話す)」だけでも現在形で6通り、全時制では80通り以上の変化があります。
さらに、ビジネスで使いこなすためには、読解や文法などテストのための勉強ではなく、実践的な練習が必要です。
中学・高校と6年間英語を勉強しても英語を話せない人はたくさんいますよね。
スペイン語に限ったことではありませんが、外国語をビジネスレベルまで学習するには、長期学習が必要であることを心得ておきましょう。
スペイン語を公用語とするラテンアメリカ諸国でのキャリアは、政治・治安リスクが伴います。
世界平和度指数では中国が88位に対し、チリ64位、アルゼンチン47位など比較的良好な国もある一方、メキシコやコロンビアでは麻薬カルテルによる治安悪化が深刻化しています。
政治リスクも無視できず、アルゼンチンでは2023年にペソが対ドルで50パーセント以上暴落するなど、政権交代により経済政策が急変するリスクや通貨不安定による資産価値の目減り、インフレーションによる生活コスト上昇なども懸念されます。



長期的なキャリア形成においてはリスク評価と安全対策を十分に検討しましょう。


ここからは中国語について見ていきましょう。
まずは、キャリア形成における中国語の優位点4つです。
中国語を学ぶ大きなメリットは、世界第2位の経済大国(GDP約19兆ドル)であり、14億人を抱える巨大市場へのアクセスが可能になる点です。
ビジネスチャンスの「絶対量」で考えれば、スペイン語圏を圧倒しているのが現状です。
中国一国の経済規模はスペイン語圏全体の約4倍に達し、製造業、EC、フィンテック(金融+IT)、AI技術など多様な成長分野が集積しているため、企業の中国戦略において中国語人材は不可欠な存在となっています。
観光業界でも、2024年は700万人弱の中国人観光客が日本を訪れました。
また、中国市場は沿岸部の大都市から内陸部の農村まで、発展段階が多様です。
事業展開においても多様なチャンスがあり、短期的な成果と長期的なキャリア双方を見込めると言えるでしょう。
中国語を習得することで、中国本土のみならず台湾、香港、シンガポール、マレーシアなどアジア全域の華僑ネットワークへアクセスしやすくなります。
アジア太平洋地域の経済発展において華人ビジネスネットワークは強い影響力があり、ASEAN諸国でも中国系企業や華僑系企業が経済の中核を担っています。
シンガポールでは人口の約75%が中華系で中国語が公用語の1つとなっており、マレーシアでは華人系企業が経済的影響力を持っています。
また、多くの日本企業は、アジア戦略の要として中国に拠点を置いています。
タイやベトナム、インドネシアといった周辺国への進出にも、中国語ができる人材が抜擢されるケースもあります。
中国語人材の需要は日本の基幹産業であるIT・製造業で特に高く、デジタル化の推進や製品の品質管理・生産管理等、全過程において重要なスキルとして位置づけられています。
例えば、トヨタの中国生産比率は15〜25%程度で、現地でのコミュニケーション能力が直接的に事業成果に影響します。
IT分野では、中国のデジタル技術が急速に発展し、中国のユニコーン企業数は約170社と世界第2位を誇るため、技術提携や共同開発において中国語ができるエンジニアやプロジェクトマネージャーの価値が上昇しています。
日本の対中貿易総額は2024年、44.2兆円で最大規模です。
貿易実務、物流、通関業務において中国語は英語と並ぶ重要スキルとして企業に認識されています。
中国は日本の最大貿易相手国であり、輸出入ともに圧倒的な取引量を誇るため、商社、物流企業、メーカーの調達部門では中国語ができる人材が継続的に求められています。
日中貿易総額は日本の総貿易額の約20パーセントを占め、中国語求人の業界別内訳では商社・貿易関連が約40パーセントを占める状況です。
複雑な貿易条件の交渉、品質仕様書の確認、納期調整などの実務レベルでは、英語よりも中国語での直接コミュニケーションが効率的かつ正確で、中国の貿易関連法規や商慣習の理解においても中国語能力は不可欠です。
実際に、三菱商事や伊藤忠商事といったトップ総合商社は、手厚い中国語研修制度を設けています。
これは、中国語能力が単なるスキルではなく、入社後の配属や昇進を左右する「決定的な武器」になることの証です。
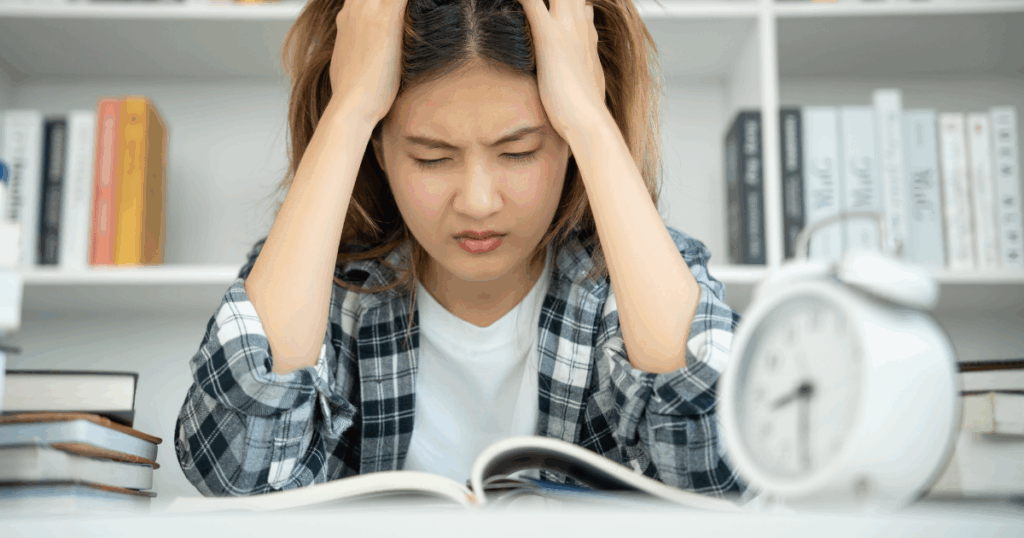
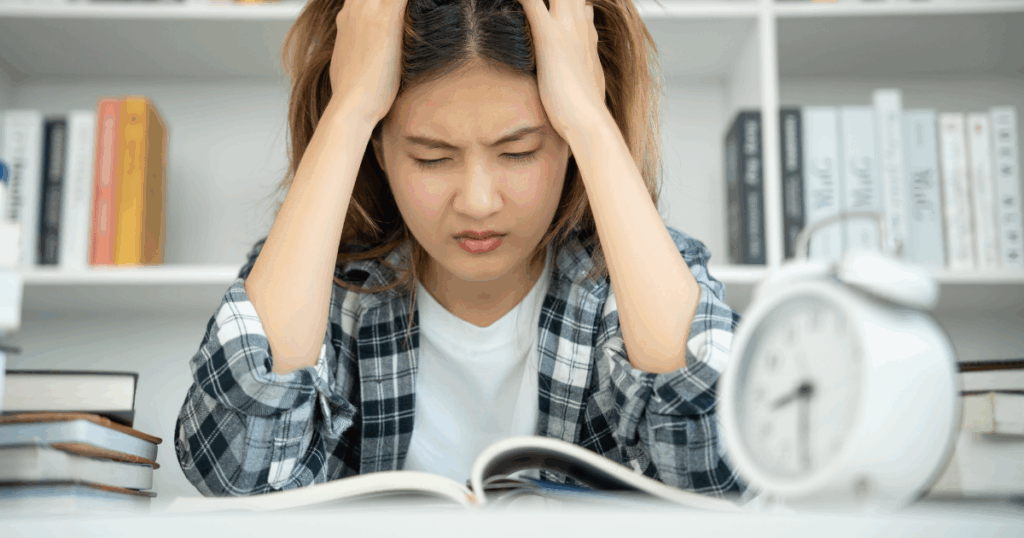
中国語ができればキャリア形成において大きな強みとなります。
しかし、実際に上級レベルまでに達して好条件の職に就くにはハードルもあります。
ここでは3点解説します。
中国語学習における最大の壁は「発音」です。
中国語は日本語とはどちらも漢字を使うという点では共通していますが、言語系統が異なります。
中国語は声調言語で、声調(四声)が違うと全く違う単語を意味してしまいます。
また、子音と母音の数も日本語よりずっと多く、日本人には発音しにくいものが少なくありません。
カタカナ発音ではほとんど通じないと思っておいた方が良いでしょう。
正しい発音ができないと、相手の話を聞くのも難しく、コミュニケーションに大きな支障が出ます。
中国語はそれだけ発音が大切なのです。
英語ほどではないものの、中国語学習者の絶対数は多く、中国語の検定試験であるHSKの日本国内年間受験者は2024年、33,815人でした。
出典:HSK 日本で一番受けられている中国語検定(HSK公式サイト)
中国語は漢字なので、漢字圏以外の人と比べれば日本人に優位な面があり、大学の第二外国語としても多く選ばれています。
そのため、中級レベルの中国語では就職の際に競争が激しく、他の求職者との差別化が難しいのが現状です。
上級レベルのHSK6級でも、中国語単体でのアピールはあまり期待できず、プラスαの専門スキル(金融・ITなど)と組み合わせることが必要になってきます。
米中対立の激化や、中国国内における規制強化、地政学的リスクの増大など、近年の国際情勢は日本企業の中国進出にとって決して容易なものではありません。
実際に中国拠点の規模を縮小したり、中国から撤退している日本企業もあります。
政治的な不安定さや突発的な政策変更が、進出や事業継続のハードルとなっているのです。
しかし一方で、こうした複雑なビジネス環境を理解し、現地との円滑なコミュニケーションを図れる「中国語ができる人材」の価値が高まっているとも言えます。
特に製造業や貿易、テック分野では、中国語スキルを持ち、かつリスクマネジメントの視点を持った人材が重宝されています。
中国語は単なる言語スキルにとどまらず、政治・経済のダイナミズムに対応できるグローバル人材としての評価にも直結しています。
将来性を見据えるなら、こうした国際情勢も踏まえて言語を学ぶことが、長期的なキャリア構築に大きな武器となるはずです。


スペイン語と中国語の将来性を比較してきました。
どちらが一方的に優れているということはなく、自分が何に興味を持ち、どんなことをしたいのかで選ぶことが重要です。
巨大経済圏でのビジネスチャンスを最優先するなら中国語、幅広い国や地域の人々と繋がり、多様な文化圏で活躍したいならスペイン語が、あなたの強力な武器となるでしょう。
中国語の学習については、毎日中国語公式LINEの情報もチェックしてみてくださいね!
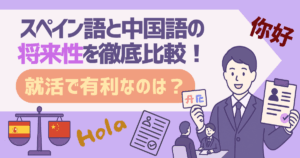
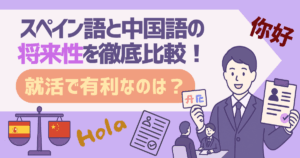
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
