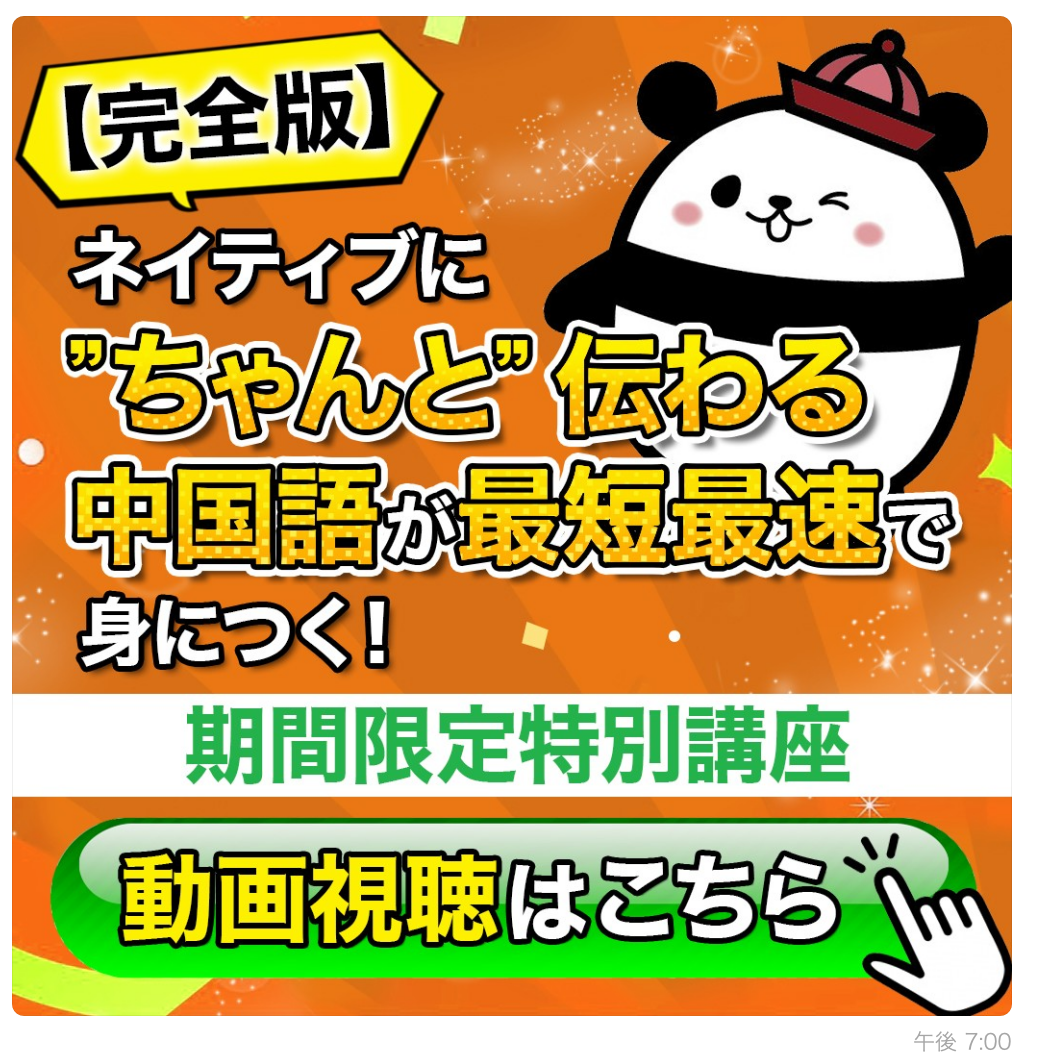
\ 期間限定動画無料配布中 /

中国語の単語で、特に発音が難しいのはどれですか?



中国語は日本語にない発音が多いため、発音に苦労している日本人は少なくありません。
この記事では、日本人が特に言いにくい単語の中から実際の会話でよく使われるものを選びました。
発音のコツもあわせて紹介しますので、今日はさっそく練習を始めて、ネイティブに褒められる発音をゲットしましょう!




それではさっそく日本人が難しいと感じる中国語の単語を見ていきましょう。
よく使われる重要単語を厳選して紹介します。
中国語学習者が最初につまずく大きな壁、それが「そり舌音(そりじたおん)」です。
ピンインの zh, ch, sh, r がこれにあたり、日本語にはない舌の使い方をするため、多くの人が苦手意識を持っています。
ポイントは、舌先を上の歯茎の少し奥(硬口蓋)に向けて持ち上げ、舌全体を少し奥に引くことです。



「舌を巻く」と意識しすぎると不自然な力が入ってしまうので、まずは「舌を奥に引いて、スプーンのような形にする」イメージを持ってみましょう。
舌をそり舌音のポジションにセットし、息を破裂させずに出します。
ワンポイント: 舌の位置をキープしたまま母音を発音する練習を繰り返しましょう。
zh と同じ舌の形で、強く息を吐きながら出します。
ティッシュを口の前にかざし、それが勢いよく揺れるくらい息を出すのが目安です。
ワンポイント: chī は「チー」にならないようにしましょう。
「出租车」は難易度が高いですが非常に良い練習になります。
zh ch と同じ舌のポジションで、息を隙間から持続的に摩擦させて出す音です。
ワンポイント: 日本語の「シ」とは口の形も舌の位置も全く異なります。
特に shì は最頻出単語なので、ここで正しい形をマスターしましょう。
日本語の「ラ行」とは違い、舌先はどこにも触れません。
ワンポイント: 誰もが苦しむ「我是日本人」が綺麗に言えれば、そり舌音はかなりマスターしたと言えるでしょう。
焦らず、ゆっくりしたスピードから練習してみてくださいね。
そり舌音と並んで、多くの日本人学習者を悩ませるのが「母音」の発音です。
日本語の母音は「ア・イ・ウ・エ・オ」の5つとシンプルですが、中国語には36種類もの母音が存在します。
特に、日本語にはない口の形や舌の動きが求められる母音は、意識して練習しないとネイティブにはなかなか通じません。
ここでは、特に日本人が苦手としがちな「ü」「e」「er」と鼻音を含む、代表的な単語を見ていきましょう。
「u」の上に点々が付く「ü」は、日本語にない代表的な母音です。
ストローで飲み物を吸う時のように唇をぐっとすぼめて「イ」を言うと近い音が出ます。
注意!: ピンインのルールで、j, q, x の後の “u” は、すべて “ü” の音で発音します。
juは実はj+uではなく、j+üです。quとxuも同様です。
口を半開きにして、舌を自然な位置に置き、喉の奥から「エ」と「オ」の中間の音を曖昧に出すのがポイントです。
口周りの力を抜いてリラックスしましょう。
曖昧母音「e」を発音しながら、最後に舌先をグッと奥に引いてカールさせる音です。
アメリカ英語の “bird” の “ir” の音によく似ています。
ワンポイント: 这儿 (zhèr) や 那儿 (nàr) のように、単語の最後につく “r” は「儿化音」と呼ばれ、前の母音と融合して発音されます。
主に中国の北方の地域で言われています。
中国語の発音の中で、日本人には同じように聞こえるのに、中国人には全く違う単語に聞こえているのが「鼻音」です。
日本語の「ん」は、実は後ろに来る音によって無意識に発音が変わる音ですが、中国語ではこの違いを意識的にコントロールする必要があります。
発音のコツ:-n は前(舌先)、-ng は奥(舌の根)
まずは、2つの音の決定的な違いである「舌の位置」を覚えましょう。
理屈がわかったら、今度は実際に単語で違いを体感してみましょう。
以下のペアを、舌の動きを大げさに意識しながら発音してみてください。
| -n 前鼻音 | -ng 後鼻音 |
| 陈 (chén) | 成 (chéng) |
| 真 (zhēn) | 正 (zhèng) |
| 心 (xīn) | 星 (xīng) |
| 晚 (wǎn) | 网 (wǎng) |
| 穿 (chuān) -着る | 窗 (chuāng) -窓 |
ミニ例文で練習!
練習のヒント
最初はゆっくり、「fanーfang」のように交互に発音し、舌先の動きと喉の響きの違いを体で覚えるのが効果的です。
自分の声を録音して、ネイティブの音声と聞き比べてみるのも良いでしょう。
中国語の単語の意味を決定づける「声調」。
実際の会話では、単語が組み合わさることで声調が変化することが頻繁に起こります。
それが「軽声(けいせい)」と「声調変化(変調)」です。



ルールを理解すれば、あなたの中国語は一気にネイティブらしくなります。
「軽声」とは、音節が本来の声調を失い、前の音に添えるように軽く、短く発音される音のことです。ピンインでは声調記号を付けずに表記されます。
助詞や単語の2音節目などによく現れ、発音に自然な強弱のリズムを生み出します。
【軽声の代表例】
ワンポイント: 軽声は、前の音節の発音が終わった後に軽く音を置くようなイメージです。
特定の声調が連続するとき、発音しやすくするために声調が変化するルールです。特に重要な3つのルールを覚えましょう。
ルール①:第三声 + 第三声 → 第二声 + 第三声
低い音である第三声が続くと発音しにくいため、前の第三声が上がり調子の第二声に変化します。これは最も頻繁に起こる変調です。
ルール②:「一 (yī)」の変調
「一」は後ろに続く単語の声調によって、声調が変わります。
ルール③:「不 (bù)」の変調
「不」はシンプルです。後ろに第四声の単語が続くときだけ、第二声の bú に変化します。
※変化しない例:不吃 (bù chī), 不忙 (bù máng)
「中国語は声調が命」——この言葉を何度も聞いたことがあるかもしれません。
日本語でも「橋(はし)」と「箸(はし)」のように同音異義語がありますが、イントネーションで区別しますよね。
中国語では、その役割を「声調」が担っています。
声調を1つ間違えるだけで、意味が通じないどころか、全く違う意味に取られてしまい、時には赤面するような誤解を生むことも…。
ここでは、特に間違えやすく、覚えておくとリスニング力とスピーキングの正確性が格段にアップする「そっくりさん単語」たちを、面白い例文と一緒に紹介します。クイズ感覚でマスターしていきましょう!
1つの音だけで意味が全く異なる、声調トレーニングの基本となる単語です。
言い間違えると意図が正反対に伝わってしまう、非常に重要なペアです。
単語が2音節になってもルールは同じです。聞き分けの難易度が少し上がりますが、良い練習になります。
このように、ピンインが同じでも声調が違うだけで意味が全く変わる単語は無数にあります。
焦らず一つずつ、音の違いを楽しみながら覚えていきましょう。


それでは最後に、中国語の発音が難しい単語の練習方法を紹介します。
中国語は発音を間違えるととても通じにくい言語です。
聞き分けて自分でも言えるようにしていきましょう。
似た音の聞き分けは、舌の位置と息の強さを「目で見て、体で感じる」練習で、意外とあっさり解決できるんです。
日本人が最も苦労するのは、そり舌音であるzh、ch、sh、rとそれ以外の区別、および有気音と無気音の区別です。
これらは発音の特徴が似ているため、聞いただけでは区別が難しいですが、発音時の舌の位置や息の強さという物理的な違いを体感することで確実に区別できるようになります。
鏡で自分の口の形や舌の位置がお手本と同じになっているか確認しましょう。



1日10分程度でも「見る・聞く・比較する」練習を続けてみてください。
「あれ?いつの間にか聞き分けできてる!」という嬉しい発見が来る日はそう遅くはありません。
声調は「手・頭・心」で覚えましょう。
声調は抽象的な音程変化のため、耳からの情報だけでは記憶に定着しにくいのです。
手のジェスチャー、単語の意味、使う場面を一緒に覚える方法なら、自然で実用的な声調感覚が短期間で身につきます。



手のジェスチャー練習では、第一声は水平、第二声は上昇、第三声はV字、第四声は下降の動きと連動させて練習しましょう。
中国語の発音は日本語より種類が多い上、声調があるため、カタカナでは正確な発音を書き表すことができません。
カタカナ発音からの卒業は4ステップで脱却しましょう。
一度カタカナで覚えてしまうと、あとから矯正するのが大変です。
中国語の発音はピンインで覚えることも大切です。


発音が難しい中国語の単語を一気に紹介しました。
中国語の発音が難しい!と感じる理由は口の形や舌の位置、息の出し方などが日本語とは異なるからです。
「我是日本人」に代表されるそり舌音をはじめ、「e」など日本語にない母音、-nと-ngの区別、有気音と無気音、さらには声調の変化まで練習することがたくさんあります。
耳だけの情報だけでは、無意識に日本語のカタカナで代用しがちなので、目や手も使って練習しましょう。
少しずつでも毎日続けることが大切です。
毎日中国語公式LINEの中国語学習情報もチェックしてみてくださいね!
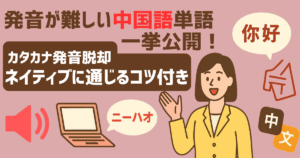
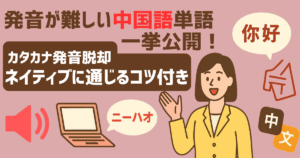
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
