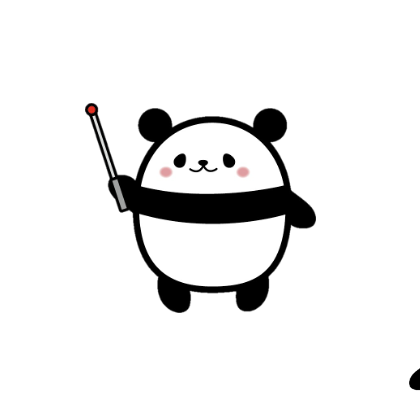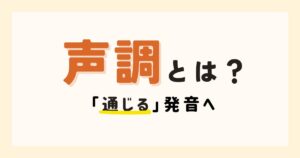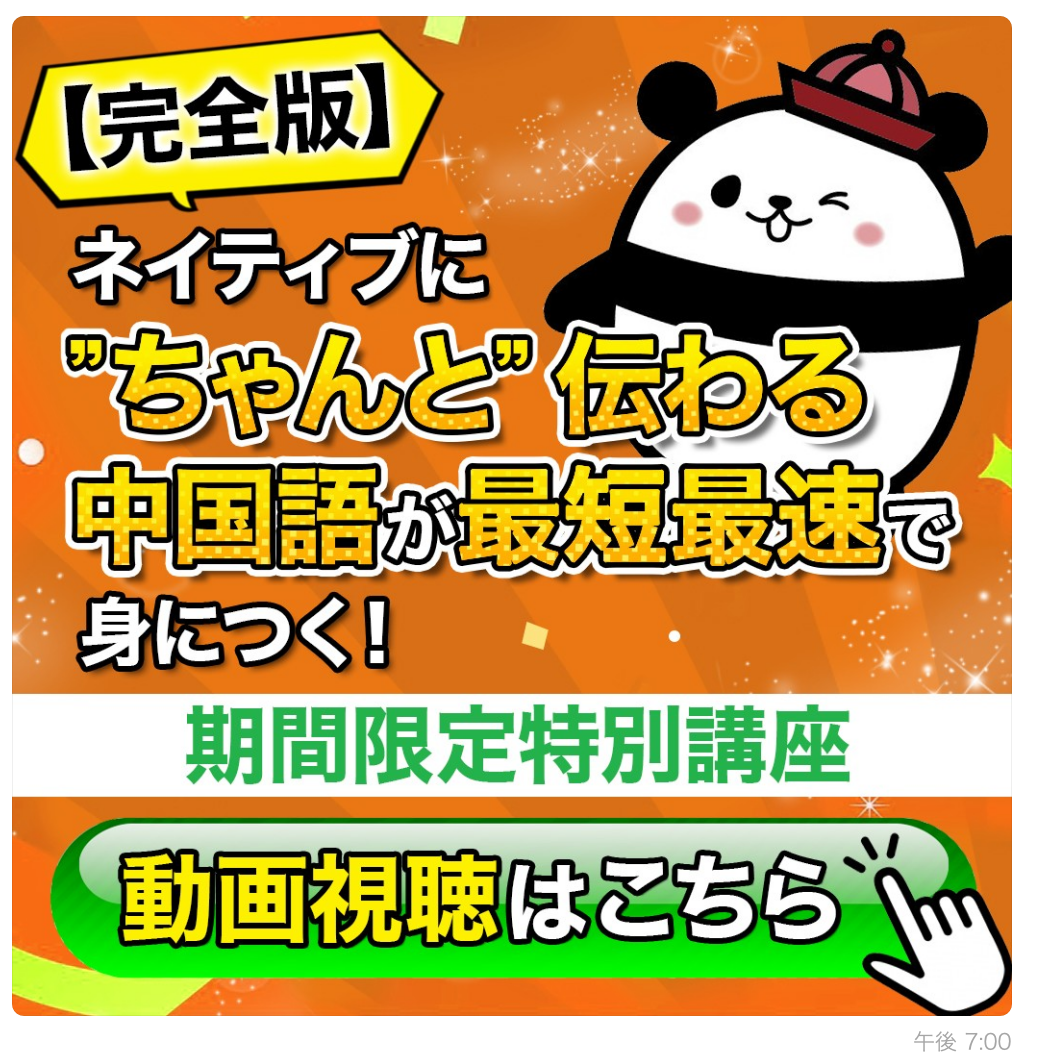
中国語の声調とは?発音の基本と変化ルールを理解し「通じる」発音へ
この記事でわかること
- 中国語は4つの声調と軽声があり、声調によって意味が変わるため非常に重要。
- 中国語の第三声、「一」、「不」は声調が変化する。
- 中国語の声調は、声調ごとの組み合わせで練習すると覚えやすい。

中国語の声調がどれも同じように聞こえたり、覚えられなかったりしていませんか?
日本語も「柿」と「牡蠣」、「橋」と「箸」のような違いはあるものの、普段アクセントを意識していることは少ないですよね。
一方、中国語は4つの声調+軽声によって意味が変わる言語で、声調を間違えると全く通じなくなってしまうことも珍しくありません。
こういった概念の差から、日本人は中国語の声調の違いを聞き分けられなかったり、なかなか覚えられなかったりするのです。
この記事では、中国語の声調の基本から、発音のコツ、声調が変化するルール、聞き分ける練習方法、声調符号の入力方法まで解説します。
ピンインとともに声調を習得し、「通じる発音」を身につけましょう!
目次
中国語の声調とは?基礎知識と重要性


この章では、中国語の声調とは何か、基本的な仕組みと重要性を紹介します。
中国語の声調には主に以下の内容があります。
- 中国語の声調の種類と特徴
- 声調が意味を分ける重要な役割
- 日本語アクセントとの違い
中国語の声調の種類と特徴
中国語(普通話)には4つの基本声調と、軽声と呼ばれる特殊な声調があり、日本語では「四声(しせい)」とも言われています。
声調(声调 shēng diào)は中国語において音の高さと変化パターンを表し、同じ音節でも声調が異なると意味が完全に変わります。
| 声調 | 例 | 発音の特徴 | イメージ |
|---|---|---|---|
| 第一声(高平音) | mā(妈)お母さん | 高く平らな音 | 汽笛の「ポー」 |
| 第二声(上昇声) | má(麻)しびれる | 低いところから高いところへ上げる | 驚いた時の「ぇえ!?」 |
| 第三声(下降上昇声) | mǎ(马)うま | 低く抑えて、力を抜いて中程度まで戻す | がっかりした時の「あ〜あ」 |
| 第四声(下降声) | mà(骂)ののしる | 高いところから低いところへ下げる | 返事をする「はい!」「そう」 |
| 軽声 | ma(吗)〜ですか? | 軽く短く発音する | 弱く音を添える |
中国語の第一声(陰平)は、高く平らに発音する声調で、安定した高音を保つのが特徴です。
音の途中で高くなったり低くなったりせず、最後まで同じ高さを維持することが重要です。
日本語の「あー」と平らに伸ばすイメージで、最も高い音域で発音しましょう。
ドレミファソラシドの「ソ」くらいの高さを意識し、息を均等に吐き出す練習が効果的です。
これにより、安定した第一声が身につきます。
中国語の第二声(陽平)は、低いところから一気に高く上がっていく声調です。
日本語の「え?」と聞き返すときの語尾の上がり方に似ています。
音の始まりは低く、終わりは最も高くなるように意識して発音します。質問しているかのように語尾を上げてみましょう。
音の上がり始めの低さから、目標とする高音まで一気に声を持ち上げる練習を繰り返すことで、滑らかで自然な第二声が身についていきます。
中国語の第三声(上声)は、一度低く沈み込み、そこから少しだけ持ち上げるように発音する声調です。
音の変化が複雑ですが、低く抑える部分と、そこからわずかに上がる部分を意識することが重要です。
日本語の「あ↘あ↗」と、一度ため息をつくように音を下げ、そこから軽く持ち上げる感覚で発音します。
単独で発音する際は少し長めになる傾向があります。
この練習で自然な第三声が身につきます。
中国語の第四声(去声)は、高いところから一気に低く下がりきる声調で、強く断定するようなイメージで発音します。
音の急激な下降が特徴で、高い音から低い音へ明確に落とすことで、意図が伝わりやすくなります。
日本語の「そう!」と強く言い切る感覚に似ています。
高い音から勢いよく音を落とす練習を繰り返すことで、力強く明確な第四声が身につきます。
メリハリをつけて発音しましょう。
軽声とは?省略される声調の正体と使い方
軽声は、特定の音節が声調を持たずに短く軽く発音される現象のことです。
前に置かれた音節よりも弱く短く発音される音のことを指します。
たとえば「妈妈(māma)」の2音目「ma」や、「什么(shénme)」の「me」が軽声です。軽声は主に助詞や代名詞、接尾語などでよく使われ、会話に自然なリズムと流れを生み出します。
発音としては平らで淡い調子になり、前の音節の強さとの対比によって軽さが際立ちます。
軽声は正確さよりもリズム重視で学ぶことがコツです。よく出てくる軽声の単語を繰り返し聞いて、感覚として身につけていくことが効果的です。
声調が意味を分ける重要な役割
中国語において声調は語の意味を区別する決定的な要素であり、声調を間違えると全く異なる意味になってしまいます。
例えば上記の表の「ma」という音節1つをとっても、声調によって「お母さん」「しびれる」「馬」「罵る」「〜ですか?」と、全く異なる意味を持ちます。
「お母さんはお元気ですか?」と言いたいのに、声調を間違えると「馬は元気ですか?」となってしまう可能性があるのです。
このように声調の違いを無視すると、意図しない誤解を招く可能性があります。
そのため、声調を軽視せず、単語を覚える際には必ず声調も一緒に覚えるようにしましょう。



間違った発音習慣が定着する前に正しい発音を身につけることが大切です。
日本語アクセントとの違い
中国語の声調と日本語のアクセントは、音の高低を使うという点では似ていますが、仕組みと機能に大きな違いがあります。
図のように、日本語は「私は」「日本人」のような単語の区切りごとにアクセントが決まっていて、ひらがな1文字が1音節です。
しかも、アクセントが違ってもコミュニケーションに支障がないことがほとんどです。
それに対し、中国語は1つの漢字ごとに音の高低が決まっていて、漢字1文字が1音節です。
そして、声調が違うと別の漢字になってしまいます。
また、中国語の声調における音の高低変化の幅は日本語のアクセントよりも広く、意識的に音の高低を大きく使い分ける必要があります。



日本人が中国語を勉強する際は、これらの違いを理解した上で、中国語特有の音の高低変化に慣れる練習を重ねていきましょう。
声調の変化ルールを理解しよう


この章では、中国語の声調の変化ルール(変調)を紹介します。
声調の変化には主に以下の内容があります。
- 第三声の変調(3声+3声→2声+3声)
- 「一」の声調変化パターン
- 「不」の声調変化パターン
- 「半三声」とは?正しい使い方
第三声の変調(3声+3声→2声+3声)
第三声が続く場合、声調が変化します。
ルール①:3声+3声→2声+3声
例)
| 単語 | ピンイン | 実際の発音 |
| 你好 | nǐ hǎo | ní hǎo |
| 可以 | kě yǐ | ké yǐ |
| 水果 | shuǐ guǒ | shuí guǒ |
ルール②:3声が3つ以上続く→一般的には最後の1つ以外が2声になる(意味の区切りによって例外あり)。
例)「我很好」wǒ hěn hǎo→wó hén hǎoが多い
このような変化はピンイン表記には表れず、実際の発音だけが変わります。
「一」の声調変化パターン
数字の「一」(yī)には、後に続く単語の声調によって変化する特殊なルールがあります。
ルール①:単独で使う場合、文末にある場合、数字の「十」の前は、本来の第一声「yī」のまま発音。
ルール②:第一声、第二声、第三声の前では第四声「yì」、第四声の前は第二声「yí」に変化。
例)
| 組み合わせ | 例 |
| 「一」+第一声→yì | 一些(yì xiē) |
| 「一」+第二声→yì | 一直(yì zhí) |
| 「一」+第三声→yì | 一起(yì qǐ) |
| 「一」+第四声→yí | 一定(yí dìng) |
その他、重ね型動詞の間では軽声になったり、声調が弱まったりすることがあります。
例)看一看 – kàn yi kàn / kàn yí kàn、想一想 – xiǎng yi xiǎng / xiǎng yì xiǎng など(文脈や話者により揺れがあり)。



日常会話で「一」は非常に頻繁に使われるため、「一起」「一定」「一下」のようなよく使われる表現を声に出して練習しましょう。
「不」の声調変化パターン
否定を表す「不」(bù)も、後に続く単語の声調によって変化する重要なルールがあります。
ルール:第一声、第二声、第三声の前では本来の第四声「bù」のまま発音、第四声の前は第二声「bú」に変化。
例)
| 組み合わせ | 例 |
| 「不」+第一声→bù | 不说(bù shuō) |
| 「不」+第二声→bù | 不能(bù néng) |
| 「不」+第三声→bù | 不想(bù xiǎng) |
| 「不」+第四声→bú | 不要(bú yào) |
また、可能補語や反復疑問文の中では軽声「bu」になることもあります。
例)「看不懂」(kàn bu dǒng)「好不好」(hǎo bu hǎo)など。
「不」の変調ルールは「一」に比べるとシンプルで、主に「第四声の前では第二声に変わる」ことを覚えておけば問題ありません。



日常会話でよく使う否定表現を正しい声調で練習していきましょう。
半三声とは?正しい使い方
半三声とは、第三声を完全に発音せず、下降部分だけを発音する方法です。
教科書では第三声は「低く下げてから上げる」と説明されていることが多いですが、実際の会話では、第三声を完全に発音することはあまりありません。
第三声が第一声、第二声、第四声、軽声の前にある場合、第三声は低く抑える「半三声」で発音されるのが一般的です。
例えば「你们」(nǐ men)を発音する際、「nǐ」の音は低く抑えるだけで、上げの動作はほとんど行いません。
同様に「你听」(nǐ tīng)、「我来」(wǒ lái)、「想去」(xiǎng qù)、「早上」(zǎo shang)なども半三声で発音します。
半三声は単独で第三声を発音する場合や文末に来る場合を除いて、ほとんどの状況で使われます。
特にスムーズな会話では、完全な第三声(下げてから上げる)よりも半三声(下げるだけ)の方が自然です。
ネイティブの発音を繰り返し聞いて、声に出して練習しましょう。
声調練習の効果的な学習方法
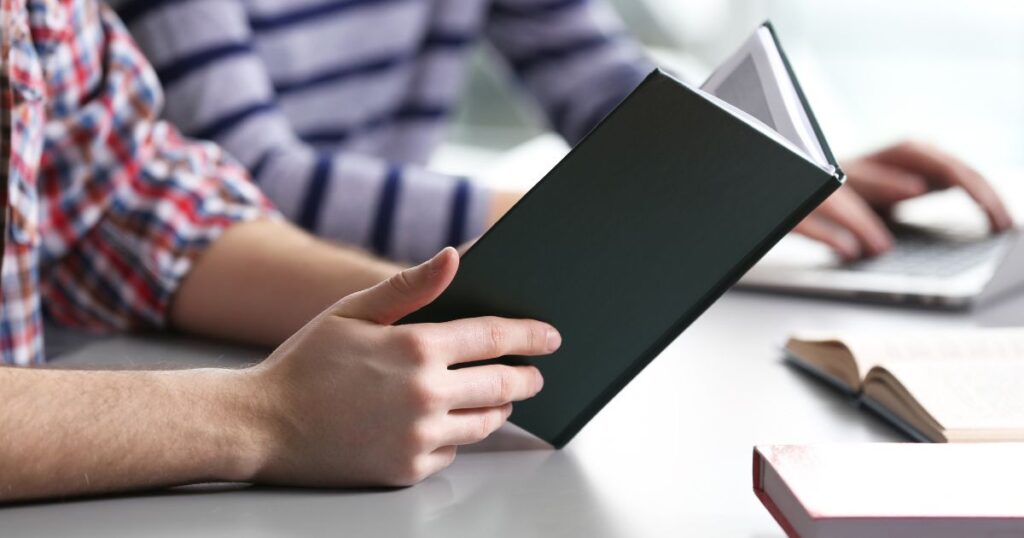
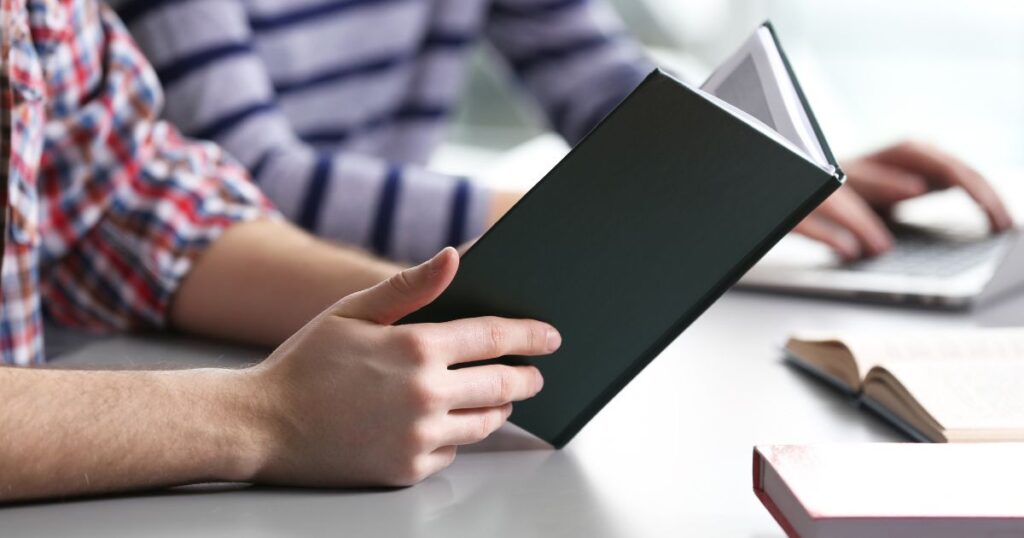
この章では、中国語の声調を聞き分けて、自分でも正しく発音できるようになる効果的な学習方法を紹介します。
声調練習の効果的な学習方法には主に以下の内容があります。
- 20通りの声調組み合わせ練習法
- 単語から文章へのステップアップ方法
- シャドーイングで声調感覚を養う
- 声調の聞き分け力を鍛える方法
20通りの声調組み合わせ練習法
中国語の単語の声調は、基本的な組み合わせとして、4つの声調同士の組み合わせ(16通り)と、各声調に軽声が続くパターン(4通り)があります。
パターンごとに練習すると違いを区別しやすく覚えやすくなります。
例)
スクロールできます
| 1声 | 2声 | 3声 | 4声 | 軽声 | |
| 1声 | 飞机 fēi jī | 公园 gōng yuán | 身体 shēn tǐ | 音乐 yīn yuè | 哥哥 gē ge |
| 2声 | 结婚 jié hūn | 学习 xué xí | 苹果 píng guǒ | 学校 xué xiào | 名字 míng zi |
| 3声 | 老师 lǎo shī | 旅行 lǚ xíng | 雨伞 yǔ sǎn | 可乐 kě lè | 姐姐 jiě jie |
| 4声 | 大家 dà jiā | 去年 qù nián | 汉语 hàn yǔ | 散步 sàn bù | 弟弟 dì di |
日本人の場合、2声+3声の組み合わせが特に言いにくいことが多いので、重点的に練習しましょう。
単語から文章へのステップアップ方法
中国語の声調習得は、次のような段階的なステップアップが効果的です。
- 単語を練習
- 2〜3語の短いフレーズを練習
- 短文を練習
- 対話文を練習
いきなり長い文に挑戦するのではなく、まずは単語レベルで正しく言えるようにし、少しずつ文を長くしていきます。
最初はゆっくりと正確に発音し、徐々にスピードを上げていきましょう。
シャドーイングで声調感覚を養う
シャドーイングとは、ネイティブスピーカーの音声を聞きながら、少し遅れて影のように発音する練習法です。
単に聞いて繰り返すリピーティングとは異なり、シャドーイングでは音声処理と発話を同時に行うため、より実践的な能力が身につきます。
練習手順としては、まず20秒~1分程度の短い音声素材を選び、内容と声調パターンを把握します。
次に音声を再生し、0.5~1秒遅れて、できるだけ同じ声調やリズムで発音します。
慣れてきたら遅れる時間を短くし、より同時に近い形で発音するようにしましょう。
中国語学習教材の音声、ポッドキャスト、YouTubeの会話チャンネル、はっきりと発音する中国語の歌などが適した素材です。
短時間でも毎日継続して練習するのが効果的です。
自分の発音を録音して比較すると改善点がわかりやすくなります。
声調の聞き分け力を鍛える方法



日本語は声調言語ではないため、日本人学習者にとって中国語の声調の聞き分けは特に難しい課題です。
声調の聞き分けに効果がある練習方法は以下のようなものがあります。
例)
- 声調だけが異なるペアを聞き比べる練習(「买 mǎi」と「卖 mài」など)
- 聞いた音声がどの声調か当てる(「超・中国語耳ゲー」などのアプリあり)
- ディクテーション(音声を聞いて書き取る)
聞くだけでなく自分でも声に出して言ってみるとさらに効果的です。
音の高さ・長さ・強さに注目するトレーニング



中国語の声調をマスターするには、音の高さ(ピッチ)、音の長さ、そして音の強さ(アクセント)を意識したトレーニングが不可欠です。
声調は単に音の高低だけでなく、音節全体の長さや、どの部分に重心を置くかによってもニュアンスが大きく変わります。
例えば、第三声は「低く抑え、少し伸ばす」という特徴がありますが、この際、ただ低いだけでなく、音の始まりから終わりまでの高さの変化、そして「低く抑える」際の音の長さを意識して発音してみましょう。
また、軽声は短く軽く発音することを意識し、他の声調との対比で練習すると、その違いがより明確になり効果的です。
発音練習の際には、音の高さをグラフで表示するアプリや、自分の声を録音して視覚的に確認できるツールを活用することをおすすめします。
これにより、客観的に自分の発音を分析し、どこを改善すべきかを見つけながら練習を進めることができるでしょう。
中国語の声調は、日本語にはない独特なルールなので、最初は戸惑うかもしれませんが、これらのポイントに注目して丁寧に練習を重ねれば、必ず上達を実感できます。
手や体を使って声調を覚える方法
声調を感覚的に覚えるためには、手や体を動かしながら練習する方法が非常に有効です。
視覚や聴覚だけでなく、運動感覚も活用することで、より深く声調のパターンを脳に定着させることができます。
特に、複雑な声調変化や連続した声調の発音時に、体の動きがガイドとなり、スムーズな発音を促してくれるでしょう。
具体的には、第一声は手を水平に伸ばす、第二声は手を上げる、第三声は手を下げてから少し上げる、第四声は手を勢いよく下げる、といったように、それぞれの声調に合わせたジェスチャーを考案し、発音と同時に実践してみてください。
または、発音のリズムに合わせて体を揺らしたり、ステップを踏んだりするのも良い方法です。
これらの身体的な動きは、特に中国語学習の初心者にとって声調のイメージをつかむのに大いに役立ちます。
最初は少し恥ずかしいと感じるかもしれませんが、積極的にこれらの方法を取り入れることで、体に声調を染み込ませ、自然な発音へとつながります。
何度も繰り返すうちに、体が声調の感覚を覚え、意識しなくても自然と正確な声調で話せるようになるはずです。
声調だけを集中的に練習するメリット
中国語の声調練習において、単語やフレーズの意味から切り離し、声調のみに焦点を当てて集中的に練習することは、非常に大きなメリットがあります。
意味を考えながら発音練習をすると、どうしても内容に意識が向きがちで、声調がおろそかになってしまうことがあります。
しかし、声調だけに集中することで、脳が純粋に音のパターンを認識し、正確な発音をするための筋肉を効率的に鍛えることができます。



これは、スポーツ選手が基礎練習を反復して行い、特定の筋肉を鍛えるのと似ています。
例えば、「ma」「ma」「ma」「ma」と、同じ音節を第一声から第四声まで連続して発音する練習をしてみてください。
この際、意味は一切考えず、ひたすら音の高さの変化とリズムに集中することが大切です。
また、異なる声調の組み合わせ(例:「mama」「nana」など)を、やはり意味を気にせず繰り返し発音するのも効果的です。
初期段階では、単調に感じるかもしれませんが、この集中的な声調練習は、その後の語彙学習や会話練習の土台を強固にするために不可欠です。
地道な練習を続けることで、より流暢な中国語への近道となるでしょう。
声調とピンインの関係を正しく理解しよう
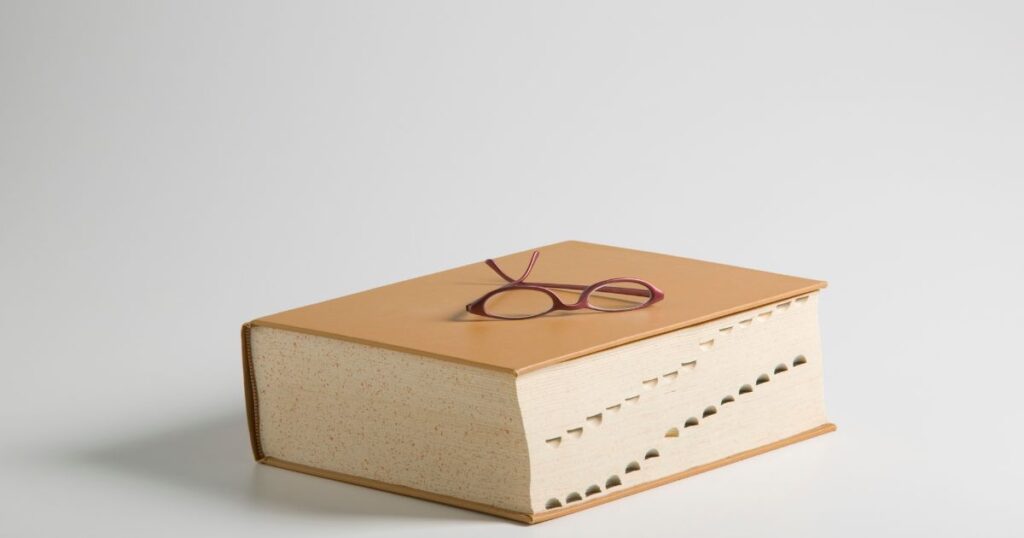
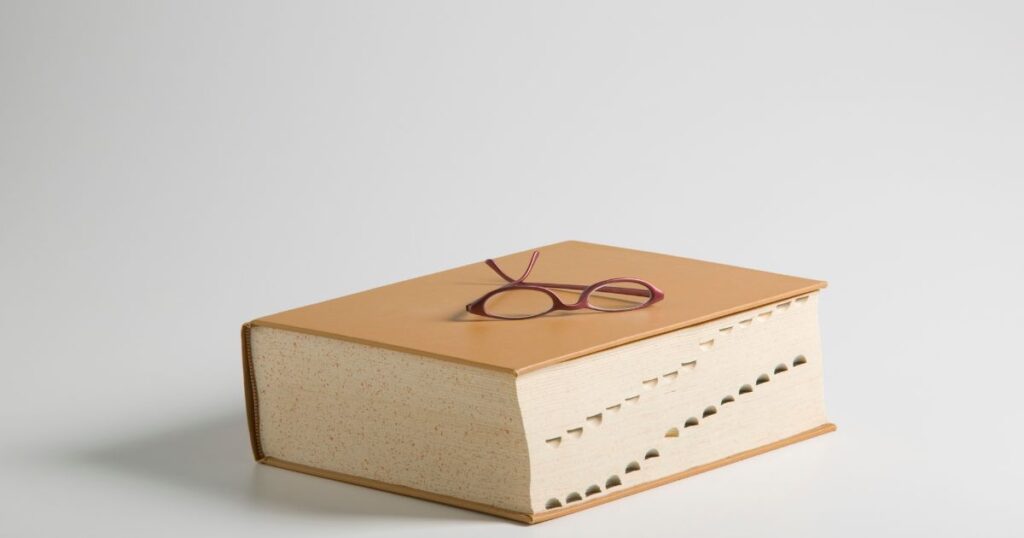
この章では、中国語の声調とピンインがどのように関係しているのかを詳しく解説します。
ピンインと声調記号の基本ルール
中国語の発音を正確に習得するためには、ピンインと声調記号の基本ルールを正しく理解することが非常に大切です。
ピンインは中国語の発音をローマ字で表したもので、声調記号はそのピンインの上に付けられ、音の高さや変化を示します。
これらのルールをしっかり理解していないと、正確に発音できないだけでなく、相手の言っていることも聞き取れない原因になってしまいます。
たとえば、同じ「ma」というピンインでも、声調記号が違うだけで意味が全く変わります。
一声の「mā」は「お母さん」、二声の「má」は「麻」、三声の「mǎ」は「馬」、四声の「mà」は「叱る」という意味になります。
声調記号はピンインの母音の上に表記され、複数の母音がある場合は、「a, o, e, i, u, ü」の順で優先されるという特定の規則があります。
ピンインと声調記号は中国語学習の最初の難関ですが、ここでしっかりと基礎を固めることが、その後の学習をスムーズに進めるための鍵となります。
発音記号の書き方や読み方を丁寧に学び、繰り返し練習を重ねましょう。
母音・子音ごとの声調のつき方のコツ



中国語の声調を正しく発音するには、母音と子音それぞれの発音の特性を理解し、それに合わせて声調を意識することが重要です。
ピンインは子音と母音の組み合わせでできており、声調は主に母音の部分に付きます。
しかし、子音の発音が不正確だと、その後に続く母音に乗る声調にも影響が出てしまいます。
また、特定の母音には声調がつきにくいという特性もあります。
例えば、単母音(a, o, e, i, u, ü)は声調が比較的つけやすいですが、複合母音(ai, ei, ao など)や鼻母音(an, en, ang など)では、どの母音に声調記号が付くかというルールがあります。
一般的には、口が大きく開く母音に記号が付きます。
子音についても、発音する際の息の出し方や舌の位置が声調の安定性に影響を与えるため、子音の発音自体も正確に行う必要があります。
ピンインの練習では、まず単音節の母音・子音の発音から始め、その後、それらに声調をつけて発音する練習に進むと効果的です。
これにより、各音の特性を理解した上で、声調を自然に乗せて発音できるようになるでしょう。
無気音と有気音の違いと発音の注意点
中国語の発音において、無気音と有気音の区別は非常に重要であり、声調と合わせて正しく発音する必要があります。
無気音と有気音は、同じ口の形で発音される子音でも、息の出し方によって全く意味が異なる単語が多く存在します。
たとえ声調が正しくても、この息の区別ができていないと、相手に違う意味で伝わってしまう可能性があります。
例えば、「b」(無気音)と「p」(有気音)、「d」(無気音)と「t」(有気音)、「g」(無気音)と「k」(有気音)などが代表的なペアです。
これらの子音に声調が付く場合、無気音は息をほとんど出さずに発音し、有気音は強く息を吐き出しながら発音します。
日本語にはない概念なので、習得するには意識的な練習が必要です。
ティッシュを口の前に置いて、発音したときにティッシュが揺れるかどうかを確認しながら練習すると、息の出方がよくわかります。



無気音と有気音は、声調と同様に中国語の発音の根幹をなす要素なので、それぞれの発音の特徴を理解し、区別して発音できるようになるまで、繰り返し練習を重ねて、よりクリアで正確な発音を目指しましょう。
j, q, x など中国語特有の子音と声調の関係
中国語特有の子音であるj, q, x など(そり舌音や歯茎硬口蓋音を含む)は、発音方法と声調の関係を理解することが大切です。
これらの子音は、日本語には存在しない発音なので、多くの学習者がつまずきやすいポイントです。
舌の位置や息の出し方が複雑で、もし不正確だと、その後に続く母音や声調にも悪い影響を与えてしまいます。
しかし、正確に発音できるようになると、より自然な中国語に近づけることができます。
例えば、「j」は舌の先を下の歯の裏に軽く当て、舌の真ん中を口蓋に近づけて息を出す音、「q」は同じ位置で息を強く吐き出す音、「x」は息を摩擦させて出す音です。
これらの子音の後ろには「i」や「ü」が続くことが多く、その際に「i」の声調が変化したり、発音される母音が特定の音になったりするルールがあります。
例えば、「ji」は「ジィ」、「qi」は「チィ」のように発音され、それぞれに声調が加わります。
これらの特殊な子音は、ネイティブスピーカーの発音をよく聞き、自分の舌の動きや息の出し方を意識しながら繰り返し練習することが大切です。
鏡を見ながら口の形を確認したり、発音練習アプリを活用したりするのも効果的です。
デジタルツールで声調学習を効率化


この章では、スマートフォンやパソコンなどデジタルツールを使って、中国語の声調学習を効率化する方法を紹介します。
デジタルツールを活用した声調学習には主に以下の内容があります。
- 声調記号の入力方法(パソコン編)
- 声調記号の入力方法(スマホ編)
- 声調学習におすすめのアプリ例
- 声調練習に役立つオンライン教材
声調記号の入力方法(パソコン編)
パソコンで声調記号を直接入力するのは少々大変なので、次のようなサイトを利用すると便利です。
- ピンイン変換サイト(「ピンイン変換」で検索すると複数あり)
- 翻訳サイト(Google翻訳など)
今すぐ必要な場合は以下をコピーしてお使いください。
| ā á ǎ à ō ó ǒ ò ē é ě è ī í ǐ ì ū ú ǔ ù ü ǖ ǘ ǚ ǜ |
また、声調符号は付ける位置が決まっています。
- aがあればaに付ける
- aがなければ、oかeに付ける
- iとuのみの場合は後ろの文字に付ける(iū/uī)
ピンインそのものではなく、中国語をピンイン入力する場合は、「設定」の「言語」から中国語簡体字もしくは繁体字を追加します。
詳しくはこちらもご覧ください。
【関連記事】中国語キーボードの設定と入力|おしゃれなアプリもあり
声調記号の入力方法(スマホ編)
中国語キーボードに切り替えたら、母音キーを長押しすると声調記号付きの候補が表示されます。
「ü」は「v」キーを押します。
テキスト入力時にキーボードアイコンをタップして切り替えると、iPhoneと同様に母音キーを長押しすることで声調記号付きの選択肢が表示されます。
Google GboardやMicrosoft SwiftKeyなどでも同様の操作が可能です。
新しく覚えた単語を声調記号付きでメモアプリに記録する習慣をつけると、声調に対する感覚も自然と養われます。
声調学習におすすめのアプリ例
スマートフォンアプリでも声調の練習ができます。
例)
- HelloChinese:AIによる発音評価や声調の視覚的表示あり
- 超・中国語耳ゲー:間違いやすい発音の聞き分けに特化
- ChineseSkill:ゲーム感覚で学べる総合的な中国語学習
- Super Chinese:AIを活用した発音評価システムあり
- Ka – 中国語の発音とリスニング:発音とリスニングに特化
(アプリの情報は変動する可能性があるため、利用前に最新の機能や評価をご確認ください。)
アプリは手軽にできるのが魅力です。
スキマ時間を利用して活用してみてくださいね。
声調練習に役立つ無料のオンライン教材
インターネット上には質の高い無料の声調練習教材が豊富にあります。
解説とお手本を見られる動画で練習して、ネイティブにチェックしてもらうのがおすすめです。
例)
【YouTube】
- 李姉妹ch 【保存版】中国語の声調が確実に上達する練習法◎1人でもできる自己チェック!
- ちゃいなさぷり@高卒のプロ通訳 中国語の声調16個を一気に練習!組み合わせでスムーズにマスター
- 毎日中国語のかね 【永久保存版】これ一本で声調・四声を完全マスター!【中国語発音】
- 毎日中国語の阿波連 【衝撃の事実】声調が定着しないのは声調を考えるから!?【中国語発音】
【言語交換】
- HelloTalk
- Tandem
独学でもできる声調チェックと実践的な発音練習方法


この章では、独学でもできる声調チェックと、より実践的な発音方法を紹介します。
自分では正しく言っているつもりでも、ネイティブが言うと違って聞こえることがあります。
以下の内容を見ていきましょう。
- 自分の発音を客観的にチェックする方法
- 声調の間違いで起こる失敗談と対策
- 実際の会話で声調を活かすコツ
自分の発音を客観的にチェックする方法
ネイティブスピーカーの指導がなくても、自分の声調発音を客観的に評価・改善することは可能です。
最も手軽な方法は録音比較法です。



スマートフォンやPCで自分の発音を録音し、教材の音声やネイティブの発音と比較します。
特定の単語やフレーズを繰り返し録音して改善の進捗を確認したり、再生速度を遅くして声調の変化をより詳しく分析したりできます。
また、音声入力を利用して、中国語が正しく入力されるかどうか試してみるのも1つの方法です。
発音が間違っていると意図せぬ漢字に変換されてしまいます。(最近は認識機能が高まっているので、多少間違っていても文脈から正しく入力されてしまうこともあります。)
音声入力は翻訳アプリやAIなどのほか、中国語のキーボードにも付いています。
試してみてくださいね。
声調の間違いで起こる失敗談と対策



中国語は声調が異なると別の意味になるため、時にとんでもない誤解を招いてしまうことがあります。
例えば、「買う」と「売る」はピンインがどちらも「mai」で声調だけが違います。
「買いたい=我要买(wǒ yào mǎi)」を間違えて「wǒ yào mài」と言うと、全く逆の「我要卖(売りたい)」という意味になってしまいます。
さらに、「お尋ねしますが…」の「请问(qǐng wèn」を「qǐng wěn」と発音すると、なんと「请吻(キスして)」になってしまいます!
このようなあらぬ誤解を避けるためにも、よく使う単語は声調をしっかり確認し、相手に正しく伝わっていないと感じたら別の言い方に言い換えたり、ジェスチャーを交えるなどして、意思疎通を図っていきましょう。
実際の会話で声調を活かすコツ
学習の初期段階では1つ1つの声調を正しく理解することが大切ですが、実際の会話では感情や文脈によって抑揚があります。
例えば、強調したい単語は声調をより明確に、それ以外は軽めに発音します。
また、質問文では文末が上がる傾向があります。
はじめはゆっくりでも正確に発音することを心がけ、徐々に自然な話し方に近づけていきましょう。
まとめ


- 第一声:汽笛の「ポー」のような高くて平らな音
- 第二声:驚いた時の「ぇえ?」のような上がる音
- 第三声:がっかりしたときの「あ〜あ」のような低く抑えた音
- 第四声:返事をする時の「はい!」のような高い音から下がる音
- 「第三声」「一」「不」は声調が変化する
中国語は4つの声調と軽声があり、声調によって意味が変わる言語です。
声調を間違えると、「買いたい」が「売りたい」になってしまうような大きな誤解を招いてしまう恐れがあります。
YouTube動画や録音機能などを使って、正しい声調を身につけていきましょう。
はじめは声調の組み合わせごとにゆっくり1つずつ確実に、慣れてきたら徐々に長い文を自然なスピードと抑揚で読めるようにしていきます。



声調が正しいと通じやすくなり、発音に自信が持てるようになりますよ。
独学で難しい場合は、毎日中国語公式LINEまでお気軽にご相談くださいね。