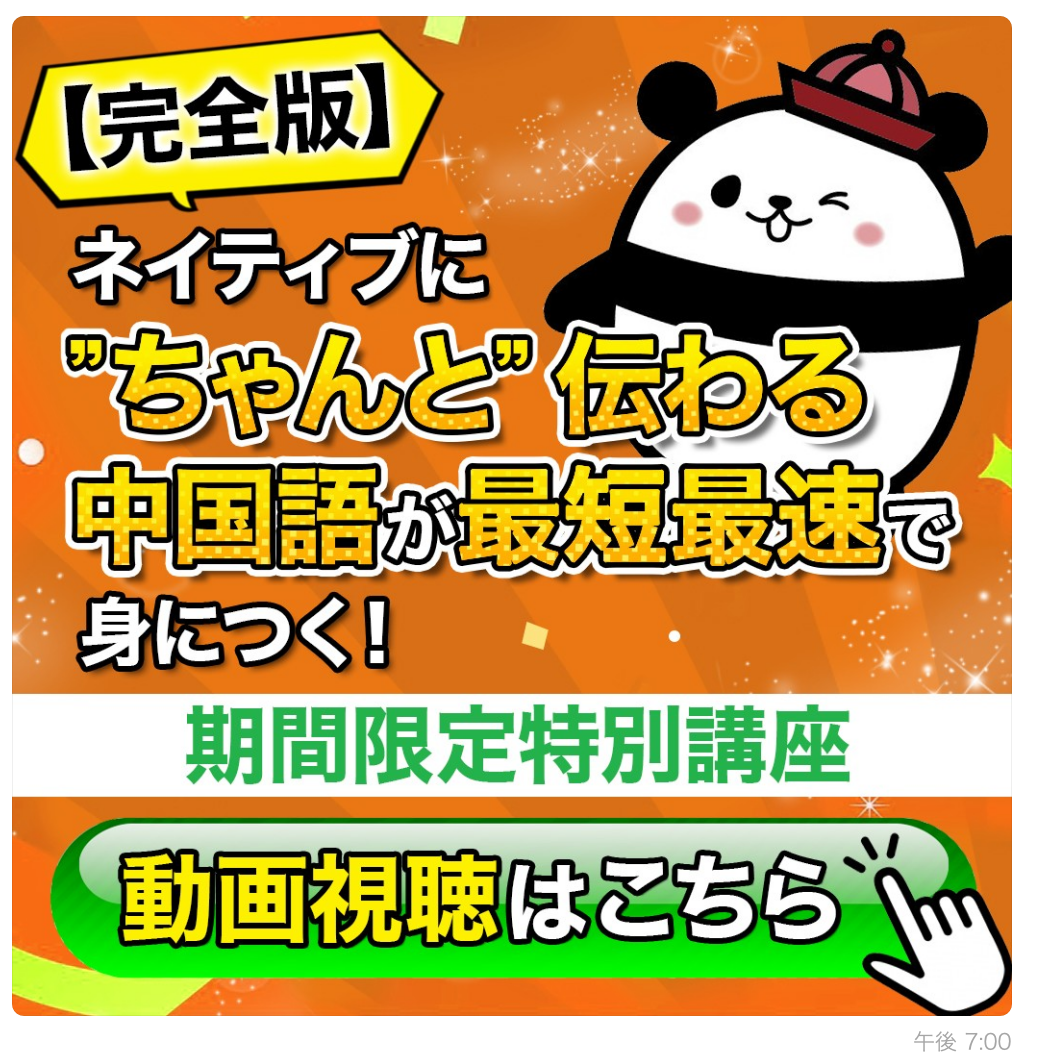
\ 期間限定動画無料配布中 /
中国語の標準語は北京語でしょうか?
実はこれにはちょっとした誤解があります。
中国語の標準語は、北京語の発音を基にしていますが、完全に一致するものではないのです。
例えて言うならば、東京の江戸弁と日本語の標準語のような違いがあります。
中国語の標準語は「普通話/マンダリン」と呼ばれ、中国全土で使用されます。
この記事では、中国語と北京語の関係性から多様な方言、簡体字と繁体字、中国語学習のポイントまで幅広く紹介します。

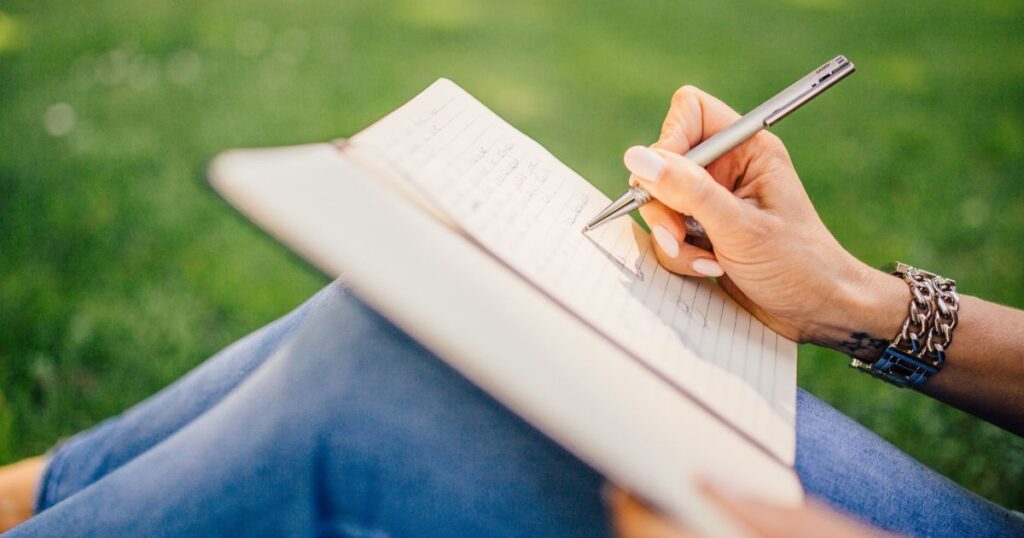
この章では、「中国語」と「北京語」の関係性や基本的な違い、そして中国における言語の多様性について紹介します。
中国はとても国土が広く、たくさんの方言があります。
お互い方言で話すと通じないため、標準語が定められています。
北京語が中国語の標準語だと思っている人も多いですが、実はちょっとした違いがあります。
その違いと、その他の地域の方言を見ていきましょう。
多くの人が「中国語=北京語」と思いがちですが、実際にはこれらは完全に同一ではありません。
標準語(普通話/pǔ tōng huà)は北京語の発音を基盤として20世紀半ばに標準化されたものです。
北京語は北京とその周辺で話される地域方言である一方、標準語は中国全土の公用語として採用されています。
両者の大きな違いは、標準化の過程で北京語特有の地域性が排除されたことです。
例えば、北京語では「儿化音」と呼ばれる巻き舌のような音が頻繁に使われますが、標準語ではその使用頻度が低くなっています。
「一点儿」(ちょっと)という表現は、北京語では「yì diǎnr」と発音し「儿」の音を強調しますが、標準語ではこの特徴が薄れます。
また、北京語には地元特有の表現や語彙もあります。
中国語学習者が学ぶのは一般的に「普通话」と呼ばれる標準語です。
普通話は中国全土の教育機関やメディア、ビジネスシーンで広く通用します。
「中国語」と一口に言っても、実際には相互理解が困難なほど異なる複数の方言グループから成り立っています。
これらは単なる「なまり」の違いではなく、ヨーロッパのロマンス諸語(フランス語、スペイン語など)に匹敵するほどの差異があります。
中国の方言は大きく分けて、7大方言、8大方言、10大方言などと分類されますが、この中にも非常にたくさんの方言があり、隣の村に行くだけで言葉が通じないということもあります。
7大方言の1つ「官話」は最大の方言グループで、北京語もこの中に含まれます。
『Ethnologue,2024』によると、約8億1300万人の話者を持ち、中国北部と南西部に広く分布しています。
他には粤語(広東語)が香港や広東省で約8560万人、呉語(上海語)が上海周辺で約8340万人、閩語(福建語)が福建省や台湾で7000万人以上、客家語は中国南部で約4990万人に話されています。
これらの方言の多様性は、中国の広大な国土と長い歴史的分断によって生まれました。
特に南部の山岳地帯では地理的要因が言語の均一性を阻み、多様性が顕著に見られます。

この章では、標準中国語(普通話)と中国の主要方言の違いについて紹介します。
中国語について理解を深めていきましょう。

北京語と広東語は同じ「中国語」に分類されますが、発音体系、特に声調の数と種類において大きく異なります。
北京語には4つの基本声調と1つの軽声があります。
これに対し広東語には6〜9つの声調があり、はるかに複雑な発音体系を持っています。
これらの違いは地理的・歴史的要因によるもので、北京語は中国北部で発達し比較的シンプルな声調システムを持つ一方、広東語は南部の言語的多様性が高い地域で独自の発展を遂げました。
例えば、「ma」という音は北京語では声調によって「妈(mā)」(お母さん)、「麻(má)」(しびれる)、「马(mǎ)」(馬)、「骂(mà)」(罵る)など異なる意味を持ちますが、広東語ではさらに多くの意味の区別が可能です。
また、北京語に存在する巻き舌音(そり舌音)の一部は広東語には存在しません。
一言に「中国語」と言っても、このような大きな違いがあるのです。



中国の主要方言である北京語、広東語、上海語はそれぞれ独自の特徴があります。
北京語は北京を中心に話されていて、「儿化音」という舌を巻く音が多いのが大きな特徴です。
漢字は簡体字を使用します。
広東語は香港、マカオ、広東省を中心に話されており、標準語より声調が多いのが特徴です、
香港やマカオでは繁体字を使用します。
また、広東語は香港の映画や音楽を通じて国際的にも広く知られています。
上海語(呉語の一種)は上海および江蘇省、浙江省の一部で話され、発音と声調が独特です。
舌を巻く発音が少ないため、日本人にとって比較的言いやすい単語があります。
これらの方言は基本的な文法構造や語彙に共通点はありますが、発音や日常会話で使われる単語は大きく異なります。
例えば「こんにちは」は北京語では「你好(nǐ hǎo)」、広東語では「nei5 hou2」と全く異なる発音になります。
中国語の文字には簡体字と繁体字の2種類があり、地域や目的によって使い分けられています。
簡体字は、画数を減らしてシンプル化した漢字です。
一方、繁体字は伝統的な字形を保持した漢字で、見た目も複雑です。
例)
| 簡体字 | 繁体字 |
| 国 | 國 |
| 马 | 馬 |
| 乐 | 樂 |
| 体 | 體 |
| 买 | 賣 |
中国本土では主に簡体字が使われ、香港、マカオ、台湾では繁体字が使用されています。



中国語を勉強する際は、中国本土との関わりが中心なら簡体字を、香港や台湾との関わりが中心なら繁体字を優先的に学ぶと効率的です。
長期的には両方に慣れておくと便利ですが、はじめは混乱を避けるためにも、どちらか一方から始めるのが良いでしょう。
台湾で使われる中国語(台湾標準語/国語)と中国本土の標準語(普通話)には、発音、語彙、文字使用において顕著な違いがあります。
まず漢字は、台湾では繁体字を使用するのに対し、中国本土では簡体字を使用します。
発音面では、共通している部分が多いものの、一部の発音が異なります。
例えば「和」の字は、北京語では通常「hé」と読まれますが、台湾では「AとB」のような接続詞として使われる場合に「hàn」と読まれることもあります。
語彙面でも違いがあり、例えば「タクシー」は台湾では「計程車」、大陸では「出租车」です。
また台湾では日本統治時代の影響で日本語からの借用語が多く、中国本土では英語から直接翻訳された語彙が多い傾向があります。
しかし基本的な文法構造は共通しているため、どちらかを学べばもう一方も大きな困難なく理解できるようになります。


この章では、マンダリン(普通話)の効果的な学習方法を紹介します。
マンダリンの語源は「役人が使っている言葉」ですが、現在では「標準語(普通话)」という意味で言われています。
マンダリン、すなわち中国標準語の学習は、声調と簡体字の習得が大きなポイントになります。
マンダリンを学ぶ上で最初の大きな壁となるのが、4つの声調と軽声の習得です。
声調は意味を区別する重要な要素で、同じ発音でも声調が違えば全く別の意味になります。
声調は視覚的にイメージすると覚えやすく、第1声(ā)は高く平らな線、第2声(á)は上昇する斜め線、第3声(ǎ)はV字型、第4声(à)は下降する斜め線で表現されます。
これらに加えて、軽く添えるように発音する軽声もあります。
同時に、ピンイン(拼音)の基礎をしっかり学ぶことも大切です。
ピンインは中国語の発音をアルファベットを使って表したものです。
特に、日本語にない音には注意が必要です。
練習は、ネイティブの音声を聞いてすぐに真似るシャドーイングや、自分の発音を録音して確認する方法も効果的です。
毎日少しずつ継続的に練習することが上達の鍵です。
声調については下記の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】中国語の四声(声調)とは?発音を練習するコツや声調変化のルールも紹介
日本人が簡体字を学ぶ際は、日本語の漢字知識を活用しつつ、簡体字の特徴や規則を覚えるのが効率的です。
例えば「語」は簡体字では「语」、「話」は「话」です。
「ごんべん」が変化していますよね。
このように偏や旁の変化を覚えると、推測がしやすくなります。
また、日本語と簡体字では同じ漢字や似ている漢字が多くあります。
例)
覚える際は、手で書いて練習するのが記憶に定着しやすいです。
日本語と形が異なる漢字を中心に書き取りましょう。
Ankiなど単語カードアプリも役に立ちます。
さらに、簡体字のみではなく、中国語の学習と並行することで、単語や文脈を通じて簡体字を自然に覚えることができます。



中国語の発音(ピンイン)も一緒に学ぶと、より実用的です。
中国語を翻訳する際は、単なる言葉の置き換えだけでなく、言語構造の違いや文化的背景を理解することが重要です。
まず、中国語の基本語順は「主語-動詞-目的語」で、修飾語は被修飾語の前に来ます。
例えば「我在北京学习中文」(私は北京で中国語を勉強している)のような構造になります。
また、中国語には名詞の前に特定の量詞が必要で、「一本书」(一冊の本)、「三杯茶」(三杯のお茶)というように使います。
時制表現の違いも注意が必要で、中国語には動詞の活用がなく、時間を表す副詞や文脈で時制を表現します。
地域による言語の違いも重要なポイントで、中国本土と台湾、香港などでは同じ概念でも異なる語彙が使われることがあります。
例えば「自転車」は中国本土で「自行车」、台湾では「腳踏車」と言います。
成語(四字熟語)や婉曲表現などの文化的要素も正確に訳すためには背景知識が必要です。
翻訳ツールは便利ですが、微妙なニュアンスや文化的要素は人間による確認が欠かせません。
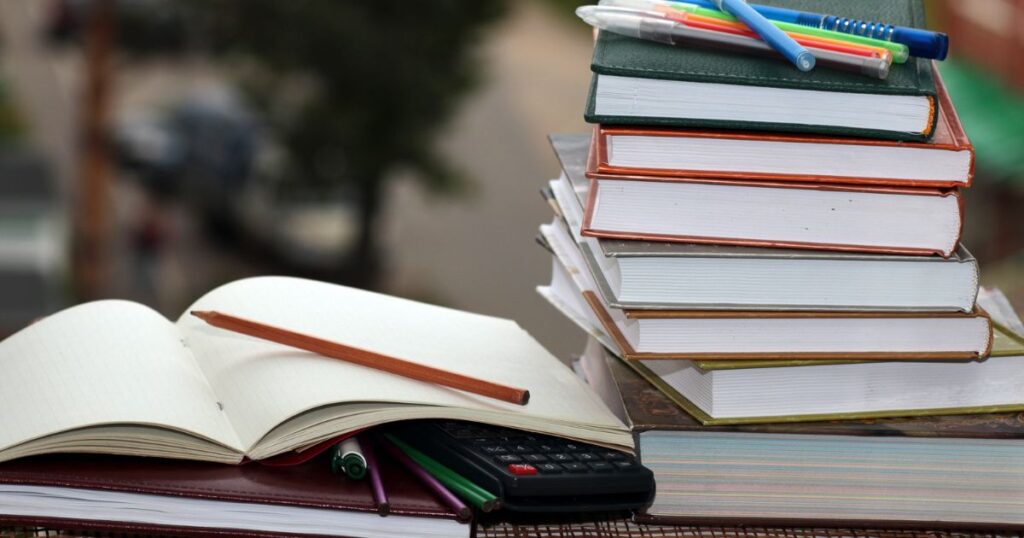
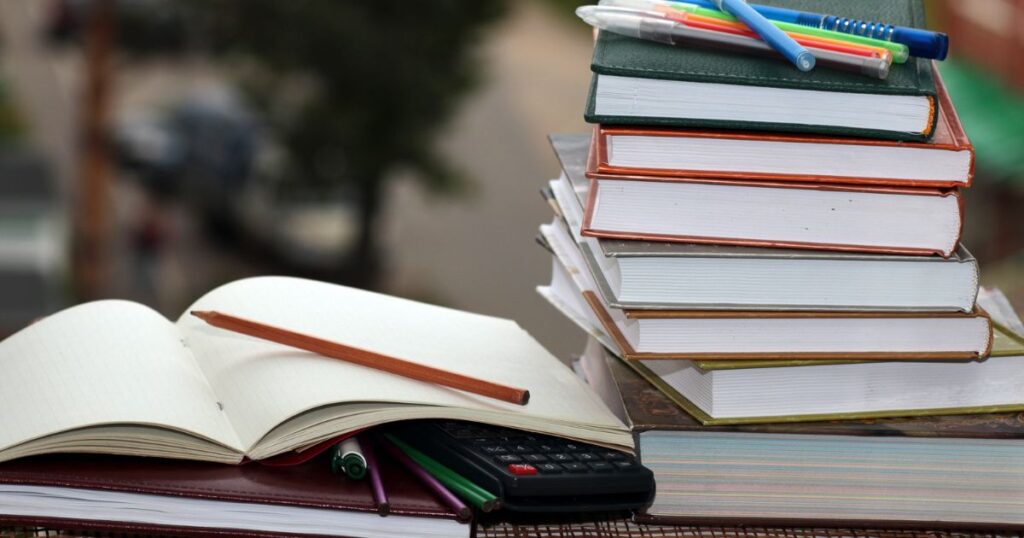
この記事では、中国語と北京語の関係性から中国各地に広がる方言の多様性、そして中国標準語(マンダリン)学習のポイントまで幅広く解説しました。
中国語の標準語が北京語だと思われることもありますが、この2つにはやや違いがあります。
また、「中国語」は単一の言語ではなく、相互理解が困難なほど異なる方言が多く存在します。
私たちは中国全土で通用する標準語(マンダリン/普通話)を学べば、中国全土で意思疎通を図ることができます。
学習の際は、声調と簡体字を重点的に練習しましょう。
独学で難しい場合は、毎日中国語公式LINEまでお気軽にご相談くださいね。
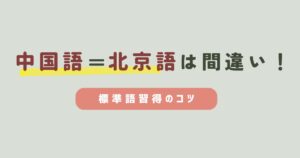
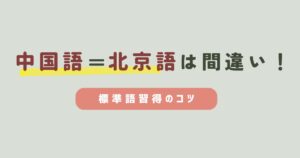
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
